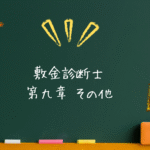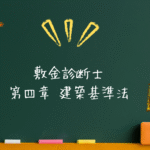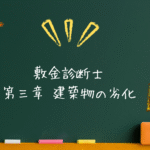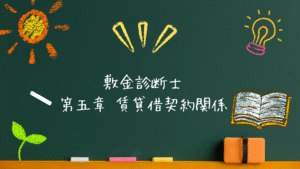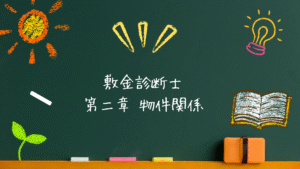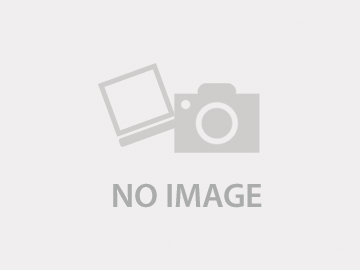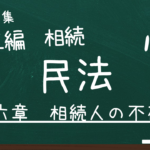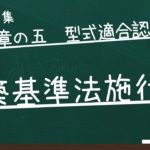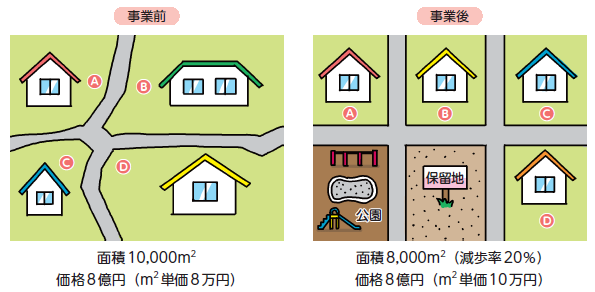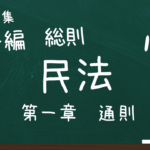第1節 建築構造
一 材料等による分類
建築物は下記にあるように、様々な材料を用いて作られる。 各構造はそれぞれ 単独の形式で用いられることが多いが、一つの建築物において、 異なった構造形 式を組み合わせて一つの建築物を構成することもある。
1. 木構造
樹木を伐木造材、 製材し、 それを用いて建築物を建築する構造。 柱や梁 どで建築物の骨組み (軸組み) をつくり、 その後壁を付けていく 「在来軸組工 法」 や、 床と壁で建築物を組み立てていく 「ツーバイフォー工法」 などがある。 木造は、他の構造に比べ自重が小さい、じん性が高い、 加工が容易といった 特徴がある反面、 火には弱い。
2. 鉄骨構造 (鋼構造 S造)
構造上主要な部分に、 形鋼 鋼板などの鋼材を用いて組み立てる構造。 長所 として、 ①RC造に比べて自重が小さい、 ② RC造に比べてじん性が高い、③ 鋼材の持つ優れた強度とじん性により高層建築 大スパン構造が容易、④他の 方式に比べ工期が短いといった特徴がある。もっとも、 短所として、 ①熱に弱 いため耐火被覆が必要、 ②錆びに弱いため防錆処理が必要 ③断面積が小さく 部材が長いと変形・座屈を生じやすい、 ④RC造に比べて耐火・遮音・耐振動 性に劣るといったものが挙げられる。
3. 鉄筋コンクリート構造(RC造)
鉄筋とコンクリートの長所を生かすように合理的に組み合わせた一体構造。 長所等として、耐震性・耐火性・耐久性に優れる、 ②目的によってかなり自 由に構造形式を決められる、といった特徴がある。もっとも、短所等として、 ①自重が大きい、 ② 解体除去 移築が困難、 ③工期が比較的長いといったものが挙げられる。
4. 鉄骨鉄筋コンクリート構造 (SRC造)
鉄骨鉄筋コンクリートを一体化した構造で、 鉄骨の周囲に鉄筋とコンクリ ートをめぐらせたもの。 鉄筋コンクリート構造よりさらに強さと粘りのある耐震耐火構造といえる。長所等として、 ① 耐震性・耐火性・耐久性に優れる ② RC造に比べて、 柱・梁等の比較的小さな断面に多量の鋼材を納めることがで きる、③鉄骨を用いることで、柱・梁等の部材・形状を小さくすることができ あるといった特徴がある。もっとも、短所等として、 ①RC造以上に解体・除去・ 移築が困難、 ②RC造以上に工期が長くかかる、 といったものが挙げられる。
5. 鋼管コンクリート構造 (CFT造)
チューブ状の鋼管の中にコンクリートを詰めて主要構造材 (主に柱)とした もの。 RC造と同様、鉄とコンクリートが特性を補い合い、優れた性能を有す る。 大スパンが可能で、 中性化も生じにくい等の長所がある。
二 力学的構造形式による分類
1. ラーメン構造
柱・梁といった部材の各節点を剛接合し、 一体となるように構成したもので、 柱・梁は主として曲げ強度で外力に抵抗する構造。高層建築物に適し、 S造、 RC造 SRC造、CFT造など多くの建築物において採用される。部材と部 材が剛接合されていることから、ある部材に力がかかると他の部材にもそれが 及び、各部材に荷重が分散するので、強く変形しにくい構造となる。
2. 壁式構造
鉄筋コンクリートの壁や床などの平面的な構造体のみで構成される構造で、壁体とスラブの剛性に頼り、柱の代わりに壁で建築物荷重を支える。 主として小規模なRC造の建築に採用される。 柱や梁などの凹凸がないため、空間を広く使えることが特徴として挙げられる。
三 地震と建築物
1. 地震と建築基準法
日本の耐震設計基準は、過去の地震災害を教訓に基準設定と改正とを繰り返 してきており、現在は、1981年に制定された 「新耐震設計基準」に落ち着いて いる。この現行の耐震基準 (新耐震基準)は、1981年(昭和56年)6月1日 以降に建築確認を受けた場合に適用されており、 震度5強程度の中規模の地震 に対して「ほとんど損傷を生じない」状態に、 また、 震度6強~震度7程度の 極めて稀にしか発生しない大規模の地震に対しても 「人命に危害を及ぼすよう な倒壊等の被害を生じない」 状態にあることを目標としている。
2.地震と耐震設計上の注意
地震への対策を考える場合、 平面形状としては、できるだけ単純でまとまり の良いものとすること、 建築物の重心と剛心とをできるだけ近づけるようにす ることが大切とされる。 また、 建築物の高さとしては、できるだけ均等とした ほうがよい。 さらに、 高さ方向の耐力要素の配置としては、バランスよく配置 することが望まれる。この点、 建築物を支持する独立の柱が並ぶ吹きさらしの空間であるピロティ は、 壁量が不足しているため、一般に耐震性能上の弱点となりやすい。それゆ えピロティ構造はバランスの崩れやすい構造といえ、 耐震性について十分注意 する必要がある。
3. 地震対策
① 構造による対策
地震への対策としては、まず、構造面での対策が考えられる。 耐震の構造 には、「構造」と「柔構造」 とがあるが、前者は、地震がきても建築物自 体は変形せず、建築物全体がゆれるような構造である。後者は、しなやかで 柔らかい構造である。構造での地震対策をより具体的すると、 ①地震に対応するために建築物自 体の剛性を高めた耐震構造、②建築物の基礎と上部構造との間等に積層ゴム や滑り機能を持つ免震装置を設けて、地震力に対して建築物がゆっくり水平 に移動するようにした免震構造、③建築物の骨組みに取り付けた制震装置に より、地震や風による揺れを吸収して小さくし、耐震安全性や居住性の向上 を図った制震構造などである。
②接続方法による対策
地震の振動に対する構造物に生じる応力や変形性状を制御するため、ある いは、コンクリートの硬化収縮によるひび割れを防止するために、 「エキス パンションジョイント」という建築物の接続方法がある。 建築物を2つ以 上に区切り、 壁、床、天井、 設備の全てを伸縮金具などで接合するものであ る。
③ 耐震補強による対策
既存の建築物に耐震補強を施すことにより、 耐震性を高めることができる。 具体的には、 建築物の耐力の増大を目的として、 ①耐震壁の増設、 ②鉄骨ブ レースの設置、 ③壁の厚さの増大、 ④柱と一体化した袖壁の設置などが考え られる。 また、 柱のじん性の向上を目的として、 ① 柱に薄型鋼板や炭素繊維 シート等を巻く、 ②柱に帯筋や溶接金網を巻き柱を太くすることなどが考え られる。 さらに、 梁のじん性の向上を目的として、1炭素繊維シートをスラ ブ下の梁に張ることなどが考えられる。なお、柱と一体化した腰壁及び垂れ壁は、耐震上不利となる。 ただし 柱 と腰壁や垂れ壁の間に構造スリットを設ける事により、耐震性を改善する事 が可能である。
第2節 建築部材
一 建築物・部材に作用する様々なカ
1. 建築物に作用する力
建築物が外部から受ける力のことを総称して荷重という。 これは長期荷重と 短期荷重とに分けられ、構造計算上は、固定荷重、 積載荷重、積雪荷重、風圧 力、地震力などがある。
① 固定荷重
建築物の躯体の重量と仕上材料の重量を総称した、 建築物自身の重量のこ と。 原則として、 建築物の各部の固定荷重は、その建築物の実況に応じて計 算しなければならないが、屋根、 床、 壁等について、 建築物の部分別に定め られた数値により計算することができる。
②積載荷重
建築物の床に加わる建物内の人並びに物品で、 移動が比較的簡単にできる ものの重量のこと。 原則として、 建築物の実況に応じて計算しなければなら ないが、 住宅の居室、 事務室、 自動車車庫等、 室の種類別に定められた数値 で計算することができる。
③ 積雪荷重
積雪重量が建築物に外力として作用する荷重のこと。 「積雪の単位荷重」 に 「屋根の水平投影面積」、 「特定行政庁が定めるその地方における垂直積雪 量」 を乗じて計算する。
④ 風圧力
建築物が強風を受けたときにかかる力のこと。 建築物の屋根の高さやその 地方における風の性状等により計算される 「速度圧」 に、 建築物の断面や平 面の形状により定まる 「風力係数」 を乗じて計算する。
⑤ 地震力
地震による揺れを、静的に評価して設計荷重として用いる力のこと。 地上 部分にある建築物のある層に作用する地震力は、その層の高さに応じ、その 層が支える荷重(固定荷重、積載荷重、多雪区域においては積雪荷重)に、 その層に対する「地震層せん断力係数」を乗じて計算する。 なお、地域性を 考慮した「地震地域係数」は、各地方における過去の地震の記録に基づく被 害の程度、地震の活動状況等に応じて定められる。
2. 部材にかかる力
① 圧縮力
中心に向かって互いに内向きに作用する力。
② 引張力
中心から互いに外向きに作用する力のこと。
③ 曲げモーメント
部材を湾曲させる力によって断面に発生している力のこと。
④ せん断力
互いに逆向きの力が働くことで発生する、部材を斜めに切断しようとする力のこと。
⑤ ねじれ力
部材の両端に軸方向に垂直に反対方向の曲げが加わることによって、軸の 周りに発生する回転力のこと。
二. 各部位の特徴
① 壁 (耐震壁)
ラーメン構造において、構造計算上、 主として地震力等の水平過重に対して、 有効に応力を負担させるように設計された壁のこと。 地震の際に壁にかかる水 平力は、壁を断ち切る力となるので、それに抵抗するものとしてのせん断補強 筋を有効に配筋する必要がある。
②柱
屋根や床の荷重を支え、基礎に伝える役割をもつ鉛直の部材のこと。 建築物 の隅角部や壁の交わる部分に配置されるが、できるだけ等間隔・規則的に配置 し、上下同じ位置に重なるように配置するのが通常である。
③ 床
建築物の中で人や物を直接支える部分。
④ 梁
柱の上部で柱と柱を架け渡す水平材のこと。 大梁と小梁がある。 大梁は、通常、床荷重による応力を受けるだけだが、地震時には強い曲げモーメントとせ通ん断力をも受ける。 他方、 小梁は、 床荷重のみを支持し、その荷重を大梁に伝える。
⑤屋根
壁・床とともに、建築物の内部空間を外界から区切るもので、強い日差しや 風雨等から内部を守り、 快適な環境を整える役割を果たす。
⑥ 階段
建築物で上下階を移動するための昇降用の通路のこと。 階段の踏板の有効部分を踏面といい、 階段の段差の寸法を蹴上という。
第3節 建築材料
一. 構造材料
1. コンクリート材料
コンクリートの組成は、一般にセメント、水、 骨材 (細骨材・粗骨材) 和材料、空隙からなる。空気・水・セメントを混ぜたものを「セメントペース ト」、空気・水・セメント・細骨材(砂)をまぜたものを「モルタル」、 空気・ 水・セメント・細骨材(砂)粗骨材(砂利)をまぜたものを「コンクリート」 という。コンクリートの容積の約70%は骨材で占められ、これがコンクリートの性質 に大きな影響を及ぼす。 また、残りのセメントペーストも、コンクリートの強 度、耐久性等の性質に極めて大きな影響を及ぼす。
2. セメント
水と反応して硬化する鉱物質の粉末で、一般にセメントという場合には、通 常、ポルトランドセメントを指す。 このポルトランドセメントは、石灰石・粘 土・けい石などを主原料とし、これらを約 1,450℃で焼成した後、適量の石膏 を加え、粉砕して作られる。セメントと水を混ぜると水和反応を生じ、 普通ポルトランドセメントで40℃ ~50℃の水和熱を発して固まる。 これを水硬性という。
3. コンクリート用骨材
コンクリート用骨材は、骨材の粒の大きさ、比重、 産地 生産加工等により、①細骨材 粗骨材、 ②普通骨材・軽量骨材 重量骨材、 ③天然骨材・人工骨材などに分類される。
4.混和材料
コンクリート又はモルタルの性質を改善し、かつ、 新しい特性を付与する材 料を混和材料という。 代表的なものには、 ①AE剤、 ② 減水剤 ③ フライアッシュなどがある。①のAE剤は、空気連行剤とも呼ばれる界面活性剤の一種である。微小な気 泡を均質に分布させてセメント粒子を分散させ、余分な水を抑えながら水和反 応を高めて、コンクリートのワーカビリティ及び耐久性を向上させる。
②の減水剤は、セメントの粒子を分散させて使用水量を減少させ、コンクリートの均質性、作業性を改善し、強度水密性を増進させる。③のフライアッシュは、微粉炭を燃焼させたときのすすである。 ルシウムの流出防止、コンクリートのワーカビリティの改善、 乾燥収縮の抑制、 水酸化力 コンクリートの密実性を高めるといった効果がある。
5. ワーカビリティ
コンクリートを完全に流し込むための作業のしやすさのこと。 このワーカビ リティの程度を図る代表的な方法として、スランプ試験がある。 これは、メガ ホン状の鉄製スランプコーンに、フレッシュコンクリートを詰め、一定の作業 の後にコーンを抜き取り、 コンクリートの下がり具合を測ることで把握する。 下がり具合を 「cm」 で表したものを 「スランプ値」といい、値が大きいほど ワーカビリティが高いということになる。
6. 水セメント比
コンクリートを生成する際のセメントに対する水の重さの割合のこと。 一般 には 50~60%とされる。 コンクリートの圧縮強度は、基本的には水セメント比 により定まり、 水セメント比が小さいほど強度が高い。 しかし、水セメント比 が小さいほど、 逆にワーカビリティは低くなる。
7. 軽量コンクリート
一般に、 普通コンクリートよりも骨材の比重が小さいもの (2.0 以下)を軽 コンクリートという。 断熱効果が大きく、間仕切り壁などに用いられる。
8. 気泡コンクリート
内部に多量の小気泡を含ませて作った多孔質のコンクリートのことをいう。 主原料は、セメントなどの強度発現材とアルミニウム粉末などの発泡剤である が、充填材としての骨材、化学反応調整剤等も必要となる。軽量で、断熱性、耐火性に優れている。 しかし、吸水性が高いため、用いる 場所によっては、防水処理が必要となる。
二. 非構造材料
① 木材
木材は、 湿気に対して腐りやすいため、特に最下階の床下に用いる場合には、 防腐処理が必要である。 また、 含水率が大きいと腐朽菌の害、シロアリ等の 害を受けやすいため、含水率の小さい乾燥状態で使うことが重要である。
② 集成材
挽き板 (ラミナ) 又は、 小角材などを、 繊維方向を平行に接着剤によって集 成したもの。 大断面長大材を作ることができるという利点があり、 構造材・ 内装材などとして用いられる。
③合板
単板 (ベニヤ) を、 繊維方向が交互に直交するように積み重ね、 接着剤で貼 り合わせたもの。 単板に比べて温度による狂いや膨張収縮の方向性が少ない。
④ 繊維板 (ファイバーボード).
木材 紙などの植物質繊維を主な原料として作った板材料の総称。(5パーティクルボード (チップボード)木材のチップに接着剤をつけ、 熱圧成形した面材のこと。
⑥ 粘土製品
粘土を主原料として、水練り成形したのち、焼成したもの。一般に、耐水・ 耐火・耐久性に優れ、 形を自由に作れる利点がある。もっとも、引張・曲げに 対する強度が低く、 衝撃性に弱く、加工性・接着性に劣るという短所もある。
⑦ガラス
酸性酸化物及び塩基性酸化物の1種以上を調合し、 1,400℃~1,600℃の高温 で融解して、結晶しないように固化させたもの。
⑧石材
岩石を所要の形状に切断成形したもの。 自然石と人造石がある。
⑨石膏ボード
焼石膏を芯材にし、 両面に石膏液を染み込ませた厚紙を張り、圧縮成形した面材。 防火性・遮音性に優れ、内装下地材として天井及び内壁に多用される。
三. 建築物と熱
1. 用語
① 熱損失係数
建築物の断熱性能を総合的・ 数値的に表したもので、 建築物各部位の熱損 失量と換気による熱損失量とを合計したものを、 延べ床面積で除することに よって算出する。 この値が小さいと断熱性能が高いことを意味する。
②熱貫流
壁、床、 屋根等を通して熱が出入りすることで、 室内の空気から屋外に熱 が伝わること。 壁の内部で一方表面から他方表面へ材料中を熱が移動する 「熱伝導」 と空気から壁の表面へ又は壁の表面から空気へ熱が伝わる 「熱伝 達」 とがある。 この外壁等の建築物の各部位について熱の通過しやすさを示 す値を熱貫流率といい、 値が小さいと熱を通しにくいことを意味する。
2. 内断熱と外断熱
構造躯体の屋内側に断熱層を設けるものを 「内断熱」、 構造躯体の外気側に 断熱層を設けるものを 「外断熱」 という。 建物の断熱性を向上させ、 結露を防 止する観点から、 外壁に外断熱を施す例が見られる。
3. 結露
結露は、 水蒸気を多く含む、湿った空気が、温度の低い壁や窓ガラスの表面 に接し、飽和水蒸気量を超えたものが結晶化することで生じる。 カビ等の原因 となるなど、 生活環境の悪化に繋がる。結露対策としては、 ①換気を行うこと、②輻射による暖房 (床暖房など)を 取り入れること、③板ガラスを重ねた間に乾燥空気を封じ込めた複層ガラス等 を用いること、などが有効である。
四. 建築物と音
建築物において外部からの音を遮断したり、内部の音を外に漏れにくくしたりすることは、生活環境の整備として重要なことである。
1. 音に関する基本用語
① dB (デシベル)
音の大きさのこと。 日本建築学会推奨基準 (室内騒音評価) では、集合住宅の居室や寝室の標準的な騒音レベルを40dB 相当としている。
②周波数
1秒間の音の振動数のことで、Hz で表す。
③固体伝搬音
音の発生源から固体振動として伝搬され、 建築物の構造を伝わる振動によって室内に達する音のこと。
④空気搬音
空気中を伝わり、 壁や開口部を通じて伝わる音のこと。
⑤L値とD値
L値とは床衝撃音の遮音等級をいい、 数値が小さいほど遮音性能が高いこ とを意味する。 他方、 D値とは壁の遮音性能の規準をいい、 数値が大きいほ ど遮音性能が高いことを意味する。
2. 床の遮音
①床衝撃音の種類
床衝撃音には、 子供が飛び跳ねるなど、 比較的重くて硬い物体が床に落下 したときに下階に発生する音である 「重量床衝撃音」 と、 コップを落とすな ど、比較的軽くて硬い物体が床に落下したときに下階に発生する音である 「軽量床衝撃音」 とがある。
②床衝撃音の遮音
重量床衝撃音の大きさは、構造躯体の特性で決まり、柱や梁によって囲まれた床板の大きさや厚さ、 密度、剛性等がその要因となる。他方、軽量床衝撃音の大きさは、衝撃力の少ない表面材の処理、つまり、表面に柔軟な弾性材料を用いているかどうかにより決まる。
③ 床材と遮音性能
材質が同一であれば、材料の厚さが厚ければ厚いほど、材料の比重が大きければ大きいほど、遮音性能が高くなる。
3.界壁や開口部の遮音
① 壁と遮音性能
界壁の遮音性能は、主として壁の密度と厚さにより決まり、単位面積当た りの重さが重いほど遮音性能が高い。
② 透過損失
透過損失とは、入射音のエネルギーと透過音のエネルギーの比で表される もので、音がさえぎられる度合いのことをいう。この値が大きいということ は、 音が外に漏れにくいということを意味する。
③ 吸音材と遮音
吸音材とはグラスウールや発泡樹脂といった多孔質吸音材等、 音を吸収す る目的で使用される材料のことをいう。 吸音材を壁仕上げの下等に採用する と有効である。 一般に、 低周波音よりも高周波音の方が、 吸収率が高い。また、吸音材以外にも、 遮音型サッシや二重サッシ、 遮音型玄関ドア、消 音タイプの換気スリーブの採用等が有効である。
第4節 防水
1. 防水の種類
防水には、面状・膜状に防水層をしく「メンブレン防水」 と、 目地線状に 防水層をしく シーリング防水」とに大別される。メンブレン防水には、露出アスファルト防水、アスファルト防水コンクリー ト押え、 改質アスファルト防水、シート防水、塗膜防水といった種類がある。 また、シーリング防水は、ウレタン系 シリコーン系、ポリサルファイド系、 変成シリコーン系といった種類がある。
2. メンブレン防水
① 露出アスファルト防水
アスファルトルーフィングを2・3層、 溶融アスファルトで接着し、一体化したもの。
②アスファルト防水コンクリート押え
アスファルト防水の上に押えコンクリートを60~100mmの厚さで打設し たもの。 縦横に数m間隔で幅2cm 程度の伸縮目地を設け、 合成樹脂の目地 材を注入する。
③ 改質アスファルト防水
アスファルトにポリマーを添加したもの。 一般に、 厚さ2~3mmのルーフ ィングシート一層を、加熱又は接着剤で張り付ける防水。
④シート防水
合成ゴム又は塩ビにより製造された厚さ 1.2~2mm のシートを接着剤で 張り付けたもの
⑤ 塗膜防水
主としてウレタンゴム系の液状の防水材を塗り重ね、厚さ2mm程度の防 水層を形成し、表面にトップコートを塗ったもの。
3. シーリング防水
① ウレタン系シーリング材
そのままでは紫外線に弱く、 劣化が早いので、 外壁塗装と一緒に表面塗装 できる箇所に使用する。伸縮性は大きくないので、コンクリート目地やサッシ枠まわり、パイプ貫 通回り等に用いられる。 コンクリートのひび割れ補修のUカットシーリン グ材としても使用される。性能 価格的に最も標準的で、 多用される。
②ポリサルファイド系シーリング材
ウレタン系より耐候性 伸縮性に優れている。主に塗装をせず、 露出して仕上げる箇所に使われる。・タイルの伸縮目地や金属間の目地等に使用する。
③ 変成シリコーン系シーリング材.
・性能はポリサルファイド系と同程度。 ウレタン系よりは耐候性、 伸縮性等 の性能に優れている。表面に塗装されても、表面塗装の剥がれや変色等の問題がないので、 使用 箇所が制限されず、 汎用的シーリング材として用いられている。
④シリコーン系シーリング材
各種のシーリング防水の中でも、最も性能が高い。周辺の壁面等を汚染させる傾向があるので、 金属、 ガラス間など使用箇所が制限される。表面に塗装はできない。