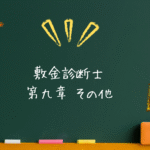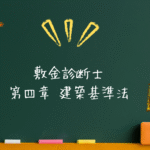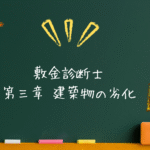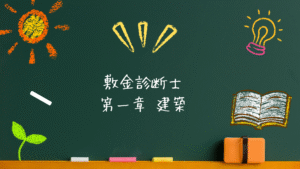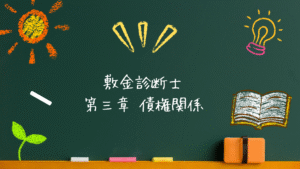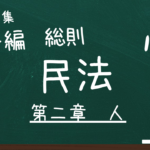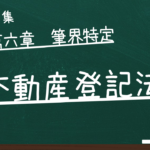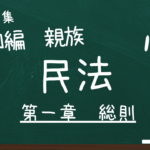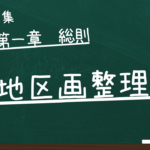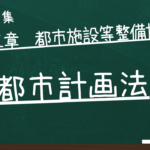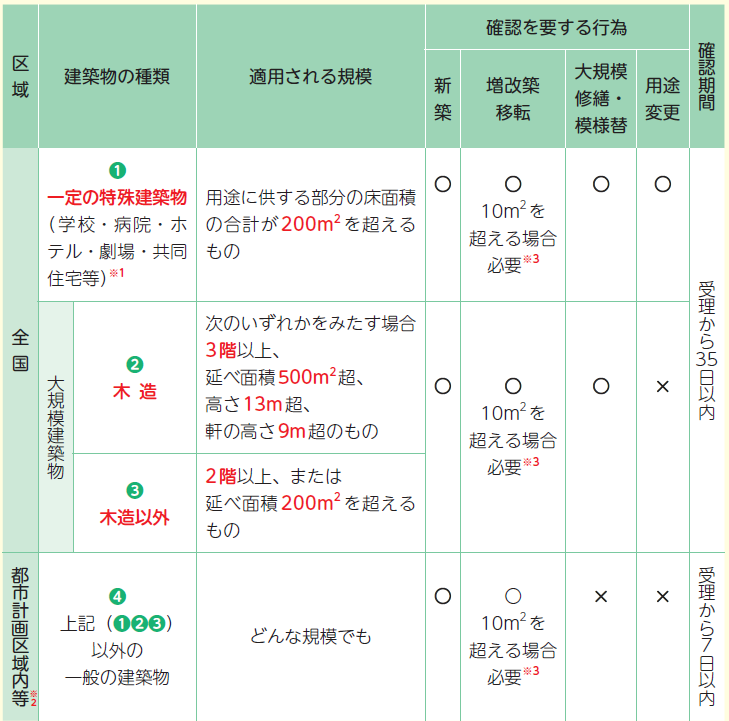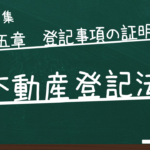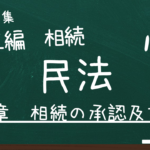第1節 民法 (共有)
共有
共有とは、一つの物を数人で所有することをいう。そして、一つの物を共有して いる場合に、それぞれの共有者が割合として持つ所有権のことを「持分」という。 共有者は、それぞれ目的物の「全体」 を 「共同して所有」することになる。共有者 は目的物の全体を使用することができるが、 排他的な使用はできない。なお、共有との比較として、「単独所有」という形態がある。これは、一人で一 つの物全体を所有していることであり、自己の所有物を、誰にも妨害されず(排他 的に) 自由に使用収益処分することができる。
1. 共有物の使用各共有者は、共有物の全体につき、 その持分に応じた使用をすることができる。
2. 持分の割合各共有者の持分は、 出資した額等に関わらず、 特約がなければ平等と推定される。
3. 共有物の管理等民法における共有物の管理は、以下のように決められる。
① 保存行為
保存行為とは、 共有物の現状を維持する行為をいう。 具体的には、共有物の 修繕依頼や不法占拠者への明渡請求、 盗まれた場合の取り戻し等である。この 保存行為は、各共有者が単独ですることができる。
②管理行為
管理行為とは、共有物を利用・改良する行為をいう。 具体的には、共有物の 第三者への貸与、共有物の賃貸借契約の解除、 共有物の利用者の決定等である。 この管理行為は、各共有者の持分価格の過半数の賛成ですることができる。
3 変更行為
変更行為とは、 共有物の形や性質に変更を加える行為をいう。 具体的には、 建物の建替え、増改築等である。 この変更行為は、共有者全員の同意ですることができる。
なお、変更行為と同じく扱われる行為として、処分行為がある。これは、共 有物を処分する行為であり、具体的には、共有物の第三者への売却等である。 この処分行為も、変更行為と同様、共有者全員の同意ですることができる。
④ 持分の処分持分の処分とは、共有物に対する各自の持分を処分する行為をいう。 具体的 には、持分を売却したり、 持分に抵当権を設定したりすることである。 この持 分の処分は、各共有者が単独ですることができる。
4. 共有物に関する負担
各共有者は、その持分に応じ、 管理の費用を支払い、 その他共有物に関する負担 を負う。これに関し、 共有者が1年以内にその支払義務を履行しないときは、他の 共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
5. 共有物についての債権
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継 人に対しても行使することができる。
6. 共有に関する債権の弁済
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、 分割に際 し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、 その弁済にあてることができる。 また、その債権について弁済を受けるために債務者に帰属すべき共有物の部分を 売却する必要があるときは、 債権者である共有者は、その売却を請求することができる。
7. 共有物の分割
各共有者は、原則として、いつでも自由に共有物の分割を請求することができる。 もっとも、共有者は、期間を5年以内とする共有物の分割を禁止する特約をするこ とができる。 なお、 この特約は更新することができる。
8. 共有者の死亡等
共有者の1人が、相続人なくして死亡して特別縁故者に対する財産分与もなされ ない場合や、 持分を放棄した場合には、その持分は他の共有者に属する。
第2節 区分所有法
一. 区分所有権
区分所有権とは、一棟の建物の中で構造上区分された数個の部分として独立して 住居・店舗・事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものを 目的とする所有権をいう。
1. 区分所有権の成立
一棟の建物に区分所有権の目的とすることのできる複数の建物部分がある場合 でも、それだけでは当然には区分所有関係は生じない。 当該建物の部分を区分所有 権の目的物とするか否かは、ひとえに所有者の意思にゆだねられている。 それゆえ、 区分所有権が成立するためには、構造上 利用上独立した数個の部分を有する一棟 の建物が存在すること、及び、 当事者の建物を区分して所有するという意思の双方 の条件を満たすことが必要である。
2. 区分所有関係の終了
区分所有関係が終了する場合としては、取壊しをした場合、 隔壁を除去した場合、 合併の登記がなされた場合などが考えられる。
二. 専有部分
専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
1. 専有部分となるための要件
建物の部分が専有部分となるためには、 ① 構造上の独立性と②利用上の独立性の 2つの条件が満たされている必要がある。
① 構造上の独立性
一棟の建物のうち、 構造上区分された部分であること。 つまり、建物の構成 部分である仕切り壁、床、天井等によって他の部分と遮断されていること。
② 利用上の独立性
独立して住居、 店舗、事務所又は倉庫、 その他建物としての用途に供するこ とができるものであること。 また、独立した出入り口があり、かつ、その出入 り口を通じて直接に外部に出入りできること
2. 専有部分の用途
専有部分の用法や用途は、区分所有者の共同利益に反しない限り、その専有部分 を所有する区分所有者の自由である。もっとも、専有部分を居住用としてのみ利用 することにするなど、 その用法や用途について、 規約で制限をすることができる。
三. 共用部分
共用部分とは、 専有部分以外の建物の部分、 専有部分に属しない建物の附属物及 び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。
1. 共用部分の種類
共用部分は、 法定共用部分と規約共用部分とに分類される。 さらに、共有の態様 に着目して、 全体共用部分と一部共用部分とに分類することもできる。
① 法定共用部分 規約共用部分法定共用部分とは、 「法律上当然に共用部分とされる、 専有部分以外の建物 の部分」 及び 「法律上当然に共用部分とされる、 専有部分に属しない建物の附 属物」 をいう。 また、 規約共用部分とは、 「規約により共用部分とされた、 専 有部分の適格性を備えた建物の部分」 及び 「規約により共用部分とされた、 附 「属の建物」 をいう。
②全体共用部分,一部共用部分
全体共用部分とは、区分所有者の全員の共用に供されるべき共用部分をいう。 これに対し、一部共用部分とは、 一部の区分所有者の共用に供されるべき部分をいう。
2. 共用部分と登記
不動産登記法上、 法定共用部分については、 その旨の表示の登記をすることがで きない。 しかし、 専有部分を規約共用部分とした場合については、 外観上構造上の 独立性及び利用上の独立性が認められるため、取引の安全を図る必要性から、 規約 共用部分たる旨の登記 (表示の登記) をしない限り、 第三者には対抗することがで きないとされている。
3. 共用部分の所有関係
全体共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、 規約により、 部の区分所有者又は管理者を所有者とすることができる (いわゆる 「管理所有」 )。
同様に、一部共用部分は、原則としてこれを共用すべき一部の区分所有者の共有に属するが、 規約により、 区分所有者全員又は一部の区分所有者又は管理者を所有者とすることができる (いわゆる「管理所有」)。
4. 管理所有の制度
原則として、共用部分等の管理を行うのは区分所有者全員である。しかし、特に 区分所有者の数が多い場合には、区分所有者全員による管理というのは現実的に困 難であり、むしろ、一定の権限を特定の者に与えて管理をする方が合理的である。 そこで、区分所有法は、一部の区分所有者又は管理者を共用部分の所有者とし、そ の管理を行わせることを可能とする制度を設けている。 これを管理所有制度といい この場合の共用部分の所有者のことを管理所有者という。管理所有は、あくまで共用部分の管理の便宜の観点から定められた制度であり、 管理所有者に共用部分の独占的使用を認めるものではない。 そこで、管理所有者は、 共用部分に関し、保存行為、管理行為、軽微変更行為までは単独ですることが可能 であるが、 重大変更にあたる共用部分の変更は、管理所有者が単独ですることがで きず、集会の決議によらなければこれをすることができないこととされている。
5. 共用部分の持分の割合
① 持分割合の算定基準
原則として、 共用部分に対する各共有者の持分は、その有する専有部分の床 面積の割合による。 ただし、 規約に別段の定めがある場合には、 それによる。
②一部共用部分の床面積の按分加算
原則として、一部共用部分で、床面積を有するものがあるときは、その一部 共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割 合により分配して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に入算する。 ただし、 規約に別段の定めがある場合には、それによる。
③ 専有部分の床面積の算定方法原則として、 専有部分の床面積は、 壁その他の区画の内側線で囲まれた部分 の水平投影面積による (内のり計算)。 ただし、 規約に別段の定めがある場合 には、それによる。
6. 共用部分の使用
各共有者(区分所有者) は、 共用部分をその用方に従って使用することができる。具体的には、法定共用部分の用方は、 共用部分の構造・位置等から必然的に定まり、 規約共用部分の用方は、 規約の内容によって定まる。
7. 共用部分の管理
共用部分の管理は、以下の手続きによっておこなう。 なお、共用部分の管理行為 及び変更行為(軽微変更重大変更) が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき ときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
① 保存行為
保存行為とは、物の滅失・損傷を防止し、 その現状を維持するための行為を いう。 共用部分の保存行為は、各共有者が単独ですることができる。
②管理行為
管理行為とは、保存行為・変更行為以外の管理に関する行為をいう。 共用部 分の管理に関する事項は、原則として、区分所有者及び議決権の各過半数の集 会の決議 (普通決議) で決する。
③変更行為
共用部分の変更のうち、形状又は効用の著しい変更を伴わないものを軽微変 更という。 軽微変更は、 集会の普通決議で行うことができる。他方、 形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除いたものを重大変更と いう。 重大変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会 の決議で決する。 ただし、この区分所有者の定数は、 規約でその過半数まで減 ずることができる。
8. 専有部分と共用部分の持分の分離処分禁止の原則
① 共用部分の持分の従属性
共用部分の持分は、 専有部分の処分に従う。 民法177 条の 「不動産の物権変 動は登記しなければ第三者には対抗できない」 とする規定は、 共用部分には適 用されない。
② 専有部分と共用部分の持分に関する単独処分禁止
共有者は、区分所有法に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部 分と分離して持分を処分することができない。 ここでいう「処分」には、譲渡 のほか、担保権の設定も含まれる。 また、 共用部分の共有者が自ら処分する場 合のみならず、 区分所有者の債権者が共有持分のみを差し押さえたり、競売し たりすることも禁止される。
例外として、共用部分の持分を専有部分から分離して単独で処分することが できる「区分所有法に別段の定めがある場合」とは、具体的には、 ①規約によ って一部の区分所有者又は管理者を共用部分の所有者とする場合 (管理所有) と、②規約の設定又は変更によって共有持分の割合を変更する場合である。
四. 敷地
建物の敷地とは、建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により建物の敷地 とされた土地をいう。 そして、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利 を敷地利用権という。
1. 敷地の種類
① 法定敷地
建物が所在する土地のこと。 法律によって当然に建物の敷地とされているの で法定敷地という。 区分所有者等が法定敷地としようとする意思があるか否か とは関係がない。
②規約敷地
建物が所在する土地以外の土地であって、 建物及び建物が所在する土地と一 体として管理又は使用する庭 通路その他の土地について、 規約により建物の 敷地とされたもののこと。
③みなし規約敷地
建物が所在する土地 (法定敷地) が、 建物の一部の滅失、又は、 分割(分筆) により、 法定敷地でなくなった場合に、 法律の規定によって、 規約敷地とみな されるものをいう。
2. 敷地利用権
敷地利用権とは、 区分所有者が専有部分を所有するために敷地について有する権 利(土地所有権 地上権・土地賃借権 土地使用借権) をいう。
3. 敷地利用権の割合
敷地利用権に対する複数の区分所有者相互間の持分割合については、区分所有法 上、 直接の定めはない。 この点、 学説上は、 民法上の共有に関する規定に従い共有 者間で別段の定めがない限り相等しいものと推定されると解されている。これに対し、 敷地利用権を数人で共有している場合において、 複数の専有部分を所有する区分所有者が存するとき、その区分所有者は各専有部分に対応する複数の 持分権を有するのではなく、あくまでその有する専有部分全体に対応する1つの特 分権を有するに過ぎない。そして、この場合の当該区分所有者の各専有部分に係る 敷地利用権の割合は、規約による別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合、 すなわち専有部分の床面積の割合によるものとしている。
4. 敷地権
敷地権とは、敷地利用権のうち登記された権利で専有部分と一体化されたものを いう。 なお、敷地利用権のうち使用借権は、 不動産登記法上登記ができないので、 敷地権とはなりえない。
5. 専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、 区分所有者は、 その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること ができない。 ただし、 規約に別段の定めがあるときは、この限りでなく、 専有部分 と敷地利用権の分離処分が認められる。専有部分と敷地利用権を分離して処分することが禁止されている場合に、当該禁 止に違反して専有部分又は敷地利用権のみを処分したとしても、その処分は無効と なるのが原則である。 しかし、かかる無効は、 分離処分の禁止について善意の第三 者には対抗することはできない。もっとも、 分離して処分することができない専有 部分及び敷地利用権であることを登記 (敷地権たる旨の登記) していた場合は、 か かる無効を善意の第三者にも対抗することができる。
6. 区分所有権売渡請求権
日本の私法上、 土地と建物とは別々の不動産である。 従って、 区分所有者が敷地 利用権を有しない場合、 土地所有者は当該区分所有者に対して専有部分の収去を請 求することができるのが原則である。 しかし、区分所有建物の一部の専有部分につ いて収去請求をすることは現実問題として困難といえる。 そこで区分所有法は、敷 地利用権を有しない区分所有者があるときは、 その専有部分の収去を請求する権利 を有する者が、当該区分所有者に対し、 区分所有権を時価で売り渡すべきことを請 求することができるとした。 これを区分所有権売渡請求権という。