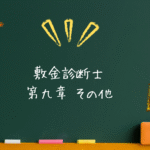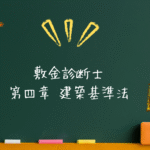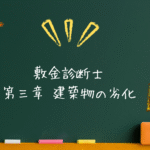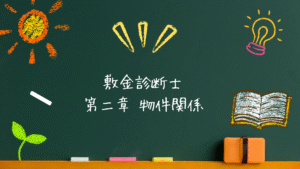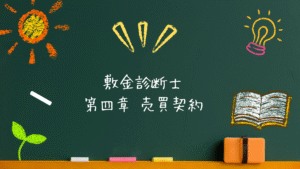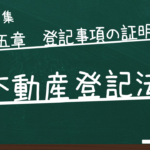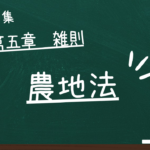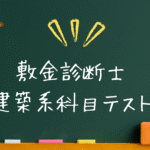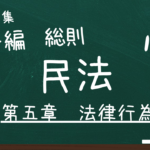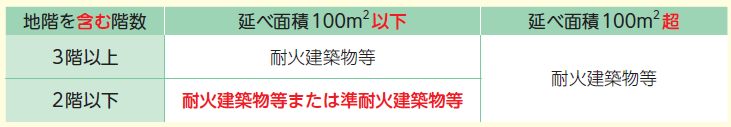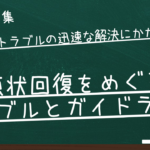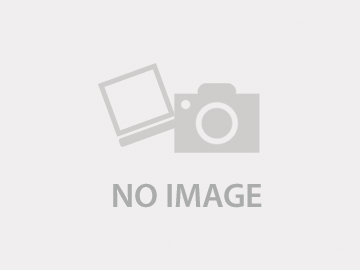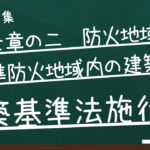Contents
第1節 民法(債務不履行)
一. 意義
債務不履行とは、債務者が債務の本旨(契約の内容) に従った履行をしないことをいう。なお、自ら雇用している職員や従業員に故意又は過失があった場合も、債務者に 故意又は過失があったと扱われる (履行補助者の故意過失)。 また、金銭債務に おいては、不可抗力による場合でも債務不履行となる。
二. 債務不履行の類型
債務不履行には、次の3つの類型がある。
① 履行遅滞
履行が可能であるのにもかかわらず、 履行期に履行の提供がな されないことをいう。
② 履行不能
契約その他の債務の発生原因 取引上の社会通念に照らして、 債務の履行ができなくなることをいう。※契約後に不能になった場合のみならず、 契約時に既に不能 であったものも含まれる。
③不完全履行
債務の履行はなされたものの、その内容が債務の本旨に従わな い不完全なものである場合をいう。
三.損害賠償請求権
債務者が義務を履行しなかったことにより、 債権者に損害を生じた場合に、その 損害をてん補して損害がなかったのと同じ状態に戻す義務を負う。 これを損害賠償 という。 履行遅滞の場合には、 履行が遅れたことで生じた損害の賠償を、履行不能 の場合には、 本来の目的物に代わる損害の賠償を請求できる。
1. 損害賠償の範囲
損害賠償は、原則として、 金銭でその額を定める。 そして、 債務不履行に対する 損害賠償の請求は、 これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的 とする。もっとも、特別の事情によって生じた損害でも、 当事者がその事情を予見 すべきであったときは、債権者は、その損害の賠償を請求できる。
2. 損害賠償額の予定
損害賠償額の予定とは、一定の債務不履行があった場合に、債務者が債権者に対 して一定の金額を支払うことを、あらかじめ約束しておくことをいう。 債権者が自 己の損害や損害額を立証しなければならないという困難、面倒を回避するための制 度である。
四. 解除
解除とは、いったん有効に成立した契約を、 契約の一方当事者の意思表示によっ て、 その契約がはじめからなかったのと同様の状態にする制度をいう。
1. 催告による解除
当事者の一方が債務を履行しない場合 (=履行遅滞)、 相手方が相当の期間を定 めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、 契約の解除をす ることができる。
※契約を解除するにあたり、 債務者の帰責事由は不要。
※催告の期間を経過した時における債務の不履行がその契約取引上の社会通 念に照らして軽微であるときは、 契約の解除はできない。
2. 催告によらない解除
次の場合には、債権者は、 催告をすることなく、直ちに契約の解除ができる。
① 債務全部が履行不能であるとき
②債務者が債務全部の履行拒絶の意思を明確に表示したとき
③債務の一部が履行不能である場合、 または債務者がその債務の一部の履行拒 絶の意思を明確に表示した場合に、 残存する部分のみでは契約目的の達成が不 可能なとき
④ 定期行為において、 債務者の履行がない場合
⑤ ①~④のほか、債務者がその債務の履行をせず、 債権者が催告をしても契約 目的達成に足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
3. 解除の効果
① 原状回復義務
解除権が行使されると、 当事者は、原状回復義務を負う。 原状回復義務とは、契 約締結以前の法律上の状態に復帰させる義務のことをいう。 金銭を返還する場合に は、その受領の時からの利息を付けることが必要となる。
② 第三者の保護
a) 解除前の第三者との関係
この場合、第三者が登記をしている場合には、売主は建物の所有権を第三者に対抗できない。
b) 解除後の第三者との関係
この場合、売主と第三者の優劣は登記の先後で決める (対抗問題)ので、 先に登記を備えたほうが勝つとされている。
第2節 民法 (契約総則)
一. 契約の成立
契約は、原則として、申込とそれに対する承諾とで成立する (諾成契約)。 もっとも、申込とそれに対する承諾に加え、物の引渡しが契約成立の条件となるような 契約もある (要物契約)。
二. 契約の効力発生要件
契約が有効に成立するためには、以下の要件を充たす必要がある。
① 契約の内容が可能であること
②契約の内容が確定できるものであること
③契約の内容が適法であって社会的妥当性のあるものであること
三. 契約成立後の関係
契約成立により、 契約当事者に債権債務が発生する。 債権を有する者を債権者と いい、 債務を有する者を債務者という。 この債権債務関係は、 給付との関係により 相対的に決せられる。なお、契約当事者双方が互いに債権債務を有する場合 (双務契約) 両債務の対 価的依存関係に基づき、 両当事者は、 相手方が履行をするまでは、 自分の債務を履 行しないと主張することができる (同時履行の抗弁権)。
四. 契約の種類と性質
契約は、「有償契約か無償契約か」 「双務契約か片務契約か」 「諾成契約か要物契 「約か」という3つの視点から分類ができる。有償契約か無償契約かは、対価的関係のある出捐があるか否かにより区別される。 また、双務契約か片務契約かは、対価的債務が生ずるか否かにより区別される。 そ して、諾成契約か要物契約かは、契約の成立に物の引渡しを必要とするか否かによ り区別される。民法では、典型契約と呼ばれる13種類の契約が規定されている。 主な契約類型 とその性質は下記のとおりである。
<民法上の主な契約類型>
| 契約類型 | 有償・無償 | 双務・片務 | 諾成・要物 |
| 贈与 | 無償 | 片務 | 諾成 |
| 売買 | 有償 | 双務 | 諾成 |
| 交換 | 有償 | 双務 | 諾成 |
| 消費貸借 | 無償 (特約で有償) | 片務 | 要物 (諾成もあり) |
| 賃貸借 | 無償 | 片務 | 諾成 |
| 雇用 | 有償 | 双務 | 諾成 |
| 請負 | 有償 | 双務 | 諾成 |
| 委任 | 有償 | 双務 | 諾成 |
| 寄託 | 無償 (特約で有償) | 片務 (双務もあり) | 諾成 |
| 無償 (特約で有償) | 片務 (双務もあり) | 諾成 |
※委任・寄託は、 報酬の支払いをすれば、有償 双務契約となる。
※消費貸借は、利息の支払いをすれば有償契約となる (片務であることは変わらない)。 また、書面でする消費貸借の場合には、 諾成契約となる。