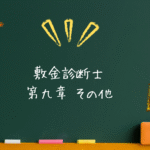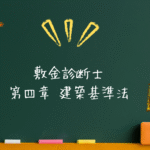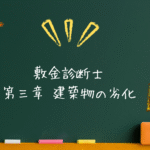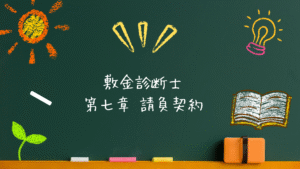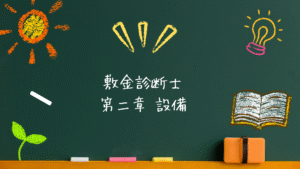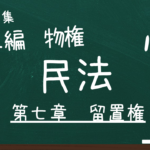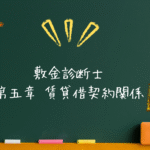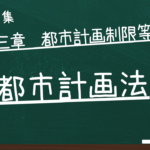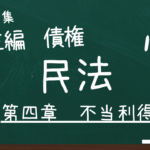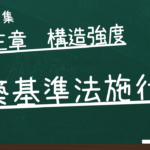Contents
第1節 民事訴訟
一. 民事訴訟総論
1. 民事訴訟とは
私人間の生活関係に関する紛争を、 裁判所 (国の司法機関)によって強制的に解 決するための手続きをいい、 その訴訟手続を定めているものが民事訴訟法である。 民事訴訟制度は、自力救済の禁止に伴って発生したものである。債務者が給付義務を履行しない場合に、 公権力によってその履行を強制させる手 続を強制執行という。 強制執行をするための前提として、債務名義を得る必要があ る。この債務名義とは、 強制執行によって実現される権利の存在を公的機関が証明し た文書のことをいう。 債務名義には、 確定判決、 仮執行宣言付判決、 和解調書、調 停調書、 執行証書 (執行認諾文言付公正証書)、 仮執行宣言付支払督促がある。
2. 三審制度
日本の裁判では、 第一審 (原審) 、 第二審 (控訴審)、 第三審 (上告審) とす る三審制度が採られている。 第一審の判決に不服があり、 さらに裁判を求めること を控訴といい、 第二審の判決にも不服があり、さらに裁判を求めることを上告とい う。
3. 管轄
① 事物管轄
事物管轄とは、訴訟事件の性質内容の違いに基づいて定められる管轄をいう。 民事訴訟事件では、訴訟の目的の価額 (訴額) が140万円を超えない事件は 簡易裁判所に、それ以外の事件は地方裁判所に管轄権がある。
②土地管轄
同種の裁判所間で、ある事件をどの土地の裁判所又は簡易裁判所が管轄するかの定めをいう。
a. 人(自然人)の普通裁判籍
住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所 により、 日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
b. 法人 その他の普通裁判籍
その主たる事務所又は営業所により、事務所・営業所がないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
③合意管轄
合意管轄とは、当事者の合意によって生じる管轄をいう。 当事者の利益を考 慮して設けられているものである。なお、合意の態様として、付加的 (競合的) 合意と専属的合意がある。
a. 付加的 (競合的) 合意
法定管轄の裁判所以外の裁判所を付加して管轄を認める合意である。
b. 専属的合意
特定の裁判所だけに管轄を認め、 その他の裁判所の管轄を排除する合意である。
④管轄の標準時
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
4. 当事者
① 当事者能力
原告 (訴訟で訴える者) または被告 (訴えられる者)として判決の名宛人と なる者を当事者といい、民事訴訟の当事者となることのできる一般的能力を当 事者能力という。原則として、 私法上の権利能力者に対応し、自然人及び法人 は当事者能力を持つ。 また、法人格のない社団・財団 (権利能力なき社団・財 団)でも、代表者又は管理人の定めのあるものについては、当事者能力を認め られる。
<権利能力なき社団の要件 (最判昭和 39.10.15) >
団体としての組織を備えること。
多数決の原則が行われていること。
構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続すること。
組織において代表の方法、 総会の運営、財産の管理その他の団体としての主要な点が確定していること。
②当事者適格
裁判で争われる一定の権利関係について、 当事者として訴訟を追行・実施で きる資格を当事者適格という。 訴訟においては、誰を当事者として判決を下せ ば紛争を実効的に解決できるか、ということを考える必要があり、個々の紛争 の対象となっている権利義務の帰属主体に、原則として、当事者適格が認めら れる。この点が、 個々の事件を離れて一般的に決められる当事者能力と異なる。
③訴訟能力
訴訟能力とは、訴訟当事者として自ら単独で有効に訴訟行為をし、又は訴訟 を有効に受けられる能力をいう。 一般における取引と同様、訴訟においても、 単独で、 完全な法律行為をすることができないものを保護する必要がある。 そ ここで、訴訟能力を有しない者は法定代理人によらなければ、訴訟行為をするこ とができないとした。民事訴訟法上は、原則として民法上の行為能力に対応して訴訟能力をとらえ る趣旨と解されている。 すなわち、 民法上の行為能力者は、訴訟能力を有する ことになる。
5. 公示送達
当事者の居住所等で送達すべき場所が分からない場合には、 公示送達という制度 を利用して、訴えを提起することができる。公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべ き者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してなされるものである。 原則として、 この掲示から2週間を経過することで効力を生じるが、 公示送達を債務者が見るこ とはほとんどないため、少額訴訟、支払督促を利用する場合は、公示送達によることはできない。
6. 本人訴訟主義と弁護士代理の原則
① 本人訴訟主義
弁我が国においては、当事者が自ら訴訟行為をなすことが認められており、 護士を訴訟代理人に選任するか否かは、当事者の自由とされている。これを本 人訴訟主義という。 なお、これに対して、 弁護士を訴訟代理人とすることを強制する制度を弁護士強制主義という。
② 弁護士代理の原則
当事者が訴訟代理人を選任する場合には、他の法令に基づく場合を除き、弁 護士を選任しなければならない。 この原則を、弁護士代理の原則という。但し、 簡易裁判所においては、係争利益が小さく、 弁護士代理の原則を貫くと費用倒 れになる場合があるので、裁判所の許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人にすることができる。
二. 少額訴訟
少額訴訟とは、一般市民間の少額で複雑でない金銭トラブルを簡易、 迅速、低廉、 公平な裁判手続によって解決を図ることを目的として制定された、 特別な訴訟手続 である。
1. 通常訴訟との違い
少額訴訟の対象となる事件は、 訴額 60 万円以下の金銭支払請求に限られる。 そ して、一般市民が利用しやすいよう手続きが簡略化されていて、原則として1回の 審理で、即日に判決を言渡す (一期日審理の原則)。 ただし、少額訴訟の利用は、 同一の簡易裁判所で年10回に限られる。 クレジット会社の債権取り立てに独占さ れるのを防ぎ、一般市民が利用しやすくするためである。 なお、 控訴はできない。
2. 通常の手続きへの移行
訴訟の目的の価額 (訴額) 60万円以下の金銭の支払請求を目的とする訴えに ついては、通常訴訟によることも少額訴訟によることもできる。 そのため、少額訴 訟による審理及び裁判を求める場合には、その旨の申述を訴えの提起の際にしなけ ればならない。このように、原告に選択権が与えられていることに対応して、公平の観点から、 被告の申述により、 通常の訴訟に移行することができる。
3. 判決による支払の猶予
裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、 判決言渡しの日から3年を超えない範囲内で、金銭の支払につき、支払猶予、分 割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払免除等を命じることができる。
4. 不服の申立て
少額訴訟の判決に対しては、 控訴が禁止されているので、判決に不満があれば、 異議申立てをすることになる。 少額訴訟おける異議申立てとは、その少額訴訟判決 を言い渡された簡易裁判所において、もう一度審理することを求めることをいう。 少額訴訟判決に対する異議の申立ては、 当事者が判決書等の送達を受けた日から 2週間の不変期間内において、 その判決をした裁判所に申し立てることができる。
5. 反訴の禁止
少額訴訟では、 簡易、 迅速な裁判が求められるため、 反訴を提起できない。 反訴 とは、民事訴訟の被告から原告に対して提起する訴えのことをいう。
三. 支払督促
支払督促とは、 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量を目的とする請求 権について、 簡易、 迅速に債務名義を与えることを目的とした手続きである。
1. 支払督促の申立て
送達原則として、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に対してする。 債権者の申立てに要件が備わっていれば、 簡易裁判所の書記官は、 債務者を審尋 しないで支払督促を発する。 支払督促の効力は、 債務者に送達された時に生じる。
2. 債務者の異議の申立て
債務者は、支払督促を発した簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。 債務者からの督促異議の申立てが適法であれば、支払督促はその督促異議の限度 で効力を失う。そして、通常訴訟による訴えの提起があったものとみなされ、通常訴訟に移行する。
3. 仮執行宣言の申立て
仮執行宣言付支払督促の送達債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしな いときは、簡易裁判所の書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言 を付さなければならない。ただし、仮執行宣言の申立てをすることができる時から 30日を経過すると、 支払督促はその効力を失う。仮執行の宣言により直ちに執行力が生じ、 債権者は債務者の財産を差し押さえ、 競売の申立てをすることができる。
4. 仮執行宣言後の異議の申立て
債務者は、 仮執行宣言付支払督促に対して、 簡易裁判所に督促異議の申立てをす ることができる。 しかし、ここで督促異議の申立てをしても、 仮執行宣言付支払督 促は効力を失われない。また、適法な督促異議の申立てがあったときは、 督促異議に係る請求については、 その目的の価額に従い、 支払督促の申立ての時に、 支払督促を発した裁判所書記官 の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があっ たものとみなされ、当該請求は通常の訴訟に移行することになる。
5. 支払督促の効力
仮執行宣言付の支払督促の送達を受けた日から、2週間以内に債務者の督促異議 の申立てがないときは、支払督促は、確定判決と同一の効果が生じる。
第2節 ADR (裁判外紛争処理)
一. ADR制度
ADRは、Alternative Dispute Resolution の略称であり、一般に裁判外紛争解 決制度と和訳される。これは、身の回りの紛争について、裁判以外の手続きによっ て解決を図る制度である。 また、このADRによる紛争解決のための活動を行って いる機関を一般にADR機関と呼ぶ。現在の裁判制度は、解決までに時間がかかる、 費用が高い、 手続の進め方が難し 経過や結果が公開されてしまう等の問題から、一般人にとって敷居が高いと指 摘されている。 そこで、 簡易かつ柔軟に紛争解決を図ることができる制度として ADRの機能が注目されている。
1. ADRのメリット
① 簡単な申立て手続
ADR機関によって申立ての手続は異なるが、 申立書の書式が簡易であり、 電話による受付をしている機関もある。
② 柔軟性
当事者の意向に応じて、柔軟に手続きを進めることができる。 また、 当事者 の意向に応じて、 柔軟な解決を図ることができる。
③迅速性
当事者の合意に従い、迅速かつ低廉に手続きを進めることができる。
④専門性
専門的な知識を持った第三者が関与することで、 専門的知見の必要となる紛争においても適切な判断を求めることができる。
⑤ 非公開性
解決までの過程は非公開で行われ、結論も原則として公開されないため、関係者以外に知られたくない情報についても取り扱うことができる。
2. 主なADRの種類
① 和解(あっせん)
第三者(あっせん人) が当事者の間に入り、双方の話し合いが円滑に進むよ う助言し、当事者同士の交渉による和解の成立を促す。和解には、裁判外の和解と裁判上の和解があり、 裁判上の和解はさらに、訴 え提起前の和解と訴訟上の和解とに分かれる。
a. 裁判外の和解
裁判外の和解は、争いの当事者間で、 当事者が互いに譲歩して争いをや めることを約することによって成立する民法上の契約である。 当事者間の 和解契約の成立により、 法律関係が確定され、 当事者は和解の内容に拘束 されることとなる。
b. 裁判上の和解
訴え提起前に、 簡易裁判所の裁判官の面前でなされる和解手続を、訴え 提起前の和解という。 この和解手続は、 訴額にかかわらず、 相手方の普通 裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所になされるのが一般的である。また、当事者双方が、訴訟の係属中に、訴訟物である権利等について、 その主張を譲歩して訴訟を終了させる裁判所又は裁判官の面前における 合意を訴訟上の和解という。 訴訟上の和解が記載された調書は、確定判決 と同一の効力を有する。
② 調停
第三者(調停人) の仲介によって解決案 (調停案) が提示され、これに当事 者が同意することで解決となる。 調停案に強制力はなく、 当事者は、 調停案が 気に入らない場合にはこれを拒否することもできる。典型的には、裁判所において行われる民事調停 (簡易裁判所) や、 家事調停 (家庭裁判所)がある。
③仲裁
当事者間の合意 (仲裁合意) に従って、 第三者(仲裁人)が紛争について判 断(仲裁)を行い、 当事者がその仲裁判断に従うことで紛争を解決する。 仲裁 判断には強制力が認められ、 当事者はこれを拒否することはできない。仲裁人は、当事者の合意によって選定されるが、 裁判官と同様の中立性が要求される。
<一般的なADRと裁判との相違>
| ADR | 裁判 | |||
| 和解 | 調停 | 仲裁 | ||
| 手続きの公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 公開 |
| 手続き利用への 当事者の同意 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 三者による解決案の提示 | 提示なし | 提示 | 提示 | 提示 |
| 当事者の解決案 の拒否 | できる | できない | できない | |
| 解決案の強制 | できない | できる | できる |
3、ADRの分類
① 手続の種類による分類
a 助言型
当事者間の自主的な解決を促すために第三者が助言を行うもの(例:相談)。
b、調整型
当事者間の合意により紛争の解決を図ろうとするもの(例:調停、あっせん)
c.裁断型
あらかじめ第三者の審理 判断に従うという一般的な合意の下に手続を開始するもの( 例: 仲裁)
②提供主体による分類
a. 司法型
裁判所内で行われるもの(例: 民事調停、家事調停)
b. 行政型
独立の行政委員会や行政機関などが行うもの(例:消費生活センター、 公害等調整委員会、建設工事紛争審査会)
c. 民間型
弁護士会、消費者団体、業界団体などが運営するもの(例: 弁護士会仲裁センター、各種PLセンター)
二. ADR 法
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」 (ADR法)は、裁判外紛争 解決手続についての基本理念、 国・地方公共団体の負う責務、民間事業者の行う和 解の仲介などについて定めた法律である。この法律は、裁判外紛争解決手続の機能を充実させることによって、 紛争の当事 者がその解決をはかるのにふさわしい手続を選択することを容易にし、国民の権利 利益の適切な実現に資することを目的とする。民間事業者の行う和解の仲介の業務に関し、 その適正さを確保するため、一定の 要件に適合していることを法務大臣が認証する制度を設け、 認証を受けた民間事業 者の和解の仲介業務には、 時効の中断 訴訟手続の中止といった法的効果が与えら れる。なお、 仲裁については仲裁法により時効の中断などの法的効果が与えられている ため、 仲裁業務はADR法による認証の対象とはならない。