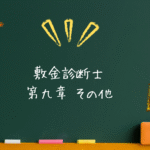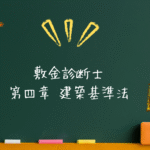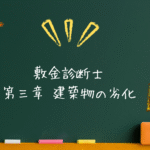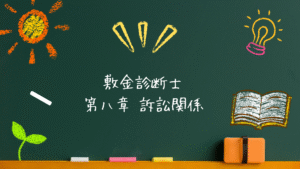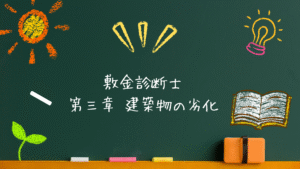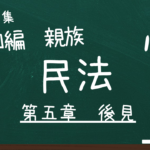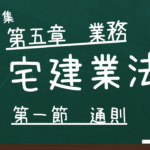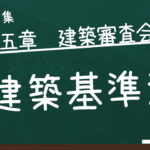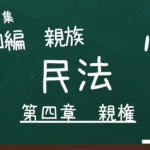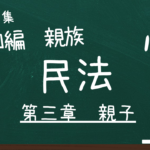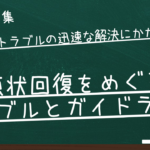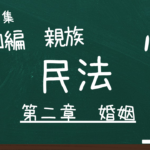第1節 給水給湯設備
一. 給水方式
1. 給水方式の種類
給水方式は、配水管から蛇口までパイプが切れ目なくつながっている 「直結 式給水」と、水をいったん受水槽に溜めてから給水する「受水槽式給水」に大 別される。
2. 直結式給水
直結式給水には、水道本管から給水管を直接分岐して建築物内に引き込み、 各住戸に直接給水する 「水道直結方式」 がある。 また、水道本管から分岐して 引き込んだ水を、 増圧給水ポンプを経て直接各住戸に給水する「増圧直結給水 方式」 がある。
3. 受水槽式給水
受水槽式給水には、水道本管から分岐して引き込んだ水を受水槽へ一時的に 貯水し、その後、 揚水ポンプで屋上に設置されている高置水槽へ揚水して、 重 力により各階の住戸に給水する 「高置水槽方式」がある。他にも、水道本管から分岐して引き込んだ水を受水槽へ一時的に貯水し、そ この後加圧給水ポンプで圧力タンクに給水して、圧力タンク内の空気を圧縮加圧 させて各階の住戸に給水する 「圧力タンク方式」 や、 水道本管から分岐して引 き込んだ水を受水槽へ一時的に貯水し、その後加圧給水ポンプで直接加圧して 各住戸に給水する 「タンクレスブースター方式 (ポンプ直送方式)」 などがあ る。
二. 給水弁
給水配管の途中に設ける水量調節をするための弁のこと。 弁体が流体の通路を 垂直に仕切ることで開閉する 「仕切弁」 や、 球状の弁箱を持ち、 流体の流れがS 字状となる「玉形弁」、 さらには弁体が流体の背圧によって逆流を防止するよう 作動する 「逆止め弁」 などがある。 また、 水槽に給水し、 浮子の浮力によって自 動的に給水を行ったり、 停止したりする「ボールタップ」 などもある。
三. さや管ヘッダー方式
1. さや管ヘッダー方式とは
さや管ヘッダー方式とは、住戸内又は配管シャフト内に給水・給湯ヘッダー (分配管)を取り付け、ヘッダー付近から住戸内の床下等にさや管(蛇腹状の 波付管。ポリエチレンが主原料)を敷設配管して、 さや管の中にたわみ性のあ あるポリエチレン管やポリブデン管を挿入するものをいう。
2. さや管ヘッダー方式の特徴
さや管ヘッダー方式は、一般に先にさや管を施工し、後から給水給湯管を 挿入するため、 床工事による配管の損傷を防ぐことができ、 また、 漏水の際の 対応が容易であることから、 近年多く採用されている。ヘッダーと給水・給湯栓が一対一の形で接続するため、 他の給水・給湯栓が 同時に使用されても吐出量の変動が少なく、 また、 給湯管が細いため、 給湯栓 を開いてから適温の湯が出るまでの湯待ち時間が短い。
四. 給水に関する問題
1. 赤水問題
鋼製の貯水槽や鋼管において、 設備内の水中の溶存酸素で赤錆が発生し、 水 道水が赤褐色になることがある。 これを赤水現象という。赤水には、休日は使用しないビルなどにおいて、休日明けの使用開始時のみ 赤水が出る状態や、常時使用しない給水栓を開いたときに赤水が出る状態であ る「軽度の赤水」や、毎朝、最初のうちは赤水が出てくるが、使用するうちに 出なくなる状態である 「中度の赤水」、さらには、常に淡い赤水が出てきて、 給水栓を全開にすると錆の微粒子が出てくる状態である 「高度の赤水」がある。 赤水の発生原因として考えられるのは 給水管の経年変化による腐食(老朽 化) 給水設備の管理の不十分さ (清掃が十分になされていない)などである。 かかる赤水問題が発生した場合の対処方法としては、応急対策の他、エポキ シ樹脂ライニング工法などの 「ライニング更生工事 (更生工法)」 既存の配管 をそのまま残し、別経路の新規配管工事を施工したり、既存の配管を取り替えたりする 「新規配管工事 (更新工法)」 などがある。
2. ウォーターハンマー現象
給水配管内のバルブを急に閉じた場合に、 給水管内の水圧が異常に上昇・低 下して圧力波が生じ、管壁にぶつかって水音を生じさせ、配管自体を振動させ る現象。不快な騒音が生じるだけでなく、配管の損傷にもつながるため、対策 が必要となる。防止策として、 流速を小さくする (2.0m/s未満、一般には0.9~1.2m/s) 他、エアチャンバー等ウォーターハンマー防止器を設置するといったことが考 えられる。
3. クロスコネクション (混合配管)
上水給水用の配管とそれ以外の水の配管 (工業用水用、冷却水用、排水用等) とが不用意に直接連結され、不純な水が上水道配管中に混入するおそれがある 状態のこと。 衛生上の観点から禁止されている。
五. 給湯設備
1. 局所式と中央式
① 局所式
住戸ごとに加熱装置を設ける方法。 配管や加熱器の規模が小さく、維持管理しやすい。
a) ガス瞬間湯沸器 (瞬間式局所給湯方式)ガスで直接加熱して給湯する方式。 出湯能力は、 「号数」 で表され、 1号 は入水温度を25℃上昇させた湯を毎分1リットル出湯できる能力のこと をさす。
b) 電気温水器 (貯湯式局所給湯方式)熱源費が日中と比べて割安な深夜電力を利用して、 一定時間(8時間又 は5時間程度) 通電し、タンク内のヒーターで水を85℃に沸かして貯湯す る。電源は200Vなので、一般電灯配線とは別に深夜電力専用配線を設置 する必要がある。
② 中央式
地階の機械室などに加熱装置を設け、各住戸に給湯する方式。
2. 先止め式と元止め式
①先止め式
給湯器の出湯側にある栓を操作することによって給湯する方式のこと。
② 元止め式
給湯器の流入側にある栓を操作することによって給湯する方式のこと。
第2節 排水・通気設備
一. 排水
1. 排水の種類
排水には、水洗便所からのし尿を含む排水である「汚水」 台所排水風呂 排水 洗面排水等の 「雑排水」、 そして、雨水や湧水等の 「雨水」の3つがある。
2. 排水方式
敷地内の排水方式としては、 汚水と雑排水を同一系統で排水する 「合流式」 と、汚水と雑排水を別系統で排水する 「分流式」 とがある。
二. 排水・通気設備
1. 排水管の勾配
排水は通常自然流下方式であるため、 勾配が緩やか過ぎると排水の流れが悪 くなり、 逆に急勾配にしすぎると水だけが流れて固形物質が残る結果となるこ とから、 排水管の勾配が重要な要素となる。 一般に、 管径が太いものほど緩や かな勾配とすることとされている。
2. 排水立て管の管径
排水立て管の管径は、 管内の気圧を安定させ、 排水障害の発生を防ぐために、 それに接続する排水横枝管の最大管径以上とし、 どの階においても、最下部の 最も大きな排水負荷を負担する部分の管径と同一管径とする必要がある。
3. トラップ
① トラップとは
トラップとは、排水管を曲げるなどして水 (封水) を溜める部分のことを いう。これにより、排水管が蓋をされた形となり、臭気や害虫が排水管を経 由して室内に侵入することを防止する目的がある。トラップの封水の深さを封水深さといい、その距離は5cm~10cm(阻集 器を兼ねる排水トラップの封水深は、5cm以上) と規定されている。 なお、 封水深さはウェア(あふれ面)とディップ (水底面頂部) の垂直距離で測る。
②各種のトラップ
トラップには、Sトラップ (大便器 掃除用流し等に用いられることが多 い)、Pトラップ(洗面器等に用いられることが多い)、Uトラップ(横走配 管の途中に設ける) 椀トラップ (浴室、洗濯機置場などの床排水に使用さ れることが多い)などがある。
4. 通気管(ベントパイプ)
① 通気管とは
排水配管において、 管内の排水による気圧変化を大気に逃がし、 管内を大 気圧と等しい状態に維持するための管。 それにより封水を保持 (破封防止) し 排水の流れを円滑にする。
②各種の通気方式
a) ループ通気
複数の排水トラップを一括して通気するために設けられる通気管のこ と。 最上流の器具排水管が排水横枝管に接続する点のすぐ下流から立ち上 げ、 通気立て管に接続する方式。
b) 各個通気
排水トラップそれぞれに通気管を設ける方式。 トラップごとに通気がなされるので、 最良の通気方式といえる。
c) 伸頂通気
通気立て管を設置せず、 排水立て管の延長である伸頂通気管のみによっ て通気を行う方式。 別系統の通気立て管がなく、他の方式よりも一般に許 容排水流量が少ない。 低層の建築物に用いられる。ただし、特殊継手方式 (通気管としては伸頂通気管のみを有するもので、 立て管継手部や立て管脚部に特殊な継手を用い、立て管内部の排水を旋回 させて合流抵抗を緩和させ、通気のための空気コアを形成することで、通 気管と同じ機能を持たせたもの)を採用すれば、高層や超高層の建物でも可能である。
5. 排水に関する諸問題
① 破封
破封とは、封水が減少するなどして、トラップに空気が流入し、トラップ としての機能を失う現象をいう。破封の原因としては、自己サイホン作用 (水受け容器から大量の排水が行 われた場合、 トラップと器具排水管の空気がなくなって排水が満流となり、 サイホン作用を生じることによって、封水がなくなる現象) 誘導サイホン 作用 (排水立て管の排水が瞬間的に満水状態で流れた場合、その付近の排水 横管に吸引作用を生じ、 封水を持ち去ってしまう現象)、逆サイホン作用 (上 下階で同時に大量の排水があった場合に、 中間階の排水トラップの封水が室 内側に飛び出す現象。 跳ね出し作用ともいう。)、 毛細管現象 (トラップウェ アに毛髪などが引っかかって垂れ下がったままになった場合に、 毛髪等を伝 わって封水が流れていく現象)、 蒸発 (長期にわたって排水をしないと、封 水が蒸発することで結果的に破封すること) などが挙げられる。
② 二重トラップ
二重トラップとは、 1つの排水系統に2個以上のトラップを直列に設置し たものをいう。 トラップを二重にすると、 排水管内の圧力変動で、排水障害 が生じるため、禁止される。
6. ディスポーザー排水処理システム
ディスポーザー、専用排水管、 排水処理槽等により構成され、 生ごみ等を破 砕して、ディスポーザー排水と台所排水とを合わせて排水中の固形物等を処理 する専用の排水処理槽で一定のBOD濃度まで処理した後、下水道に放流する。 破砕時の騒音と震動が伝播しないように、ディスポーザーには機器に防振装 置等を取り付けるなどする。 ディスポーザーから排水槽への専用管は、浴室洗 面系や汚水系排水管とは分離される。
第3節 換気・冷暖房設備
一. 換気設備
換気の方式としては、室内外温度差や圧力を利用する 「自然換気方式」と、機 械力によって強制的に換気を行う 「機械換気方式」 があるさらに、機械換気方式は、 ①給気、 排気ともファンなどの機械を用いる 「第1 「種換気方式」 ② 給気のみにファンを用いる 「第2種換気方式」 ③ 排気のみにフ ァンを用いる 「第3種換気方式」 に分類される。換気が有効に行われるためには、 排気量にみあう給気の確保が必要となる。 特 に第三種機械換気方式では、 給気の確保が不十分だと、 換気扇の能力を大きくし ても必要な換気量を確保することはできないため、 十分な給気の確保がよりいっ そう重要となる。
二. 冷暖房設備
マンション等では、 一棟全体のための冷暖房設備を設置する 「住棟セントラル 方式」、 住戸ごとに冷暖房設備を設置する 「住戸セントラル方式」、必要な部屋ご とに冷暖房設備を設置する 「個別方式」 などが用いられる。 戸建てでは、一般に 住戸セントラル方式と個別方式が用いられる。
第4節 電気ガス設備
一. 電気設備
1. 電力の引き込み
建物への電力の引き込みは、 供給電圧によって「低圧引き込み」、 「高圧引き 込み」、 「特別高圧引き込み」 の3種類に分類される。引き込み方法としては、 「単相三線式」 「単相二線式」 といった種類がある。 三本のケーブルのうち二本を使い分けることにより 「100V」 「200V の電気 製品が使用できる 「単相三線式」 が一般的である。
2. 各種引き込み
① 低圧引き込み
契約電力が50kW未満の場合の引き込み方法。
②高圧引き込み
契約電力が50kW以上の場合における引き込みの方法。 戸建てでは通常この方式はない。
a) 借室方式
借棟方式借室方式とは、 建築物内の1室を変圧器室として電力会社へ無償で提供 する方式のことをいう。 借室内部空間と受変電設備等は電力会社の管理対 象物となる。 また、 借棟方式とは、 建築物敷地内に変圧器棟を設置して電 力会社へ無償で提供する方式のことをいう。 借室内部空間と受変電設備等 は、電力会社の管理対象物となる。借室 借棟には、 電力会社関係者の立会いがなければ入室できず、その 維持管理一切は電力会社が行う。
b) 集合住宅用変圧器方式
敷地内の屋外に、地上用変圧器を設置して供給する方式のことをいう。 パットマウント方式とも呼ばれる。 1戸あたり 50A契約で、 最大 100戸 程度まで供給を受けることができる。
c) 借柱方式
電柱上に変圧器を設置して供給する方式のこと。
3.電気工作物
① 電気工作物とは
送電 配電など電気の使用のために設置する機械、 器具その他の工作物を 電気工作物という。主に一般住宅や小規模店舗のように、一定以下の電圧で受電し、受電場所 と同一の構内においてその受電にかかる電気を使用するための電気工作物 のうち、一定のものなどを 「一般用電気工作物」、それ以外の電気工作物を 「事業用電気工作物」という。
② 自家用電気工作物
共用部分の契約電力のみで 50kW以上となるときは、自家用受変電設備を 設置した自家用電気室を設けて変圧する。電気事業法の定義では、 自家用電気工作物とは、 電気事業の用にする電気 工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物とされている。
4. インバーター
① インバーターとは
インバーターとは、 電気の交流を直流にし、 直流を任意の電圧 周波数の 交流に再変換させるための装置 (周波数の変換装置) である。 インバーター 制御により、モーターの回転数などを連続的に切り替える。
②インバータータイプにすることによる利点
インバータータイプにすることで、50Hz/60Hz の変換が不要となり、日 本のどこでも機器の使用ができるようになる。 また、省エネルギー化も図れ る。
二. ガス設備
1. 使用されるガスの種類
地域にもよるが、 都市ガス、 プロパンガスなどの液化石油ガス(LPG) などが使用されている。都市ガスは、石炭、 コークス、 ナフサ 天然ガス等を原料として製造したガ スを精製、混合して所定の発熱量に調整したもので、一般に空気より軽い。一方、液化石油ガス (LPG) は、常温常圧では気体で、圧力を加えたり、 冷却したりすれば容易に液化する、 石油中に含まれている炭化水素類の総称をいい、一般に空気より重い。
2. ガス供給業者
都市ガス業者によりガスが供給されている場合、 設計施工は各都市ガス事業 者の責任となっており、一般業者が行うことはできない。 なお、屋内ガスの配 管には配管用炭素鋼管 (SPG)、 屋外には管径75mm未満は鋼管、 75mm以 上は鋳鉄管を用いることが多い。
3. ガス用品
主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる一定の機械器具 又は材料のこと。
4. 特定ガス用品
ガス用品のうち、 構造、 使用条件、 使用状況等からみて特にガスによる災害 の発生のおそれが多いと認められるもののこと。
5. ガス漏れ検知器の設置位置
検知器は、 使用しているガスが都市ガスの場合は、 燃焼機器から水平距離8 m以内の範囲で天井下 30cm以内の位置に、 液化石油ガス(LPG) の場合は、 燃焼機器から水平距離 4m以内の範囲で床上 30cm 以内の位置に取り付けるも のとされている。 なお、 出入口 換気口付近では、 検知器を設置しないように する必要がある。
6. マイコンメーター
マイコンメーターは、基本的な安全システムで、 ガスメーターにマイコン機 能を搭載したもの。 マイコンに正常なガスの使用パターンが記憶されており、 ガス漏れや消し忘れ、 地震などの異常を感知するとガスを自動的に遮断する機 能を有する。
第5節 消防設備
一. 火災消火
1. 火災の種類
火災は、火災の原因となるものに応じて、A火災、 B火災、C火災、ガス火災などの種類に分けられる。火災とは、普通火災のことで、木材、紙、繊維等の一般可燃物による火災 をいう。 B火災とは、油火災のことで、石油類等の油類による火災をいう。 火災とは、電気火災のことで電気施設など感電のおそれのある火災をいう。 ガ ス火災とは、 可燃性ガスによる火災をいう。
2. 消火方法の種類
火災が発生した場合の消火方法には、いくつかの種類がある。 火災原因によ り有効な消火方法が異なる。
① 冷却消火
水をかけて発火温度以下にすることで消火する方法。 A火災に対して有効である。
② 窒息消火
泡、 二酸化炭素、 四塩化炭素などで火を覆い、燃焼に必要な酸素を遮断す ることで消火する方法。 B火災、 C火災に対して特に有効である。
③負触媒作用による消火
ハロゲン化物などが気化すると重い気体となる性質を利用し、 燃焼部分を覆わせて、 燃焼に必要な酸素を遮断することで消火する方法。
④ 除去消火
火災の周囲にある可燃物を除去することで消火する方法。
二. 消防用設備等
1. 設置・維持
消防法上、 一定の防火対象物について、関係者(所有者、管理者又は占有者) は、一定の消防の用に供する設備、 消防用水及び消火活動上必要な施設を設置 し、及び維持しなければならない。
2. 消防用設備等の種類(概論)
消防用設備等については、消防法上、 ①消防の用に供する設備、 ②消防用水、 ③ 消火活動上必要な施設の3つの種類がある。このうち①については、さらに 消火設備、警報設備、避難設備に分類される。なお、消防の用に供する設備 消火設備 警報設備 避難設備) は、 建築物 に消防隊が到着するまでの間、 建築物利用者側が使用することを念頭に置いた 設備である。 これに対し、 消防用水及び消火活動上必要な施設は、 消防隊が消 火活動に使用することを念頭においた設備である。
3. 消防用設備等の種類 (各論)
① 消防の用に供する設備
a) 消火設備に分類されるもの消火器及び簡易消火器具 (水バケツ、 乾燥砂)、 屋内消火栓設備、スプ リンクラー設備、 水噴霧消火設備、 泡消火設備、不活性ガス消火設備、二 酸化炭素消火設備、 ハロゲン化物消火設備、 粉末消火設備、 屋外消火栓設 備、動力消防ポンプ設備
b) 警報設備に分類されるもの自動火災報知設備、 ガス漏れ火災警報設備、 漏電火災警報器、 消防機関 へ通報する火災報知設備、 警鐘、 携帯用拡声器 手動式サイレンその他の 非常警報器具及び非常用警報設備 (非常ベル、 自動式サイレン、 放送設備)
c) 避難設備に分類されるもの避難器具又は設備 (すべり台、避難はしご、 救助袋 緩降機、 避難橋そ の他の避難器具) 誘導灯及び誘導標識
② 消防用水
防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
③ 消火活動上必要な施設
排煙設備、 連結散水設備 連結送水管、 非常コンセント設備、 無線通信補助設備
4. 主要な消防用設備等の説明
① 消火器
・火災を発見した者が、 初期消火に使用するもの。
② スプリンクラー設備
・火災発生時に自動的に熱を感知し、自動的に天井のスプリンクラーヘッド から出火箇所に散水消火を行う設備。・ヘッドの放水口が常時閉じている閉鎖型と常時開放している開放型とがある。・配管を満水にして圧力を加えておく湿式と、配管に水のかわりに加圧空気 を入れておく乾式とがあり、寒冷地を除いて一般に湿式が用いられる。
③自動火災報知設備
・煙又は熱を感知して、 自動的に警報を発する。 煙感知器型と熱感知器型とがある。煙感知器には、 光電式とイオン式とがある。熱感知器には、周囲が一定以上の温度になった場合に作動する定温式と、 一定の温度上昇 (温度差) があると作動する差動式とがある。 火が燃える ときの火焔のゆらめきを感知する炎感知式も実用化されている。
④ 非常警報設備
押ボタンを押すことで発せられる信号を受信して警報を発する非常ベル及 び自動式サイレンと、スピーカーから音声で警報を発する放送設備とがあ る。
⑤避難器具
避難はしご、緩降機等、 避難をする場合における安全を補助するための器 具。
⑥ 誘導灯
火災等の非常時に、避難口 避難通路、 避難方向を灯火により表示し、避 難時の混乱を未然に防ぎ安全に避難口に誘導させるためのもの。・誘導灯には、避難口誘導灯、 廊下通路誘導灯、 室内通路誘導灯、客席通路 誘導灯などがあり、これらには、 大型 中型 小型の区分や点灯時間、 色 (緑色) などの規定がされている。常時点灯が原則で、 非常時には、 非常用の予備電源で20分以上点灯する ことが要求されている。
三. 消防法の規定
1. 消防用設備等の設置及び維持義務
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合 用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者(所有者、管 理者又は占有者)は、政令で定める消防の用に供する設備、 消防用水及び消火 活動上必要な施設 (消防用設備等)について消火、 避難その他の消防の活動の ために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、 設置し、及び維持しなければならない。消防長又は消防署長は、火災予防のため必要があれば、関係者に対し資料の 提出を命じ、 若しくは報告を命じ、 又は当該消防職員に立ち入り検査をさせる ことができる。 その他、 防火対象物の改修、 移転、 使用禁止等を命ずることも できる。
2. 消防用設備等の点検及び点検結果報告義務
一定の防火対象物の関係者は、 消防用設備について消防設備士等の有資格者 に、法定の点検をさせ、 その結果を定期に消防長又は消防署長に報告しなけれ ばならない。この期間は、 店舗・事務所建物や複合用途建物等の特定防火対象物では1年 に1回、一般の共同住宅等の非特定防火対象物では3年に1回である。
3. 点検の種類と期間
① 機器点検 (必要な設備につき、 6ヶ月に1回行う)
消防用設備等に附置される非常電源 (自家発電設備に限る。) 又は動力消防ポンプが正常に作動するかを、 点検基準に従って確認する。消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項について、 点検基準に従って確認する。.消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項について、 点検基準に従って確認する。
②総合点検 (必要な設備につき、1年に1回行う).
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使 用することによって、 当該消防用設備等の総合的な機能について点検基準に従って確認する。
4. 消防設備等の点検資格者について
① 延べ面積 1,000㎡以上の特定防火対象物
消防設備士 (免状の交付を受けている者) 又は消防設備点検資格者による点検が義務付けられている。
②延べ面積 1,000 ㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの。消防設備士免状の交付を受けている者) 又は消防設備点検資格者による点検が義務付けられている。
③ ①② 以外の防火対象物消防設備士(免状の交付を受けている者)、 消防設備点検資格者による点 検が望ましいが、建築物の関係者や防火管理者等でも行うことができる。な 防火管理者とは、一定の資格を有した者で、防火対象物において防火管 理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にあ る者をいう。
5. 消防長又は消防署長の権限
消防長又は消防署長は、 消防用設備等が消防法に定める技術上の基準に従っ て設置又は維持されていない防火対象物の管理権原者に対して、 必要な措置を 講じるように命じることができる。
6. 高層建築物にかかる消防計画の作成等
高さ 31mを超える5. 消防長又は消防署長の権限建築物その他政令で定める防火対象物で、 一定の管理に関 する権原を有する者は、その防火対象物について、 消防計画の作成その他の防 火管理上必要な業務に関する一定の事項を、 協議して定めておかなければなら ない。