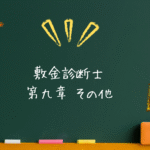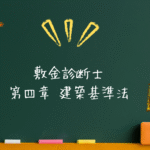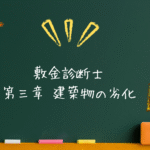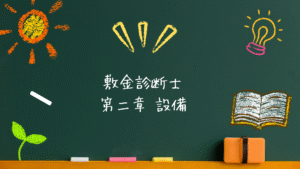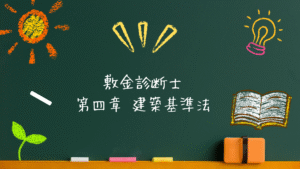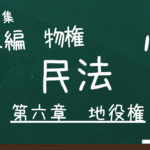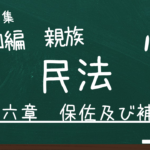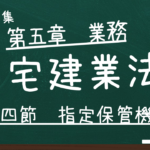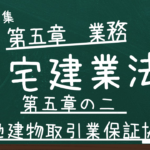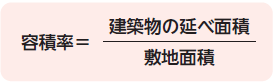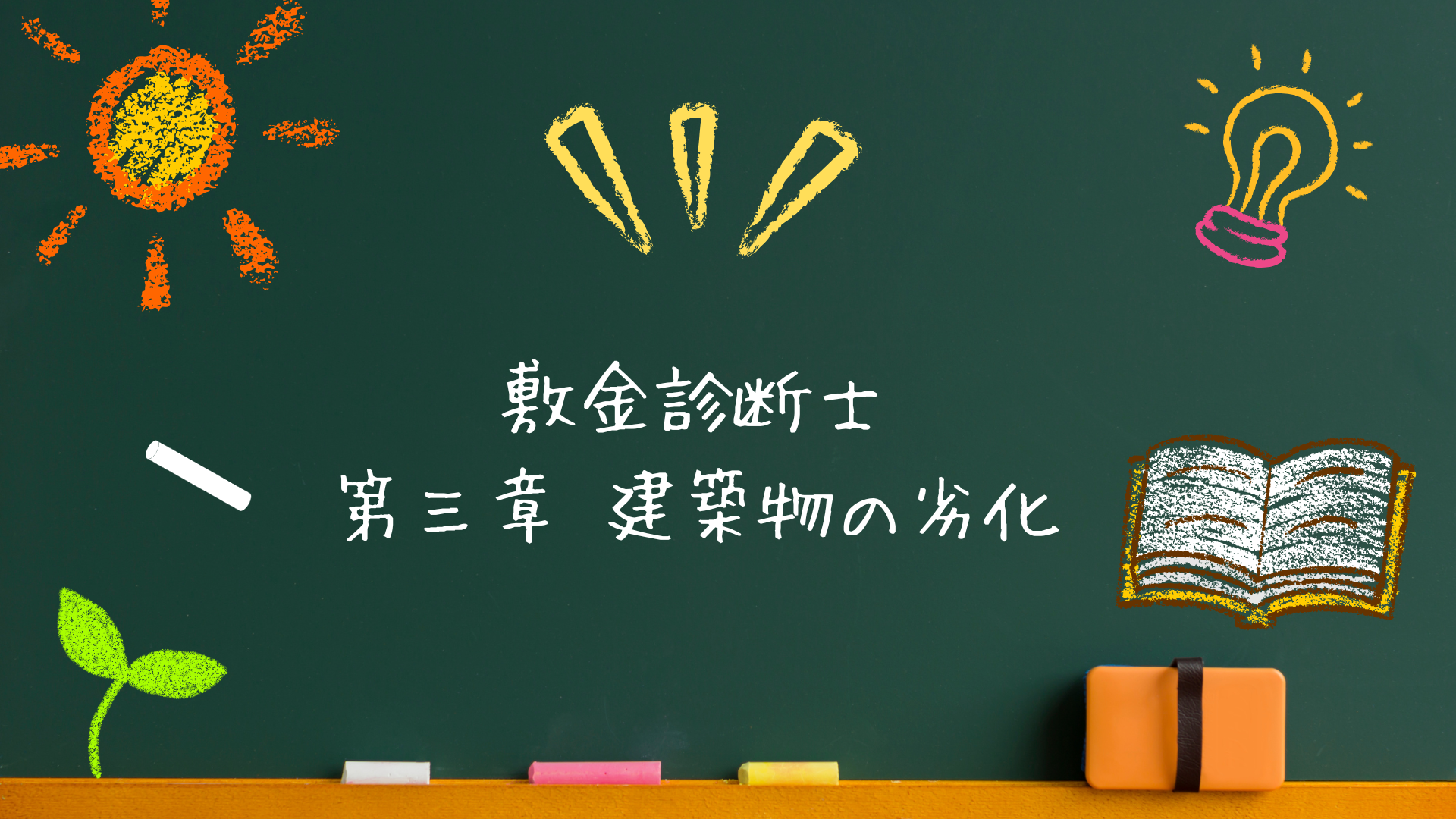
Contents
第1節 建築物の劣化
一. 劣化の種類
建築物の劣化の種類は、物理的劣化機能的劣化・社会的劣化の3つに分類す ることができる。
① 物理的劣化
建築物は、 建築されてから一定年数を経過すると、雨水・空気中の炭酸ガス 等の化学的要因や継続使用による減耗などの物理的要因等によって、使用材 料 機器の劣化が始まる。 さらに、年月が経過するとともに劣化の範囲が広が り、その程度も大きくなっていく。 これを物理的劣化という。
②機能的劣化
様々な技術の進歩があれば、 建築時には存在しなかった材料が開発されたり、 より性能の高い機器等が開発されたりする。 その結果、 建築時に設置された機 器等の性能が相対的に低下する。 また、 法規制の変化により、 現存する建築物 の性能が法制度上低下することもある。 このようなことを原因とする劣化を機 能的劣化という。
③社会的劣化
高度情報化、 生活スタイルの多様化、生活に潤いやゆとりなどを求める社会 の変化に応じて、 建築物に求められる内容も変化する。 そうした社会的要求水 準や要求内容が変化したことによって生じる劣化のことを社会的劣化という。
ニ. 劣化診断項目・診断方法等
1. 木造の劣化
① 生物劣化
生物劣化とは、腐朽菌やしろあり等による木材の腐朽ならびに食害をさす。 木材の劣化現象は、 害虫、 結露、カビ、 雨漏りなど様々な原因により発生す るが、とりわけシロアリによる被害が大きな割合を占める。日本に棲息するしろありの種類は、「やまとしろあり」、 「いえしろあり」、 「さつましろあり」、「かたんしろあり」 「おおしろ」の5種類があると言わ れるが、そのうち特に「やまとしろあり」と「いえしろあり」による被害 が大きい。
「やまとしろあり」は北海道の一部を除くほぼ日本全土に分布し、湿潤し た木材を対象として食害が生じさせるので、腐朽箇所と同様、建物の下部に 被害が集中する。 一方、「いえしろあり」は、本州では静岡以西の海岸線に 四国・九州では平地に分布するとされる。 やましろありと異なり水分補給能 力があるため、乾燥状態の木材でも食害を発生させる。
②水廻り等、 水分による腐朽
水を使用する部位、水がかかりやすい部位で、木材に水がかかることによ って生ずる腐朽のこと。
③ 接合金物の腐食による腐朽
木材等を接合する金物が経年劣化で腐食することにより、構造木材が腐朽 すること。
2. 構造躯体の劣化 (鉄筋コンクリート造の典型的なもの)
① 鉄筋腐食
コンクリートの中性化やひび割れ、 侵食性化学物質 漏洩電流等によって 鉄筋に錆が発生する現象。
② ひび割れ
打ちこんだ時点では一体であったコンクリート部材に、 その後コンクリー トの許容応力度以上の応力が作用して生じるコンクリートの部分的破壊現 象。 コンクリートの打継面、 コールドジョイント等のコンクリートの不連続 部分とは、 発生過程の上で区別される。なお、 鉄筋に沿ったひび割れは、 面的に見て配筋の位置と思われる個所に 発生し、一般に鉛直又は水平の直線状のパターンを呈する。 これに対し、開 口部におけるひび割れは、開口部の隅角部から斜めに発生する。
③ 漏水
水が存在する環境下において、水が部材断面を透過してしみ出るか、ある いは部材内及び部材間の間隙部分を通して漏出する現象のこと。 ここでいう 間隙部分とは、コンクリート部材内に発生したひび割れ、 コールドジョイン ト、豆板等の他に、 部材間の打継面、 接合部等を総称する。
④ 強度劣化
低品質材料使用環境・熱作用 化学作用・疲労等によって、 コンクリー トの強度が低下する現象。 ここでは竣工時に強度が低かったものも含む。
⑤大たわみ
鉄筋の腐食・ひび割れ・強度劣化のほか、設計、施工欠陥、 構造的外力作 用・熱作用等によって、主として水平部材が大きく変形する現象 (短期荷重 は除く)。
⑥ 表面劣化
コンクリートの表面が、 使用環境 熱作用 化学作用によって損傷し、 ポ ップアウトや剥離、 剥落などを起こす現象 (凍害による表面劣化は別に扱う)。
⑦ 中性化
コンクリートのアルカリ性が、 空気中 水中に存在する炭酸その他の酸性 ガスあるいは塩類の作用によって失われる現象。
⑧コールドジョイント
連続して大量のコンクリートを打ち込んだり、 急結剤を使用したコンクリ ートを打ち込んだりして、 打設を中断したり遅延させたりした場合に、 先に 打ち込んだコンクリートの凝結が始まり、その間に施工継目が生じた状態と なって生ずる肌離れの継目のこと。 一般に、 気温が高い方がコンクリートの 硬化が早まり、 コールドジョイントが発生しやすい。
⑨ 豆板
コンクリートを打ち込む際にできた充填の不良部分のこと。材料の分離や 締固め不足などの原因によって、硬化したコンクリート中の一部に粗骨材が 集まり、 露出した空隙の多い部分を指す。
⑩ 浮き
仕上材が躯体から剥離したり、 躯体コンクリートで鉄筋のかぶり等が浮いている状態。
⑪ 錆汚れ
腐食した鉄筋の錆がひび割れ部から流出して、 仕上材又はコンクリートの表面に付着している状態
⑫ 錆鉄筋露出
腐食した鉄筋が表面のコンクリートを押し出し、剥離させ、露出した状態 で、新築時のかぶり厚さ不足が主な原因である。 点状、線状、ひどい場合に は網目状に露出することもある。
⑬ エフロレッセンス (白華現象)
硬化したコンクリートの表面に出た白色の物質で、コンクリート中の水分 やひび割れから浸入した雨水が、コンクリート中の可溶性物質(石灰等)を 溶解し、この溶液が表面に出てきて空気中の炭酸ガスと化合して、固まって 白色の粉状等になったものをいう。
⑭ ポップアウト
コンクリート内部の部分的な膨張圧によって、 コンクリート表面の小部分 が円錐形のくぼみ状に破壊された状態のこと。
3. 各種診断の種類 内容
① 中性化深さの診断
コンクリートの中性化が進行すると、内部の鉄筋が錆びて膨張してコンク リートのひび割れ等が発生し、その結果、 躯体の強度が低下するので、問題 である。そこで、 中性化の進行具合を診断するために測定部位のコンクリートを一 部円筒状に抜き取り、取り出したものにフェノールフタレイン溶液を噴きつ けて、スケールで中性化深さを測定する。 フェノールフタレイン溶液は、対 象物が pH10 以上のアルカリ性を帯びていると赤色に変色し、 それ以下のpH では変色しないという特性を持つ。
②コンクリート中の塩分量の診断コンクリート中の塩分量が多いと、 鉄筋を腐食させ、鉄筋コンクリートの 耐久性の低下につながる。 塩分量の診断は、コア抜きしたコンクリートを試 験場に持ち込んで行う。
③コンクリートの圧縮強度の診断
コンクリート強度の診断は、対象物から抜いたコンクリートコアを破壊し 検査診断する破壊検査と、 より簡易な方法である非破壊検査とがある。 非破 壊検査としては、シュミットハンマー試験が代表的である。
④ ひび割れの診断ひび割れ箇所は、鉄筋の腐食箇所や漏水箇所と関連が深い。 クラックスケ ールなどでひび割れの幅を把握した上で、 その程度により補修方法を決める。 補修方法としては。 Uカットシール工法や、エポキシ樹脂注入工法 (自動低 圧注入) 等がある。
⑤ 浮きの診断
コンクリートやタイルの浮きの有無、程度を調査するもの。 パールハンマ(テストハンマー)を用い、打音で判断する。
⑥ 外壁タイルの診断
a) 打撃診断外壁打診用ハンマー (パールハンマー) で部分打診、 全面打診をし、そ の打音により浮きの有無と程度を判断する。
b) 非破壊診断
・反発法タイル面に一定の打撃を加え、その衝撃により生じた跳ね返りの大きさを自動的に記録し、 タイルの浮き等を調査する。
・赤外線装置法 (赤外線サーモグラフィ法)建築物の外壁タイル又はモルタル仕上げ等の剥離部と健常部の熱伝導 の違いによる温度差を赤外線映像装置によって測定し、 タイル面の浮き 等の程度を調査する。
c) 破壊診断
・付着強度試験アタッチメントのタイル面への接着面を紙やすりで磨き、シンナーで拭 いて油脂分を除去した上、 タイル表面にアタッチメントを速乾性接着剤 及びガムテープで固定する。 そして、 タイル目地に沿ってコンクリート 躯体までディスクサンダーで切り目を入れ、 引張試験機で引っ張り、 破 断したときの測定値から、 付着強度を算出する。
⑦ 外壁塗装の診断
外壁塗装は、塗膜の表面の劣化と塗膜内部の劣化等に分類できる。 表面の 劣化現象には、汚れの付着、 光沢度低下、 変退色、 白亜化、 磨耗がある。 方、内部の劣化現象には、 ふくれ、 割れ、剥れ、 磨耗、 それらの混在がある。 塗装の付着度を測定する方法としては、塗装表面にカッターで格子状の傷 をつけてその上からテープなどを貼り、剥がした後の塗装の残り具合で塗装 の付着度を測定するクロスカット試験がある。