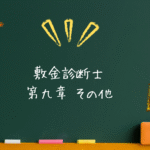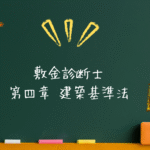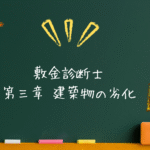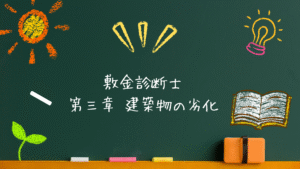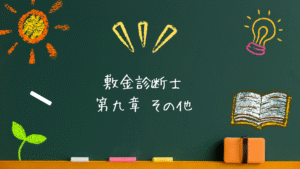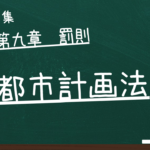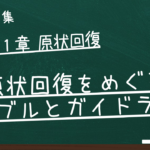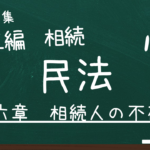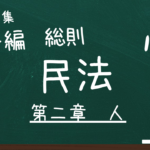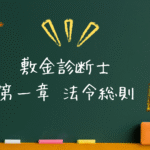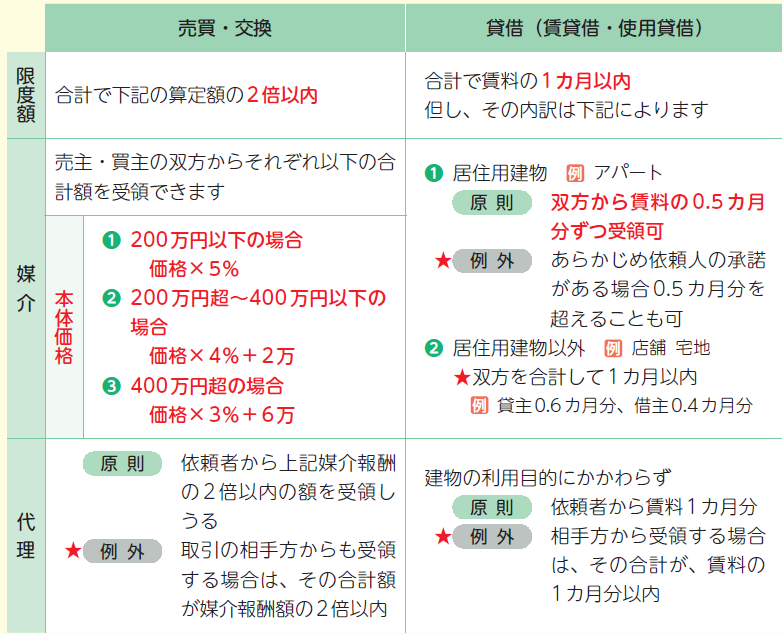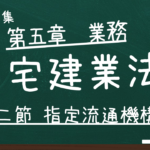Contents
- 1 第1節 総論
- 1.1 一. 建築基準法の目的
- 1.2 二. 建築基準法の全体構造
- 1.3 三. 建築基準法における用語の定義
- 1.3.1 1. 建築物
- 1.3.2 2. 特殊建築物
- 1.3.3 3. 建築設備
- 1.3.4 4. 居室
- 1.3.5 5. 敷地
- 1.3.6 6. 地階
- 1.3.7 7. 主要構造部
- 1.3.8 8. 延焼のおそれのある部分
- 1.3.9 9. 構造耐力上主要な部分
- 1.3.10 10. 耐火構造
- 1.3.11 11. 準耐火構造
- 1.3.12 12. 防火構造
- 1.3.13 13. 耐火建築物
- 1.3.14 14. 準耐火建築物
- 1.3.15 15. 防煙壁
- 1.3.16 16. 不燃材料
- 1.3.17 17. 準不燃材料
- 1.3.18 18. 難燃材料
- 1.3.19 19. 耐水材料
- 1.3.20 20. 設計図書
- 1.3.21 21. 建築
- 1.3.22 22. 大規模の修繕
- 1.3.23 23. 大規模の模様替
- 1.3.24 24. 建築主
- 1.3.25 25. 設計者
- 1.3.26 26. 工事施工者
- 1.3.27 27. 特定行政庁
- 1.3.28 28. 敷地面積
- 1.3.29 29. 建築面積
- 1.3.30 30. 床面積
- 1.3.31 31. 延べ面積
- 1.3.32 32. 築造面積
- 1.3.33 33. 建築物の高さ
- 1.3.34 34. 軒の高さ
- 1.3.35 35. 階数
- 2 第2節 単体規定
- 3 第3節 集団規定
第1節 総論
一. 建築基準法の目的
建築基準法は、建築物の敷地、構造、 設備及び用途に関する最低の基準を定め さて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資する ことを目的としている。
二. 建築基準法の全体構造
建築基準法には、その制度自体に関する規定の他に、単体規定と集団規定とが ある。単体規定とは、全国すべての建築物に全国一律の基準で、建築物の単体として の構造耐力・防火 避難上の安全・衛生上の環境について最低基準を定めたもの をいう。 個々の建築物や設備が単体として備えていなければならない構造耐力、 防火、 衛生などに関する技術的な最低限度の基準を定めた規定で、 全国一律に適 用されるものである。集団規定とは、原則として都市計画区域内及び準都市計画区域内の建築物につ いて、その敷地、構造及び建築設備に関して用途・形態・ 構造設備面から規制 を加えるものをいう。 町や都市など建築物が密集する地域において、安全で合理 的な土地利用の調整と環境保護を図るための規定で、 容積率や建蔽率等がその具 体例となる。
三. 建築基準法における用語の定義
1. 建築物
土地に定着する工作物のうち、 ①屋根、及び、 ②柱又は壁を有するものなどをいい、建築設備を含む。
2. 特殊建築物
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、 集会場、 展示場、 百貨店市場、ダン スホール、遊技場、公衆浴場、旅館、 共同住宅、 寄宿舎、 下宿、工場、倉庫、 自動車車庫、 危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類 する用途に供する建築物をいう。
3. 建築設備
建築物に設ける、 電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙。 汚物処理の設備、又は、 煙突、昇降機、 避雷針をいう。
4. 居室
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に 使用する室をいう。
5. 敷地
一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土 地をいう
6. 地階
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さ の3分の1以上のものをいう。
7. 主要構造部
壁、柱、床、はり、屋根、階段をいい、 建築物の構造上重要でない間仕切壁、 間柱、 附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、 小ばり、ひさし、局部的 な小階段 屋外階段などを除く。
8. 延焼のおそれのある部分
隣地境界線 道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物 (延べ面積の合計 が 500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。) 相互の外壁間の中心線から、 1階にあっては3m以下、 2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の 部分をいう。 ただし、 ① 防火上有効な公園、 広場、 川等の空地若しくは水面又 は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分と、 ② 建築物の外壁面 と隣地境界線等との角度に応じて、 当該建築物の周囲において発生する通常の 火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が 定める部分 (熱の影響を受けにくい部分)を除く。
9. 構造耐力上主要な部分
基礎 基礎ぐい 壁、柱、 小屋組、 土台、 斜材 (筋かい、方づえ、 火打材そ の他これらに類するものをいう。)、 床版、 屋根版又は横架材 (はり、 けたその 他これらに類するものをいう。) で、 建築物の自重若しくは積載荷重、 積雪、 風圧、 土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをい う。
10. 耐火構造
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能に関して政令で定 める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、 れんが造その他の構造で、国 土交通大臣が定めた構造方法を用いるものなどをいう。
11. 準耐火構造
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能に関して政令で 定める技術的基準に適合するもので、 国土交通大臣が定めた構造方法を用いる ものなどをいう。
12. 防火構造
建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、 防火性能に関して政令で定める技術的 基準に適合する鉄網モルタル塗、しっくい塗その他の構造で、 国土交通大臣が 定めた構造方法を用いるものなどをいう。
13. 耐火建築物
主要構造部が① 耐火構造又は 「耐火建築物の主要構造部に関する技術的基 準」に適合するもので、「かつ」、 ②外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に 防火設備を設けたものをいう。
14. 準耐火建築物
主要構造部が① 準耐火構造又は 「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する建 築物の技術的基準」 に適合するもので、 外壁の開口部で延焼のおそれのある部 分に防火設備を有する建築物。
15. 防煙壁
間仕切壁や天井面から 50cm 以上下方に突き出した垂れ壁、 その他これらと 同等以上の煙の流動を妨げる効用のあるもので、 不燃材料で造り又は覆われたもの。
16. 不燃材料
建築材料のうち、20分間の不燃性能があるもので、 国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。
17. 準不燃材料
建築材料のうち、10分間の不燃性能があるもので、 国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。
18. 難燃材料
建築材料のうち、5分間の不燃性能があるもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。
19. 耐水材料
れんが、 石、 人造石、コンクリート、 アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。
20. 設計図書
建築物、その敷地又は一定の工作物に関する①工事用の図面 (現寸図その他これに類するものを除く。)、及び、 ②仕様書をいう。
21. 建築
建築物を新築し、増築し、改築し、又は、移転することをいう。
22. 大規模の修繕
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
23. 大規模の模様替
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
24. 建築主
建築物に関する工事の請負契約の注文者、又は、請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
25. 設計者
その者の責任において、 設計図書を作成した者をいう。
26. 工事施工者
建築物、 その敷地などに関する工事の請負人、又は、請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
27. 特定行政庁
原則として、 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。
28. 敷地面積
原則として、敷地の水平投影面積による。
29. 建築面積
原則として、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線 (軒、 ひさし はね 出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出 たものがある場合においては、 その端から水平距離1m後退した線)で囲まれ また部分の水平投影面積による。 なお、 地盤面上1m以下の地階部分は算入され ない。
30. 床面積
建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水 平投影面積による。
31. 延べ面積
原則として、建築物の各階の床面積の合計による。
32. 築造面積
原則として、 工作物の水平投影面積による。
33. 建築物の高さ
原則として、 地盤面からの高さによる。 棟飾、 防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、 当該建築物の高さに算入しない。
34. 軒の高さ
原則として、地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた又は柱の上端までの高さによる。
35. 階数
階数は、原則として、各階の床の数をもって算入する。 ① 昇降機塔、 装飾塔、 物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、 機械室その他 これらに類する建築物の部分で、 水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の 建築面積の8分の1以下のものは、 当該建築物の階数に算入しない。 ②建築物 の一部が吹抜きとなっている場合、 建築物の敷地が斜面又は段地である場合そ の他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のう ち最大なものによる。
第2節 単体規定
一. 居室の構造等
住宅の居室には、健康上の理由から、採光が必要である。 また、居室内の通 風や火気の使用等による室内汚染を防ぐために換気が必要となる。
1. 居室の採光
住宅、学校、病院、診療所、 寄宿舎、 下宿等の居室には、原則として採光 のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室 の床面積に対して一定の割合としなければならない。 具体的には、住宅に関し ては7分の1以上、 その他の建築物に関しては、5分の1~10分の1である。 なお、居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開 口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定す るものとされている。
2. 居室の換気
居室には、 換気のための窓その他の開口部を設け、 その換気に有効な部分の 面積は、その居室の床面積に対して、 20分の1以上としなければならない。
3. 建築物の調理室、 浴室等の換気設備
建築物の調理室、 浴室その他の室でかまど、 こんろその他火を使用する設備 若しくは器具を設けたものには、 原則として、 換気設備を設けなければならな い。ただし、密閉式燃焼器具等以外の火を使用する設備又は器具を設けていな い室等については、 換気設備を設ける必要はない。かかる火気を使用する部屋の換気設備の設置は、後述するシックハウス対策 用の機械換気設備を設けたとしてもそれだけで免除されることにはならない。
4. 換気設備
建築基準法上、 換気設備としては、 自然換気設備、 機械換気設備、 中央管理 方式の空気調和設備、それ以外の設備で一定の基準に適合し、国土交通大臣の 認定を受けたものの4種類が規定されている。
a) 建築物 (換気設備を設ける調理室等を除く) に設ける自然換気設備の構造
換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。
・給気口は、居室の天井の高さの2分の1以下の高さの位置に設け、 常時外 気に開放された構造とすること。
排気口 (排気筒の居室に面する開口部) は、 給気口より高い位置に設け、 常時開放された構造とし、かつ、 排気筒の立上り部分に直結すること。
排気筒は、 排気上有効な立上り部分を有し、 その頂部は、 外気の流れによ って排気が妨げられない構造とし、かつ、 直接外気に開放すること。 排気筒には、その頂部及び排気口を除き、 開口部を設けないこと。
給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、 雨水又はねずみ、 虫、ほこり その他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。
b) 建築物 (換気設備を設ける調理室等を除く) に設ける機械換気設備の構造
・換気上有効な給気機及び排気機 換気上有効な給気機及び排気口又は換気 上有効な給気口及び排気機を有すること。
・給気口及び排気口の位置及び構造は、 当該居室内の人が通常活動すること が想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ、 著しく局部的な 空気の流れを生じないようにすること
・給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口に は、雨水又はねずみ、 虫、 ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設 備をすること。
・直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設ける場合には、外気 の流れによって著しく換気能力が低下しない構造とすること
・風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造ること。
二. 石綿の飛散又は発散に対する衛生上の措置
1. 石綿とは
石綿とは、 天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、アスベストとも呼ばれる。 従来、断熱材、 保温材、 防音材などで多用されていた。 近年、石綿の繊維は、 じん肺、悪性中皮腫 肺がん等の原因となることが指摘され、その対策として 平成18年10月に、工作物の解体等の作業による石綿の飛散の防止、石綿を添 加した建築材料の使用の制限、 石綿が含まれる廃棄物の無害化処理の促進等の 措置を講ずることを内容とする 「石綿による健康等に係る被害の防止のための 大気汚染防止法等の一部を改正する法律」 が施行された。これを受けて建築基 準法においても、 建築物における石綿の使用が規制されることとなった。
2. 石綿の種類
石綿には、いくつかの種類があるが、 代表的なものは、 白石綿(クリソタイ ル)、青石綿 (クロシドライト)、 茶石綿 (アモサイト) である。 クロシドライ トとアモサイトは、 クリソタイルと比べて、 一般的に発がん性が強い。
3. 石綿に対する規制
① 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物 質 (石綿等)を添加しないこと。
②石綿等をあらかじめ添加した建築材料 (石綿等を飛散又は発散させるおそ れがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を 受けたものを除く。) を使用しないこと。
③吹付け石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用してはならない。
④吹付けロックウールで、その含有する石綿の重量が、 建築材料の重量の0.1%を超えるものをあらかじめ添加した建築材料を使用してはならない。
4. アスベスト (規制対象建築材料) が使用されている既存建築物に関する、 増改築等の際における対応
① 原則として、 全ての規制対象建築材料を除去しなければならない。 これは、 厳しい規制であるので、次のb) のような緩和措置が取られている。
②「増改築で、増改築部分が基準時 (平成18年10月1日) における既存建 築物の延床面積の2分の1以下である場合」 には、 増改築部分に規制対象建 材が使われないこと、 増改築以外の部分に規制対象建材がある場合には、 封じ込め若しくは囲い込み (除却も可)が施されること。「大規模修繕・模様替の場合」には、大規模の修繕・模様替部分に、規制 対象建築材料が使われないこと、大規模の修繕・模様替以外の部分に規制対 象建築材料がある場合には、封じ込め若しくは囲い込みの措置(除却も可) が施されること。
5. アスベストとロックウール
アスベスト(石綿) は、 天然に産する鉱物繊維であるのに対し、ロックウー ル (綿) は工場で製造された人造の鉱物繊維で、 石綿の主要な代替品として 使用されているものである。
三. 石綿等以外の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
1. 規制の概要
居室を有する建築物においては、 石綿等以外の物質でその居室内において衛 生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、 建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合することとさ れている。 いわゆるシックハウス症候群対策である。
2. 規制対象物質
シックハウス対策としての規制対象物質は、クロルピリホスとホルムアルデ ヒドの2種類の化学物質である。 クロルピリホスについては、 使用が禁止され、 ホルムアルデヒドについては、 使用建材の発散量に応じて使用禁止、床面積あ たりの使用量の制限、使用量に応じて強制換気させる機械換気設備の設置等が 義務づけられている。ホルムアルデヒドを発散させる建材を使用しない場合でも、家具等からの発 散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられ た。いわゆる24時間換気システムである。
3.クロルピリホスに関する規制
建築材料には、クロルピリホスを添加してはならない。また、クロルピリホ スをあらかじめ添加した建築材料を使用してはならない。ただし、建築物に用 いられた状態で添加後5年以上経過しているものは使用できる。
4. ホルムアルデヒドに関する規制
ホルムアルデヒドは、第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 (毎時 0.12mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定め ある建築材料)、 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 (毎時 0.02mgを超え0.12mg 以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が 定める建築材料)、 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 (毎時 0.005mgを超 え 0.02mg以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料) 3つに分類される。第1種ホルムアルデヒド発散建築材料は、 居室の壁、床及び天井 (天井のな い場合においては、屋根) 並びにこれらの開口部に設ける戸その他の内装(回 り縁 窓台その他これらに類する部分を除く建具の室内に面する部分)の仕上 げに使用することが禁止されているまた、第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発 散建築材料については、第2種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装 の仕上げの部分の面積に一定の数値を乗じて得た面積又は第3種ホルムアル デヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に一定の数値を乗 じて得た面積(居室の内装の仕上げに第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及 び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合 計)が、当該居室の床面積を超えないようにしなければならないとの規制が課されている。なお、ホルムアルデヒドについても、クロルピリホスと同様に、 建築物に用 いられた状態で、 5年以上経過したものは除かれる。
5. 換気設備の設置
居室には、 石綿等以外の物質の発散による衛生上の支障が生じないように、 原則として、一定の基準に適合する構造の換気設備を設けなければならない。
① 有効換気量 (㎡毎時で表した量とする。) が、 一定の式によって計算した 必要有効換気量以上であること。 住宅等の居室の場合、 換気回数として毎時 0.5回以上が必要とされている。
②一の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあっては、当該換気設備の 有効換気量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。
③ ①及び②のほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないよう にするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣 が定めた構造方法を使用するもの。
なお、1年を通じて、 当該居室内の人が通常活動することが想定される空間 のホルムアルデヒドの量を空気1㎡につきおおむね 0.1mg 以下に保つことが できるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、換気設備を 設ける必要はない。
四. 居室に関する規定
1. 天井の高さ
居室の天井の高さは、 2.1m以上でなければならず、 その高さは、 室の床面か ら測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、 その平均の高 さによる。
2. 居室の床の高さ及び防湿方法
最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、 床下 をコンクリート、 たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階 の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、 国土交通大臣の認定を受けたものを除き、 次に定めるところによらなければな らない。
① 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。
②外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm以上の換気孔 を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること
3. 地階における住宅等の居室
住宅の居室 学校の教室、 病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるもの は、壁・床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術 的基準に適合するものとしなければならない。
4. 長屋・共同住宅の各戸の界壁
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほ か、原則として、その構造を遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合 する一定のものとしなければならない。 具体的には、 125Hz では 25dB、500Hz では40dB、 2,000Hz では50dB というように、 振動数が高くなるほど、大きい数値の透過損失が求められているまた、間柱及び胴縁その他の下地 (下地等) を有しない界壁にあっては、 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが 10cm以上のものとされている。また、厚さが10cm 以上の気泡コンクリート の両面に厚さが1.5cm以上のモルタル、プラスター又はしっくいを塗ったもの とされている。
五. 階段・その他
1. 階段
① 直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階又は居室の床面積の 合計が 100㎡を超える地階若しくは地下工作物内におけるものについては、 階段及びその踊場の幅は120cm以上、 けあげの寸法は20cm以下、踏面の寸 法は24cm 以上であることが必要とされている。また、上記に満たない上記に満たない小規模な階段については、階段及び その踊場の幅は75cm 以上、 けあげの寸法は22cm 以下、踏面の寸法は21cm 以上であることが必要とされている。
②回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位 置において測るものとする。
③ 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でそ の高さが50cm以下のもの(「手すり等) が設けられた場合における階段・ その踊場の幅は、 手すり等の幅が10cm を限度として、ないものとみなして 算定する。
④ 踊場の位置及び踏幅高さが4mを超える階段では、 高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない。その階段が直階段である場合、その踊場の踏幅 (踏面に相当) は、 1.2m以上としなけばならない。
⑤階段には、手すりを設けなければならない。 また、 階段及びその踊場の両 側 (手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設 けなければならない。 ただし、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。
⑥ 階段に代わる傾斜路について、勾配は8分の1を超えてはならない。 また、 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げることが必要とされる。
2. 屋上広場等
屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周 囲には、安全上必要な高さが 1.1m以上の手すり壁、 さく又は金網を設けなけ ればならない。
3. 便所
便所は、原則として、 汚水管が公共下水道に連結された水洗便所以外の便所 としてはならない。便所から排出する汚物を公共下水道以外に放流しようとする場合において は、汚物処理性能に関して政令で定める技術的基準に適合する一定のし尿浄化 槽を設けなければならない。また、便所には、 採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければな らない。 ただし、 水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、 その 必要はない。
六. 単体規定における各種設備に関わる規定
1. 給水・排水等の配管設備に共通する構造に関する基準
① コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質 に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。
② 構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造 耐力上支障を生じないようにすること。
③エレベーターの昇降路内に設けないこと。 ただし、地震時においても昇降 機のかごの昇降、かご及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配 管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法 を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
④ 圧力タンク及び給湯設備には有効な安全装置を設けること。
⑤水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない構造とすること。
2. 飲料水の配管設備の設置及び構造に関する基準
① 飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。
②水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備 の水栓の開口部にあっては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との 直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講ずること。
③ 飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土 交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けた ものであることが必要である。
a) 当該配管設備から漏水しないものであること。b) 当該配管設備から溶出する物質によって汚染されないものであること
④ 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措 置を講ずること。
⑤ 給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない 構造とし、金属性のものにあっては、衛生上支障のないように有効なさび止 めのための措置を講ずること。
⑥ 給水配管においてウォーターハンマーが生ずるおそれがある場合におい ては、エアチャンバーを設ける等有効なウォーターハンマー防止のための 置を講ずること。
⑦ 給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点に近接し た部分で、かつ、 操作を容易に行うことができる部分に止水弁を設けること。
3. 給水タンク及び貯水タンクを建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける 場合の構造に関する基準
① 外部から給水タンク又は貯水タンク (以下 「給水タンク等」という。)の 天井、又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設け ること。
② 給水タンク等の天井、底又は周壁は、建築物の他の部分と兼用しないこと。
③内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けないこと。
④ 内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、次に定める構 造としたマンホールを設けること。 ただし、給水タンク等の天井がふたを兼 ねる場合においては、この限りでない。
a) 内部が常時加圧される構造の給水タンク等(以下「圧力タンク等」と いう。)に設ける場合を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らな いように有効に立ち上げること。
b) 直径 60cm 以上の円が内接することができるものとすること。 ただし、 外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な 給水タンク等にあっては、この限りでない。
⑤ ④のほか、水抜管を設ける等内部の保守点検を容易に行うことができる構 造とすること。
⑥ 圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造のオ ーバーフロー管を有効に設けること。
⑦ 最下階の床下その他浸水によりオーバーフロー管から水が逆流するおそ れのある場所に給水タンク等を設置する場合にあっては、 浸水を容易に覚知 することができるよう浸水を検知し警報する装置の設置その他の措置を講 じること。
⑧ 圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通 気のための装置を有効に設けること。 ただし、 有効容量が2㎡未満の給水タ ンク等については、この限りでない。
⑨給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、 空気調和機等の機器を設ける場合 においては、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講ずる こと。
4. 建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造に関する基準
① 排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、 傾斜及び材質を 有すること。
② 配管設備には、排水トラップ、 通気管等を設置する等衛生上必要な措置を 講ずること。
③ 配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有 効に連結すること。
④ 汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。
5. 排水槽の構造
① 通気のための装置以外の部分から臭気が洩れない構造とする。
②内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置にマンホール (直 径60cm以上の円が内接することができるものに限る。)を設けること。 ただ し、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な排 水槽にあっては、この限りでない。
③ 排水槽の底に吸い込みピットを設ける等保守点検がしやすい構造とする こと。
④ 排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かって 1/15 以上1/10 以下とする 等内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる構造とすること。
⑤ 通気のための装置を設け、かつ、当該装置は、直接外気に衛生上有効に開 放すること。
6. 排水トラップの構造に関する基準
① 雨水排水管 (雨水排水立て管を除く。)を汚水排水のための配管設備に連 結する場合においては、当該雨水排水管に排水トラップを設けること。
②二重トラップとならないように設けること。
③排水管内の臭気、 衛生害虫等の移動を有効に防止することができる構造とすること。
④汚水に含まれる汚物等が付着し、又は沈殿しない構造とすること。 ただし、 阻集器を兼ねる排水トラップについては、この限りでない。
⑤封水深は、 5cm以上10cm以下 (阻集器を兼ねる排水トラップについて は5cm以上) とすること。
⑥ 容易に掃除ができる構造とすること。
7. 通気管の構造に関する基準
① 排水トラップの封水部に加わる排水管内の圧力と大気圧との差によって排水トラップが破封しないように有効に設けること。
② 汚水の流入により通気が妨げられないようにすること。
③直接外気に衛生上有効に開放すること。 ただし、配管内の空気が屋内に漏 れることを防止する装置が設けられている場合にあっては、この限りでない。
七. 建築物の防火
1. 指定区域内の屋根の不燃化
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域 内にある建築物の屋根の構造は、 通常の火災を想定した火の粉による建築物の 火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造 及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通 大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものと しなければならない。
2. 外壁
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域 内にある建築物で、 その主要構造部 (床、 屋根および階段を除く) の政令で定 める部分が木材、 プラスチックその他の可燃材料で造られたものは、その外壁 で延焼のおそれのある部分の構造を、 準防火性能に関して政令で定める技術的 基準に適合する土塗壁その他の構造で、 国土交通大臣が定めた構造方法を用い あるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
3. 外壁の構造等
延べ面積が1,000㎡ (同一敷地内の木造建築物等は延べ面積の合計) を超え る木造建築物等は、 外壁 軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋 根を不燃材料で造るか、 葺かなければならない。
4. 建築物の防火壁
延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、耐火建築物準耐火建築物や主要構 造部が不燃材料等で造られた物などを除き、 防火上有効な構造の防火壁又は防 火床によって有効に区画し、かつ、 各区画の床面積の合計をそれぞれ 1,000㎡² 以内としなければならない。
5. 建築物の界壁・間仕切壁・隔壁
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達 せしめなければならない。
第3節 集団規定
一. 建蔽率
1. 建蔽率とは建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことをいい、 火災の際の延焼防止、日照・採光・通風確保などの目的で規制がなされる。
2.建蔽率制限の緩和特定行政庁の指定する角地、防火地域内の耐火建築物等 (建蔽率が10分の 8の地域を除く)、準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等については、建蔽率の規制は、 10分の1緩和される。
3. 建蔽率制限の適用除外①建蔽率が10分の8と定められた地域内で、 防火地域内の耐火建築物等、 ②巡査派出所、公衆便所、 公共用歩廊など、③公園、広場などの内にある建築 物で、安全上 防火上 衛生上支障がないとして、 特定行政庁が建築審査会の 同意を得て許可したものについては、 建蔽率規制は適用されない。
二. 容積率
1. 容積率とは
容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいい、良好な環境 の確保と公共施設の整備とのバランスを保つために規制がなされる。
2. 前面道路の幅員が12m未満である場合の容積率の制限
前面道路 前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。) の幅員 12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、 建築物の所在する地域等の区分に従い、それぞれ一定の数値を乗じたもの以下 でなければならない。
3. 容積率の特例
① 高度利用地区内の規制
高度利用地区内においては、 容積率は、 高度利用地区に関する都市計画に適合するものでなければならない。
②高層住居誘導地区
高層住居誘導地区内の住宅部分の床面積が全体の3分の2以上の建築物 は、都市計画で定める容積率の制限が1.5倍までその住宅割合に応じて緩和される。
③地下室の延べ面積への不算入
建築物の地階で、 その天井が地盤面からの高さ1m以下にある場合、住宅 の用途に供する部分 (共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除 く。)の床面積は、その建築物の住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用 の廊下又は階段の用に供する部分を除く。) の3分の1までは、建築物の延 面積に算入しない。
d) 共同住宅の共用部分の延べ面積への不算入
エレベーターの昇降路の部分、 共同住宅の共用の廊下・階段の用に供する 部分の床面積は、 容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
e) 自動車車庫等の延べ面積への不算入
建築物の容積率の算定の基礎となるべき延べ面積の算定にあたり、自動車 車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に 供する部分の床面積は、原則として、 当該敷地内の建築物の各階の床面積の 合計 (同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、 それらの建築物 の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しないものとされ る。
f) 共同住宅のバルコニーと容積率
外気に有効に開放されている共同住宅のバルコニーについては、その先端 から幅2mまでの部分は、床面積に入れない。
g)宅配ボックスの延べ面積への不算入
建築物の用途や設置場所に関係なく、宅配ボックスの設置部分の床面積は、 敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度として、 容積率の 算定の基礎となる延べ面積に算入しない。