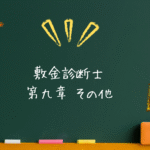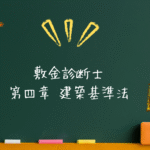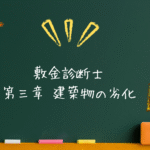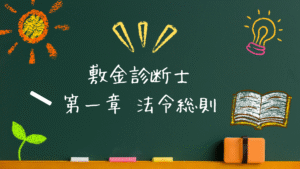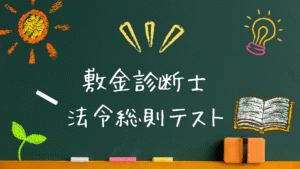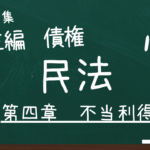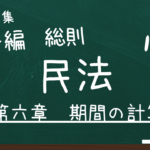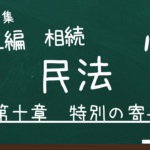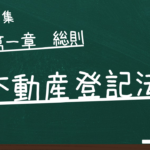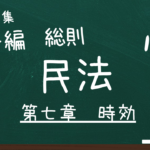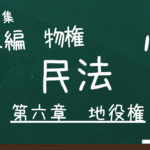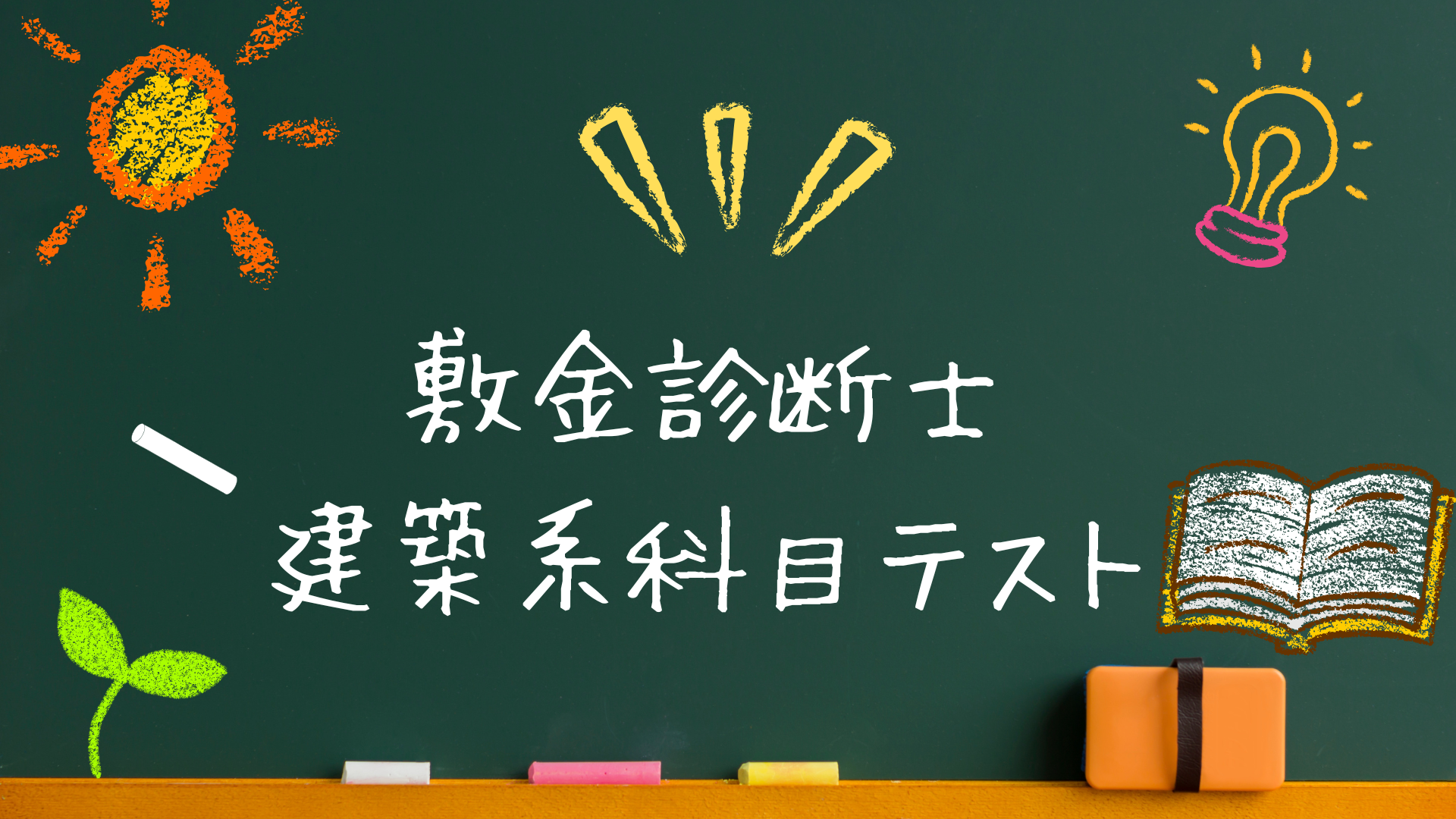
Contents
第1節 建築構造
1. 鉄筋コンクリート造は、部材の圧縮力を鉄筋が負担し、引張力をコンクリートが負担する、 合理的な構造である。
2. 鉄骨構造において、ひふく被覆のない鋼材は500℃以上の熱にさらされる と容易に変形し、強度が半減するため、耐火被覆をする必要がある。
3. 免震構造とは 積層ゴム等の支承を設けて地盤から建物に伝わる地震の振 動を軽減しようとする構造方式である
4. 耐震構造とは、建物自体の剛性を高めて地震に対応する構造方式をいう。
1. × 鉄筋コンクリート造は、部材の引張力を鉄筋が負担し、 圧縮力をコンクリートが 負担する、合理的な構造である。 従って、鉄筋とコンクリートの説明が逆である。
2. ○ 鉄骨構造において、被覆のない鋼材は500℃以上の熱にさらされると容易に変形し、 強度が半減するため、耐火被覆をする必要がある。
3. ○ 免震構造とは 積層ゴム等の支承を設けて地盤から建物に伝わる地震の振動を軽 減しようとする構造方式である。
4. ○ 耐震構造とは、建物自体の剛性を高めて地震に対応する構造方式をいう。
第2節 建築部材
1. 耐震壁とは、ラーメン構造において、 構造計算上、 主として地震力等の鉛 直過重に対して、 有効に応力を負担させるように設計された壁のことをさす。
2. 柱とは、屋根や床の荷重を支え、基礎に伝える役割をもつ鉛直の部材のこ とをいうが、力の分散を図るため、上下階では異なる位置に重なるように配 置するのが通常である。
3. 梁とは、柱の上部で柱と柱を架け渡す水平材のことをいい、 柱に直接連結 している大梁と、柱に直接連結していない小梁とがある。
4. 階段とは、建築物で上下階を移動するための昇降用の通路のことをいい、 階段の段差の寸法を踏面といい、 階段の踏板の有効部分を蹴上という。
1. × 耐震壁とは、ラーメン構造において、 構造計算上、主として地震力等の 「水平」 過重に対して、有効に応力を負担させるように設計された壁のことをさす。 地震の 際に壁にかかる水平力は、 壁を断ち切る力となるので、それに抵抗するものとして のせん断補強筋を有効に配筋する必要がある。
2. × 柱とは、屋根や床の荷重を支え、基礎に伝える役割をもつ鉛直の部材のことをい う。 建築物の隅角部や壁の交わる部分に配置されるが、できるだけ等間隔・規則的 に配置し、上下同じ位置に重なるように配置するのが通常である。
3. ○ 梁とは、柱の上部で柱と柱を架け渡す水平材のことをいい、 柱に直接連結されて いる大梁と、柱に直接連結されていない小梁とがある。 大梁は、通常、 床荷重によ る応力を受けるだけだが、地震時には強い曲げモーメントとせん断力をも受ける。 他方、小梁は、床荷重のみを支持し、 その荷重を大梁に伝える。
4. × 階段とは、建築物で上下階を移動するための昇降用の通路のことをいう。 階段の 路板の有効部分を路面といい、階段の段差の寸法を蹴上という。
第3節 建築材料
1. 建築材料の特徴を比較すると、 圧縮に対する強度については、鉄筋は強いがコンクリートは弱く、じん性 (粘り強さ)については、鉄筋は低いがコン クリートは高い。
2. 建築材料の特徴を比較すると、引っ張る力に対しては、鉄筋は弱いがコン クリートは強く、熱に対しては、鉄筋は強いがコンクリートは弱い。
3. セメントと水を混練すると、発熱して固まる。
4. コンクリートの種類は、骨材等により、 普通コンクリート、 軽量コンクリ ート、 重量コンクリートに分類される。
5. 気泡コンクリートとは、内部に発泡性の断熱材を挟み込んだものである。
6. 水セメント比とは、水とセメントの重量比であり、この値を大きくすると、 コンクリートの耐久性が向上する。
7. 合板とは、木材 紙などの植物質繊維を原料として成形した面材の総称を いう。
8. 繊維板とは、 化学合成した糸状の材を圧縮成形したものである。
1. × 建築材料の特徴を比較すると、 圧縮に対する強度は、 鉄筋コンクリート共に、 強い。ただし、鉄筋は座屈に対して弱い。 じん性 (粘り強さ)は、鉄筋は高いがコ ンクリートは低い。
2. × 引っ張る力に対しては、コンクリートは弱いが鉄筋は強く、熱に対しては、コン クリートは強いが鉄筋は弱い。 従って、鉄筋とコンクリートの「引っ張る力」 と 「耐 「熱性」についての説明が、 ともに逆になっている。
3. ○ セメントと水を混練すると、 発熱して固まる。 なお、この場合の熱のことを水和 熱といい、固まる性質のことを水硬性という。
4. ○ コンクリートの種類は、 骨材等より、普通コンクリート (骨材として川砂、川砂 利、砕石等を使用)、 軽量コンクリート (骨材として天然軽量骨材、 人工軽量骨材を 使用)、 重量コンクリート (骨材として鉄粉、 磁鉄鉱等を使用) に分類される。
5. × 気泡コンクリートとは、内部に多量の小気泡を含ませて作った多孔質のコンクリ ートである。 発泡性の断熱材を挟み込むものではない。
6.× 水セメント比とは、 水とセメントの重量比であり、 この値を大きくすると (水量 を大きくすると)、コンクリートの耐久性が低下する。
7. × 合板とは、ラワン材を主材とした厚さ1~3mmの単板を繊維方向を交互に直交す るように重ね接着した板状の材料をいう。 単板に比べて温度による狂いや膨張収縮 の方向性が少ないという利点がある。 なお、本肢は、 「繊維板 (ファイバーボード)」 についての説明である。
8. × 繊維板とは、 植物繊維を主な原料として作った板材料の総称である。
第4節 防水
1. 露出アスファルト防水とは、アスファルトルーフィングを溶融アスファル トによって一体化する防水である。
2. 歩行用の屋上には、防水層の上にコンクリートを打設し、 伸縮目地を設け ることがある。
3. シート防水とは、液状ウレタンを塗り重ね、 トップコートを塗ったもので ある。
4. ウレタン系シーリングは、性能 価格的に最も標準的であるが、紫外線に 弱い。
1. ○ 露出アスファルト防水とは、アスファルトルーフィングを2~3層、溶融アスプ ァルトによって一体化する防水である。
2. ○ 歩行用の屋上には、アスファルト防水の上にコンクリートを10cmほど打設し、 伸縮目地を設けることがある。
3. × シート防水は、一層のシートを接着剤等で張り付けるものである。 設問は、塗膜 防水の説明である。
4. ○ ウレタン系シーリングは、性能・価格的に最も標準的であり、紫外線に弱い。
第二章設備
第1節 給水・給湯設備
1. 給水方式の一つである水道直結方式は、増圧給水設備 (ポンプ)を経て各 住戸に給水する方式である。
2. 給水方式につき、 受水槽方式を採用した場合、 停電時における給水は不可 能である。
3. 水道直結給水方式においては、ポンプを用いる事によって、 断水時の給水 が可能となる。
4. 水道水を給水する管とその他の目的の管が直接連結される事をクロスコ ネクションといい、 上水道配管中に不純な水が混入する恐れがあるため、 禁 止される。
5. ウォーターハンマーとは配管内の水の流れに対する、 急激な圧力変動によ る騒音・振動現象で、 水撃作用ともいわれ、 主に水栓や弁などを急激に開い たときに生ずる。
6. 高度の赤水が発生した場合の対処方法として、 防錆剤 (腐食抑制剤)の使 用により、 腐食を防止するのが効果的である。
7. ライニング更正工事とは、 防錆などを目的として、 タンクや管などの内側 壁を耐熱材、耐薬品材などで被覆する工事を指す。
1. × 水道直結方式は、水道本管からの水を各住戸に直接給水する方式であるため、増 圧給水設備 (ポンプ)は不要である。なお、本管直結式で増圧給水設備を用いるも のは、 増圧直結給水方式といわれる。
2. × 受水槽方式 (高置 (高架) 水槽方式、 ポンプ直送方式、 圧力タンク方式)におい しては、発電機を設置すれば、 停電時の給水が可能となる。 又、高置水槽方式では、 高置水槽に元々貯水されているものは、 給水可能である。
3. × 水道直結給水方式には、受水槽がないため (水槽内に残っている水量を使用する ことができない)、 断水時の給水は不可能であり、ポンプを用いる事による効果は無い。
4. ○ クロスコネクションとは水道水を給水する管とその他の目的の管が直接連結され る事を指し、 上水道配管中に不純な水が混入する恐れがあるため、 禁止される。
5. × ウォーターハンマーとは配管内の水の流れに対する、 急激な圧力変動による騒 音・振動現象で、 水撃作用ともいわれ、 主に水栓や弁などを急激に閉じたときに生 ずる。 なお、 急激に開いたときに生ずることもある。
6. × 高度の赤水が発生した場合の対処方法として、 給水管の設備替えをするのが最適 である。 なお、 「軽度・中度の赤水」 の場合は、 防錆剤 (腐食抑制剤) の使用により、 腐食を防止するのが効果的である。
7. ○ ライニング更正工事とは、 防錆などを目的として、タンクや管などの内側壁を耐 熱材、耐薬品材などで被覆する工事を指す。
第2節 排水・通気設備
1. 排水は、汚水 雑排水、雨水の3つに分類され、洗面所からの排水は汚水にあたる。
2. トラップとは、排水管を曲げるなどして水(封水)を溜める部分のことで あり 排水管内の臭気や害虫が室内に侵入することを防ぐものである。
3. 合流式の排水方式は、敷地内において雑排水と雨水を同一の系統で排水する方式である。
4. 通気管の主な機能は、 トラップの封水を保持したり、排水の流れが円滑に行われるようにすることである。
1. × 排水は、汚水 雑排水、雨水の3つに分類され、洗面所からの排水は雑排水にあ たる。 汚水にあたるのはトイレからのし尿であり、 洗面や台所からの排水は雑排水にある
2. ○ トラップとは、 排水管を曲げるなどして水 (封水) を溜める部分のことであり、 排水管内の臭気や害虫が室内に侵入することを防ぐものである。
3. × 合流式の排水方式は、 敷地内において汚水と雑排水を同一の系統で排水する方式 である。
4. ○ 通気管の主な機能は、 ① 排水管系統内の換気を行い、②サイフォン作用や背圧によるトラップの封水切れを防止し、 ③ 排水管内外の気圧差をできるだけ生じさせな いようにして、 排水の流れを円滑にすることにある。
第3節 換気・冷暖房設備
1. 第三種機械換気方式とは、 給気を機械で行い、 排気を自然に行う方式をい い、具体例として、 住戸内のトイレが挙げられる。
2. 換気が有効に行われるためには給気が重要であり、 給気の確保が不十分で あると、 換気扇の能力をいくら大きくしても必要換気量を確保することはで きない。
3. マンションに採用されている冷暖房設備の方式は、一般的に、 住棟セント ラル方式、 住戸セントラル方式、 個別方式の3つに分類される。
1. × 第三種機械換気方式とは、 排気を機械で行い、 給気を自然に行う方式をいい、 具 体例として、 住戸内のトイレが挙げられる。
2. ○ 換気が有効に行われるためには、 給気が重要である。 給気の確保が不十分である と換気扇の能力をいくら大きくしても必要換気量を確保することはできない。
3. ○ マンションに採用されている冷暖房設備の方式は、一般的に、空調管理室を経て 各住戸に供給する住棟セントラル方式、 住戸ごとに熱源を設ける住戸セントラル方 式、必要な部屋ごとに冷暖房設備を設ける個別方式の3つに分類される。
4節 電気・ガス設備
1. 建物への電力の引き込みは、 供給電圧によって 「低圧引き込み」 「中圧引き込み」 「高圧引き込み」 の3種類に分類される。
2. 借室変電設備とは、 電力会社が建物敷地内に必要なスペースを一般に有償 で借りて、高圧から低圧に電圧を変換して各住戸に供給するために設置する 変電設備のことである。
1. × 建物への電力の引き込みは、 供給電圧によって 「低圧引き込み」 「高圧引き込み」 「特別高圧引き込み」 の3種類に分類される。
2. × 借室変電設備とは、 電力会社が建物敷地内に必要なスペースを一般に無償で借り て、高圧から低圧に電圧を変換して各住戸に供給するために設置する変電設備のことである。
第5節 消防設備
1. 消防用設備等に対する点検は、全て1年に1回行うものとされている。
2. 消防用設備等の点検は、 消防設備士免状の交付を受けている者であれば誰 でも行うことができる。
3. 消防長又は消防署長は、 消防用設備等が設備等技術基準に従って設置又は 維持されていない防火対象物の管理権原者に対して、必要な措置を講じるよ う命じることができる。
1. × 消防用設備等に対する点検は、1年に1回行うものと6ヵ月に1回行わなければならないものがある (消防法17条の3の3、 施行規則31条の6)。
2. × 消防用設備等の点検は、 消防設備士免状の交付を受けている者等で一定の講習機 関において必要な知識及び技能を修得した者 (消防設備点検資格者)が行わなけれ ばならない(消防法施行規則 31 条の6第6項)。 従って、 消防設備士免状を有する だけでは足りない。
3. ○ 消防長又は消防署長は、 消防用設備等が設備等技術基準に従って設置又は維持さ れていない防火対象物の管理権原者に対して、 必要な措置を講じるよう命じること ができる (消防法17条の4)。
第三章 建築物の劣化
第1節 建築物の劣化
1. 物理的劣化とは、建物等が建設されてから一定の年数の経過に伴う化学 的要因及び物理的要因等によって、使用材料や機器が劣化することをいう。
2. 機能的劣化とは、建物等が、 高度情報化、 現代社会の傾向、ライフスタイ ル等の変化などでの新たな要求に対応できないことによる劣化をいう。
3. 社会的劣化とは、建設後の技術の向上により、 建設時よりも優れた性能の 設備機器、 材料が開発され、その結果建設当初設置された機器等の性能が劣 化していなくとも、相対的な評価としてその機器等が陳腐化することにより 建物が劣化する場合をいう。
4. 水が部材内部及び部材間の間隙部分を通して漏出する現象を漏水という が、ここでいう間隙部分とは、 まめ板やポップアウトのことをいう。
5. 硬化したコンクリートの表面に染み出した白色の物質は、エフロレッセン スと呼ばれる。
6. コンクリートのクラック幅は、 クラックスケールをクラックに挿入して測 定する。
7. 打撃法は、各種のハンマーを用いてコンクリートの表面に打撃を与えるこ とによって、表面のくぼみの直径やはね返りの高さ (反発硬度)を測定して コンクリート強度を推定する方法であり、 局部破壊検査法の一つである。
1. ○ 建物等は建設されてから一定の年数を経ると、雨水、空気中の炭酸ガス等の化学的要因及び継続使用による減耗などの物理的要因等によって、使用材料、機器の劣 化が始まり、さらに経年とともに劣化範囲の拡大、 劣化程度も進行していく。 この ことを建物等の物理的劣化という。このため、劣化が建物全体に及ぶと、大規模な 修繕を実施する必要がある。
2. × 機能的劣化とは、 建設後の技術の向上によって、 建設時よりも優れた性能や、よ りコンパクトな設備機器、材料が開発され、 その結果当初設置された機器等の性能 が劣化していなくとも、 相対的な評価としてその機器等が陳腐化する場合をいう。 本肢は、 「社会的劣化」についての説明である。
3. × 社会的劣化とは、 建物等については、 高度情報化、多様化あるいは潤いを求める 現代社会の変化に対応して、住居に要求する内容も変貌しており、 部屋構成の変化、 住戸面積の増大、建物の外観の高級化等が求められているが、これらに対応できな いことにより生ずる劣化をいう。 本肢は、「機能的劣化」についての説明である。
4. × 漏水の生じる部材内部及び部材間の間隙部分とは、 まめ板、 コールドジョイント などをさすが、 ポップアウトは、単なる表面劣化である。
5. ○ コンクリートの表面に染み出た白色の汚れは、エフロレッセンスと呼ばれる。 セ メント中の石灰などが水に溶け、空気中の炭酸ガスと化合したものが主成分である。
6. × コンクリートのクラック幅は、 クラックスケールをコンクリート表面に接して置 き、クラックの幅を測定する。
7. × 打撃法は、各種のハンマーを用いてコンクリートの表面に打撃を与えることによ って、表面のくぼみの直径やはね返りの高さ (反発硬度)を測定してコンクリート 強度を推定する方法であり、純非破壊検査法の一つである。
第四章建築基準法
第1節 総論
1. 「建築設備」とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、 換気、 暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、 昇降機若しくは避雷針 をいう。
2. 建築基準法における「大規模の修繕」 とは、 建築物の主要構造部の2種以 上について行う過半の修繕をいう。
1. ○ 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消 火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、 昇降機若しくは避雷針をいう(建基法 2条3号)。
2. × 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の 「1種以上」について行う過半の修繕 をいう(建基法2条14号)。
第2節 単体規定
1. 共同住宅の居室においては、 窓や開口部の換気に有効な面積を、その居室 の床面積の1/7 以上、 確保しなければならない。
2. 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、 その換気に有効な部分の 面積は、その居室の床面積に対して、50分の1以上としなければならない が、一定の技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限り でない。
3. 共同住宅の調理室に、 火を使用するこんろを設けた場合、 一定の換気設備 を設けなければならない。
4. 共同住宅の居室内におけるシックハウス対策において、 保温材及び断熱材 以外の建築材料に含まれるホルムアルデヒドがその対象の化学物質である。
5. 受水槽における保守点検及び清掃のためのスペースは、 全面において少な くとも60cmは必要である。
1. × 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、 その換気に有効な面積は、その 居室の床面積に対して、 1/20 以上としなければならない (建基法28条2項)。 よっ て、本肢は誤り。 なお、 1/7 としなければならないのは、 採光に有効な面積の確保に ついてである。
2. × 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、 その換気に有効な部分の面積は、 その居室の床面積に対して 20 分の1以上としなければならない。 ただし、 一定の 技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない (建基法 28 条2項)。
3. ○ 建築物の調理室で、 かまど、 こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設け たものには、原則として、政令で定める換気設備を設けなければならない (建基法 28条3項)。
4. × 共同住宅の居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置 いわゆるシッ クハウス対策において、保温材及び断熱材を 「含む」 建築材料に含まれるホルムア ルデヒドがその対象の化学物質である (建基法28条の2)。
5. × 受水槽における保守点検及び清掃のためのスペースは、上部が100cm、 その他の部 分では60cm以上設けるのが適切とされる。
第3節 集団規定
1. 建蔽率とは、 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
2. 容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことをいう。
3. 建蔽率が10分の8と定められた地域内で、防火地域内の耐火建築物につ いては、建蔽率規制は適用されない。
4. 特定行政庁の指定する角地及び防火地域内の耐火建築物の場合 (建蔽率が 10分の8の地域を除く) については、建蔽率の規制は、10分の2緩和され る。
5. 前面道路 (前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅 員が 12m未満である建築物の容積率は、 当該前面道路の幅員のメートルの 数値に、 建築物の所在する地域等の区分に従い、 それぞれ一定の数値を乗じ たもの以上でなければならない。
6. 高度利用地区内においては、 容積率は、 高度利用地区に関する都市計画に 適合するものでなければならない。
7. 高層住居誘導地区内の住宅部分の床面積が全体の3分の2以上の建築物 は、都市計画で定める容積率の制限が1.5倍までその住宅割合に応じて緩和 される。
1. × 建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことをいい、火災の際 この延焼防止、日照 採光・通風確保などの目的で規制がなされる。
2. × 容積率とは、 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいい、良好な環境の確 保と公共施設の整備とのバランスを保つために規制がなされる。
3. ○ ① 建蔽率が10分の8と定められた地域内で防火地域内の耐火建築物、 ②巡査派出 所、 公衆便所、 公共用歩廊など、 ③公園、広場などの内にある建築物で安全上・防 火上 衛生上支障がないとして特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの、 については、 建蔽率規制は適用されない。
4. ○ 特定行政庁の指定する角地及び防火地域内の耐火建築物の場合 (建蔽率が10分の 8の地域を除く) については、建蔽率の規制は、10分の2緩和される。
5. × 前面道路 (前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が 12 m未満である建築物の容積率は、 当該前面道路の幅員のメートルの数値に、 建築物 の所在する地域等の区分に従い、 それぞれ一定の数値を乗じたもの 「以下」でなけ ればならない。
6. ○ 高度利用地区内においては、 容積率は、 高度利用地区に関する都市計画に適合す るものでなければならない。
7. ○ 高層住居誘導地区内の住宅部分の床面積が全体の3分の2以上の建築物は、 都市 計画で定める容積率の制限が1.5倍までその住宅割合に応じて緩和される。