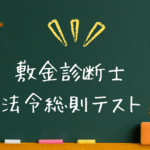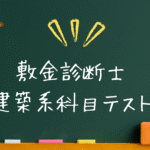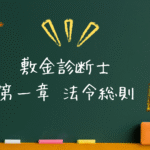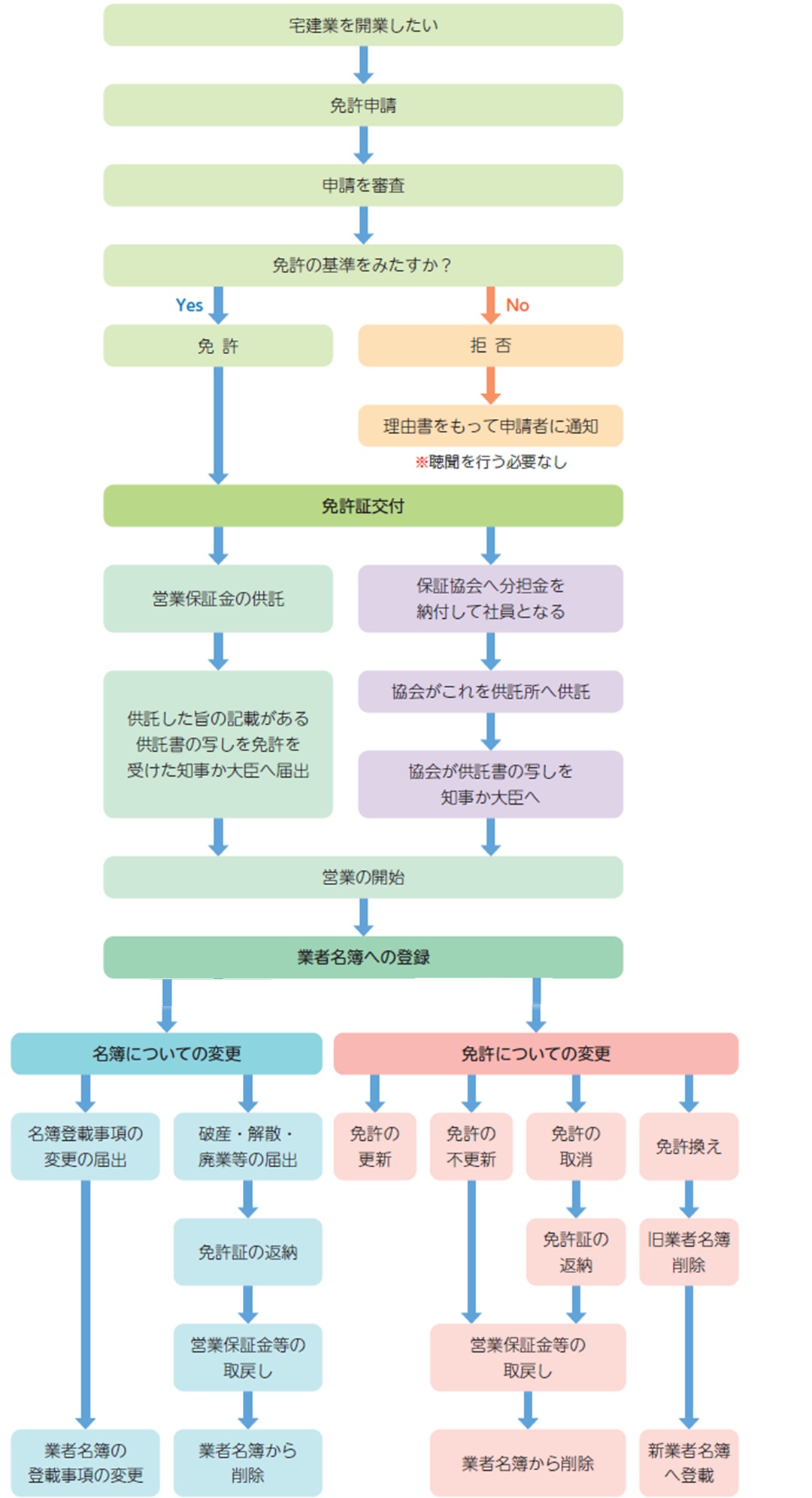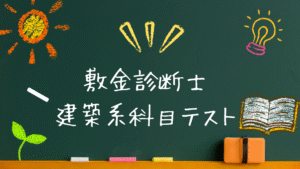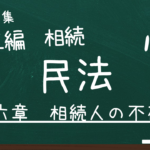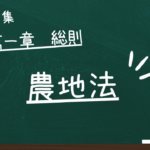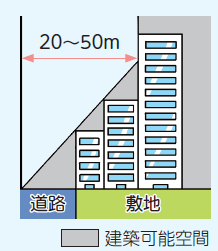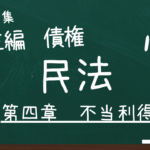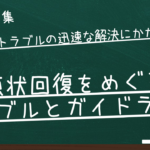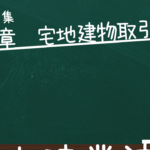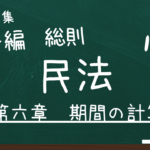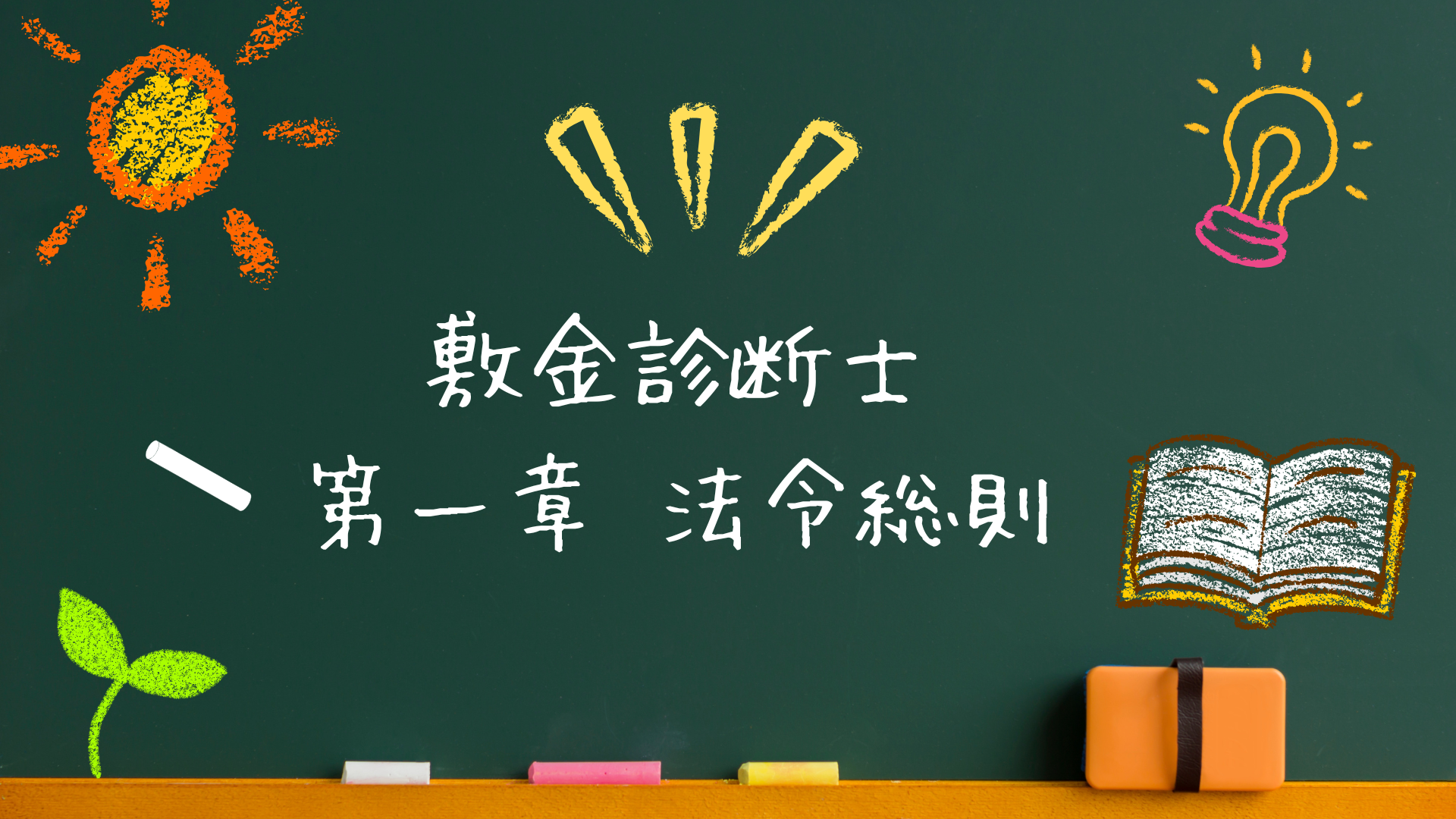
第1節 民法(総則)
一 序論
1. 民法の意義
民法は、 私法の一般法であり、 私法の大原則となる。
① 公法 私法「公法」 は、 憲法や刑法のように、国と国民との関係を定めた法のことであ り、命令服従をその指導原理とする。 一方、 「私法」 は、 民法や商法のように、 国民と国民との関係を定めた法のことであり、 自由平等をその指導原理とする。
②一般法・特別法「一般法」 は、 民法のように、一般の人に、 一般的場面において適用される 法のことをいい、 「特別法」 とは、 商法などのように、 特別な立場の人や事柄 に対してのみ適用される法のことをいう。一般法と特別法の規定内容が抵触する場合、 特別法が一般法に優先する。
2. 民法の基本原則
① 所有権絶対の原則則。
所有権は他人はもとより、 国家権力といえども侵すことはできないという原則
②私的自治の原則則。
私的な法律関係については、 自分の自由意志に基づいて形成しうるという原則
③ 過失責任の原則
過失がなければ責任を負わされることもないという原則。
3. 民法上の権利
① 内容による分類
財產権 経済的価値を有する権利 物権・債権・無体財産権
非財產権 経済的価値を有しない権利 人格権・身分権
② 作用による分類
支配権 権利者の意思だけで権利内容 を実現することができる権利 物権・無体財産権・人格権
請求権 他人に一定の行為を要求する ことのできる権利 債権・物上請求権
形成権 一方的意思表示によって法律 関係の変動を生じる権利 取消権・解除権・売買の予約権
抗弁権 他人の権利行使を妨げる権利 同時履行の抗弁権・催告の抗弁権・検索の抗弁権
管理権 財産的事務の処理を行う権利 不在者の財産管理人の管理権・相続財産管理人の管理権
二 信義誠実の原則 (信義則)
「信義誠実の原則 (信義則)」 とは、 ある具体的事情の下において、 相互に相手方 の信頼を害さないように誠意をもって行動すべきであるという原則である。 信義則 は、法律行為の解釈の基準となり、 また。 社会的接触関係に立つ者の規範関係を具 体化し、法律に規定のない部分を補充する機能を有している。信義則から派生する代表的な原則として次のものがある。
禁反言の法則 自己の行為に矛盾した態度をとることは許されない。
クリーンハンズ の原則 自ら不法に関与したものには法の救済を与えない。
事情変更の法則 社会的事情に変化があれば、 契約内容はそれに応じて 変更されなければならない。
権利失効の原則 権利者が信義に反して長期間権利を行使しない場合、 権利の行使が阻止される。
三 制限行為能力者
制限行為能力者とは、自らの行為の結果を判断する能力に欠けるか、又はその能 力が十分ではないために、単独で確定的に有効な法律行為をなしえないと認められ た者のことをいう。
1. 制限行為能力者の種類
① 未成年者
未成年者とは、満20歳未満の者 (2022年4月1日からは満18歳未満の者) をいう。ただし、未成年者でも、婚姻をした場合は、 成年に達したものとみな される。これを成年擬制という。
②成年後見人
成年被後見人とは、 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあ る者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者をいう。
③ 被保佐人
被保佐人とは、 精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分で ある者で、 家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者をいう。
④被補助人
被補助人とは、 精神上の障害により、 事理を弁識する能力が不十分である者 で、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者をいう。
2. 制限行為能力者の保護
制限行為能力者が、単独で結んだ一定の契約は取り消すことができるとした。 制限行為能力者に対して保護者を付け (未成年者には、 「親権者 未成年者後見 「人」、 成年被後見人には、 「成年後見人」 被保佐人には、 「保佐人」、 被補助人には、 「補助人」)、 その保護監督にあたらせることとした。
3. 取消の範囲
① 未成年者
法定代理人の同意を得ずに、 未成年者が単独でなした行為は、原則として取 り消すことができる。 ただし、以下の行為は、単独で行った場合でも、取り消せない。
a.単に権利を得、又は義務を免れる行為
b. 処分を許された財産の処分
c. 営業の許可を得た場合の営業上の行為
d. 法定代理人の同意を得て行った行為
② 成年被後見人
単独でなした行為は、原則として取り消すことができる。 しかし、日用品の 購入その他日常生活に関する行為は、単独で行った場合でも取り消すことができない。
③ 被保佐人
単独でなした行為は、原則として取り消すことができない。 ただし、 保佐人 の同意を得ないで以下の重要な行為を行った場合には、その行為は取り消すこ とができる。
a. 元本を領収し、 又は利用すること
b. 借金をし、 保証をすること
c. 不動産又は重要な財産の売買等
d. 訴訟行為
e. 贈与 和解・仲裁契約をすること
f. 相続の承認・放棄又は遺産分割すること
g. 贈与 遺贈の拒絶をし、 又は負担付き贈与 遺贈を受諾すること
h. 新築・増改築 大修繕をすること.
i 一定の期間を超える賃貸借契約をすること (宅地は5年、 建物は3年)
j. 上記aiに掲げる行為を制限行為能力者 (未成年者、 成年被後見人、 被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。)の法定 代理人としてすること
④ 被補助人単独でなした行為は、原則として取り消すことができない。 ただし、 家庭裁 判所が③に掲げるajの行為の中で特に定めた重要な行為について、補助人 の同意を得ないで行った場合、取り消すことができる。
4. 相手方の保護の制度
制限行為能力者がした行為は、一応有効であるが、 取り消される可能性があるの で、取引の相手方は不安定な立場におかれる。 そこで、取引の相手方を保護するた め、以下のような規定が定められている。
① 催告権
制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者となった場合(未成年者が成年になった後や、制限行為能力者が能力を回復したときなど)、1 カ月以上の期間を定めて、その法律行為を追認するか否かを確答するように催 告することができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しな いときは、その行為を追認したものとみなす。
②取消権の喪失
制限行為能力者が、自分が行為能力者であると信じさせるため詐術を用いた 場合には、取消権を行使できなくなる。
③ 法定追認
制限行為能力者が追認をできるようになった後 (未成年者が成年になった後 や、制限行為能力者が能力を回復したときなど) に、 以下の行為をした場合に は、原則として、 法律上当然に追認したものとみなされる。
a) 全部又は一部の履行
b) 履行の請求
c) 更改
d) 担保の供与
e) 取消しできる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
f) 強制執行
④まる取消権の消滅取消権は、 追認をすることができるときから5年間行使しない場合は時効に より消滅する。 また、 行為のときから20年を経過した場合も消滅する (除斥期間)
四 意思表示
意思表示とは、一定の法律効果発生の意思を外部に対して表示する行為をいう。
1. 無効にかかる制度
① 心裡留保
心裡留保とは、表意者が真意でないと知りながらする意思表示のことをいう。 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであってもそ のためにその効力を妨げられない。 ただし、 相手方がその意思表示が表意者の 真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無 効となる。なお、上記意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
② (通謀) 虚偽表示
虚偽表示とは、相手方と通じてした虚偽の意思表示のことをいう。 虚偽表示 による意思表示は、当事者間では、 無効である。 ただし、虚偽の意思表示につ いて、虚偽であることを知らなかった第三者(=善意の第三者) に対しては、 意思表示の無効を対抗 (=主張) することはできない。
2. 取消しにかかる制度
①錯誤
錯誤による意思表示とは、 表示行為から推測される意思表示上の効果意思) と表意者の真意との間にくい違いがあるのに、 表意者がそのくい違いに気づか ずにした意思表示のことをいう。錯誤には、 ① 動機の錯誤と②表示行為の錯誤の2種類のものがあり、 ①動機 の錯誤とは、 建築できない土地を建築可能と思って購入する意思を表示した場 合など、 ある意思表示をするまでの動機 (過程) の部分に勘違いがあるものを いう。 他方、②表示行為の錯誤とは、売買代金の言い間違いや目的物の取り違 えなど、 ある意思決定がなされてから、それを外部に表示するまでの間に勘違 いが生じたものをい意思表示は、次の①又は②に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が 法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取 り消すことができる。 ただし、②の動機の錯誤を前提とする意思表示の取消し は、 その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限ら れる。
① 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 (表示行為の錯誤)
② 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する 錯誤 (動機の錯誤)
この点、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、原則とし て、 錯誤による意思表示の取消しをすることはできない。 もっとも、例外とし て、次のa) b) のいずれかの場合は、 錯誤による意思表示の取消しをする ことができる。
a) 相手方が表意者に錯誤があることを知り、 又は重大な過失によって知ら なかったとき (相手方の悪意又は重過失 )
b) 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき (共通錯誤 )
なお、錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
② 詐欺による意思表示
詐欺による契約は取り消すことができる。 詐欺による取消しは、a)取消し 前の第三者が詐欺の事実を知っている(悪意)か、知らないことに落ち度があ (善意だが有過失) 場合には、当該第三者に対抗できるが、 b) 取消し前の 第三者が詐欺の事実を知らず、 知らないことに落ち度もない (善意かつ無過失) 場合には、当該第三者に対抗できない。なお、 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合には、相 手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、 その意思表示を取 り消すことができる。
3 強迫による意思表示
強迫による契約は取り消すことができる。 強迫による取消しは、取消し前に 現れた善意 無過失の第三者にも対抗できる。
五 代理
代理とは、 代理人が、 本人に代わって法律行為をし、 それによって本人が直接に 法律効果を取得する制度をいう。 代理人は、 行為能力者である必要はない。 つまり、 未成年者などの制限行為能力者でもよい。
1. 代理の要件
① 有効な代理権を有すること
②代理人が、本人のためにする意思 (代理意思) を明らかにすること (顕名)
③ 代理行為をしたこと
2. 顕名を忘れた場合
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として、 自己 のためにしたもの、つまり、契約は、代理人自身と相手方との間で締結されたこと になる。 しかし、相手方が、 代理意思を有していることを知っているか、又は知ら なかったことに過失がある場合には、本人に効果が帰属する。
3.復代理
復代理とは、代理人が、その権限内の行為をさせるために、さらに代理人(復代 理人を選任することをいう。 復代理人の行った行為の効果は、直接本人に及ぶ。 なぜならば、復代理人は、あくまで本人の代理人であるからである。代理人が復代理人を選任しても、代理人の代理権は消滅しない。 そして複代理 人の代理権の範囲は代理人の代理権の範囲を超えることができず、 また、 代理人の 代理権が消滅した場合には復代理人の代理権も消滅する。
4. 自己契約・双方代理
自己契約とは、 代理人自身が契約の相手方になることをいい、双方代理とは、当 事者双方の代理人になることをいう。自己契約と双方代理は、 代理権を有しない者がした行為 (=無権代理行為) とみ なされる。もっとも、 本人保護の目的で禁止しているため、 ①本人に不利益が生ず るおそれのない単なる債務の履行や、 ② 本人があらかじめ許諾した行為は、禁止さ れない。
5. 無権代理
無権代理とは、代理権がないにもかかわらず、代理人と称してなされた行為のこ とをいう。 無権代理行為は、原則として無効であり、 本人には契約の効果が帰属し ない。ただし、 本人の追認があれば、 代理行為の時点 (契約の時点) から有効な代 理となり、 本人に効果が帰属する。一方、この場合の相手方保護の制度として以下のものがある。
① 催告権
無権代理行為の相手方は、 一定の期間を定めて、 本人に対して、 追認するか どうかの確答を促すことができる (催告権)。 この催告権は、 無権代理行為に つき悪意の相手方でも行使できる。 そして、 催告に対して確答がない場合、追 認拒絶とみなされ、 無権代理行為は無効に確定する。
② 取消権
無権代理行為は、本人が追認するまでの間は、 無権代理行為につき善意の相 手方が取り消すことができる。
③ 無権代理人に対する責任追及
他人の代理人として契約をした者は、次表のとおり、相手方の選択に従い、 相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。無権代理人への責任追及は、基本的に、無権代理であることについて相手方 「善意無過失」 の場合にすることができる。しかし、無権代理人が自らに代理権がないことを知っていた場合は、無権代 理であることについて相手方に過失があったとしても、相手方を保護する必要 性があるため、相手方は無権代理人の責任を追及することができる。
相手方善意無過失善意有過失惡意善意O×無權代理人惡意O×○=無権代理人の責任追及 「可」 x=無権代理人の責任追及 「不可」
④表見代理
表見代理とは、 無権代理行為であっても、一定の要件を充たす場合に、 有効 な代理行為があったものと扱い、 本人に対して効果を帰属させる制度をいう。
<成立要件>
a. 代理権があるような外観の存在
b. 外観が存在することについて本人の帰責性
c. 相手方の信頼 (無権代理であることにつき善意 無過失)
<表見代理の類型>
a. 代理権授与表示による表見代理
代理権を与えていないにもかかわらず、 代理人として行為した者に対し代理権を与えた旨を、 相手方に表示する場合
b. 権限喩越の表見代理
代理人が、 元々の代理権の範囲を超えて、 相手方と代理行為をする場合
c. 代理権消滅後の表見代理
以前に代理権を与えられ、その代理権が消滅しているにもかかわらず、代理行為を行う場合
六 時効
時効とは、事実状態が一定の期間継続することによって、これまで持っていなか った権利を取得したり、これまで存在していた権利が消滅したりすることを認める 制度をいう。
1. 取得時効
取得時効とは、権利者らしい状態が一定の期間継続することによって、これまで 持っていなかった権利を取得することをいう。 取得時効の対象となる権利としては、 所有権及び所有権以外の財産権 (地上権・永小作権・地役権・賃借権など) がある。
<要件>
所有の意思をもって、 平穏公然に占有すること
占有開始時に、善意無過失であれば 10年間占有を継続すること
占有開始時に、 悪意又は有過失であれば20年間占有を継続すること
2. 消滅時効
消滅時効とは、事実状態が一定の期間継続することによって、これまで存在して いた権利が消滅することをいう。 この「一定の期間」 の数えはじめの時点を 「起算 点」 といい、 経過が必要な期間を 「時効期間」という。
<消滅時効の期間>
種類起算点時効期間債権者が権利を行使できることを知った時 から (=主観的起算点)5年一般の債権権利を行使することができる時から (=客観 的起算点)10年債権・所有権 「以 「外」の財産権権利を行使することができる時から (=客観 的起算点)20年不法行為による損害賠償請求権被害者またはその法定代理人が損害および 加害者を知った時から (=主観的起算点)3年(人の生命・身体以外)不法行為の時から (=客観的起算点)20年
人の生命・身体の債権者が権利を行使できることを知った時から (=主観的起算点)5年侵害による損害 賠償請求權権利を行使することができる時から (=客観 的起算点)20年判決等の確定のときから判決等で確定した権利※確定時に弁済期の到来している債権に 限る。10年
3. 時効の援用・放棄
時効の援用とは、時効による利益を受ける旨を当事者が主張することをいう。 時 効には、継続した事実状態を尊重する結果、真実に反して権利を取得したり、義務 を免れたりする側面もあるため、 ①時効に必要な期間の経過 (時効の完成) に加え、 ②当事者の時効の援用があってはじめて、 時効の効果が生ずるものとされている。 時効を援用することができるのは、債務者や連帯債務者といった「当事者」であ る。 消滅時効にあっては、保証人、 物上保証人、 第三取得者その他権利の消滅につ いて正当な利益を有する者もこれに含まれる。なお、時効によって利益を受ける者 (債務者)は、その利益を放棄することもで きるが、時効が完成する前にあらかじめ時効の利益を放棄することは、債権者によ る濫用のおそれがあるので許されない。 一方、 時効完成後に、 債務者が気付かない で弁済をしてしまった場合、債務者は信義則上、 時効の援用をすることはできない。 また、 時効の効力 (権利の得喪) は、 時効期間の最初にさかのぼる。 これを時効 の遡及効という。
4. 時効の完成猶予・時効の更新等
時効の完成猶予とは,所定の事実 (=完成猶予事由) が認められた場合に,一定 期間 (=その事実が終わるまでの間), 時効が完成しないという制度である。 他方、 時効の更新とは、所定の事実 (更新事由) が認められた場合に, 時効完成に向か っている時計の針をゼロに巻き戻して, 改めて時効期間を進行させるという制度で ある。
主な時効の完成猶予事由 時効の更新事由は,次のとおり。
Da主な完成猶予事由主な更新事由① 裁判上の請求等① 裁判上の請求等強制執行等(2)強制執行等仮差押え 仮処分承認④ 催告(5協議を行う旨の合意天災等
5. 時効完成後の債務の承認等
時効が完成した後に債務の承認や弁済等をした債務者は, 改めて時効の援用をすることはできない。
第2節 消費者契約法
一 序論
1. 消費者契約法の目的
消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者 の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又は その承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠 償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の 全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生 活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された。
2.消費者契約法上の用語の定義
消費者契約法は、 消費者と事業者との契約 (=消費者契約) を規律し、 「消費者」 を保護するための法律である。 したがって、 消費者同士の契約や、 事業者同士の契 約は、消費者契約には該当しない。 用語の定義は、次のとおりである。
① 消費者
消費者とは、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く個人をいう。
②事業者
法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
③ 消費者契約
消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
二 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
1. 取消事由
事業者が次のような不当な勧誘行為をしたことで消費者が誤認困惑して契約 の申込み 承諾の意思表示をした場合、 消費者は、当該契約を取り消すことがで きる。 また、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者 契約の締結について媒介をすることの委託をし、当該委託を受けた第三者が消費 者に対して行った場合も同様である。
主な不当勧誘行為
不実告知
重要事項について事実と異なることを告げること
断定的判断の提供
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるも のに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費 者が受け取るべき金額、その他の将来における変動が不確 実な事項につき断定的な判断を提供すること
不利益事実の不告知
消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連す る事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、 当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を 故意又は重大な過失によって告げなかったこと
不退去
事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行 っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかか わらず、それらの場所から退去しないこと
退去妨害
事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしてい 場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもか かわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと
過料契約
消費者契約の目的となるものの分量等が、 その消費者にと っての通常の分量等を著しく超えることを知っていた場 合において、その勧誘によりなされた消費者契約
不安をあおる告知
消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、次の事項 に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知 りながら、その不安をあおり、 裏付けとなる合理的な根拠 がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、 物 品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるもの が当該願望を実現するために必要である旨を告げること。 イ 進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要 な事項
ロ 容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重 要な事項
好意の感情の 不当な利用
消費者が、 社会生活上の経験が乏しいことから、 当該消費 者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情そ の他の好意の感情を抱き、かつ、 当該勧誘を行う者も当該 消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信して いることを知りながら、これに乗じ、 当該消費者契約を締 結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻すること になる旨を告げること
判断力の低下の 不当な利用
消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく 低下していることから、生計、 健康その他の事項に関しそ の現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知 りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠 がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、 当 該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が 困難となる旨を告げること
霊感等による知見 を用いた告知
消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく 低下していることから、 生計、 健康その他の事項に関しそ の現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知 りながら、 その不安をあおり、 裏付けとなる合理的な根拠 がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当 該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が 困難となる旨を告げること
契約締結前に債務 の内容を実施等
消費者が消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を する前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととな る義務の内容の全部又は一部を実施し、 その実施前の原状 の回復を著しく困難とすること
2. 取消権の行使期間
取消権は、 追認をすることができる時から1年間行わないときは、 時効によっ て消滅する。 また、 消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様に、 取消権は消滅する。
三 不当な契約条項が含まれていた場合における当該契約条項の無効
消費者契約における次の条項は、原則として、無効とされる。
主な不当契約条項
事業者の損害賠償の責任を免除する 条項
a) 事業者の債務不履行による損害賠償責任の免責条項
b) 事業者の不法行為による損害賠償責任の免責条項
c) 契約不適合による損害賠償責任の免責条項
消費者の解除権を 放棄させる条項
事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄 させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限 を付与する消費者契約の条項
事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項
事業者に対し後見開始の審判等によ る解除権を付与す る条項消費者が支払う損 害賠償の額を予定 する条項消費者の利益を一 方的に害する条項
消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項
a) 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金 を定める条項で、 これらを合算した額が、 同種の消費者 契約の解除で事業者に生ずべき平均的な損害の額を超 えるもの (超過する部分が無効)b) 消費者契約において消費者に課される遅延損害金年率 が 14.6%を超えるもの (超過する部分が無効)
消費者の利益を一方的に害する条項
民法、商法等の法律の公の秩序に関しない規定の適用によ る場合に比し、 消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務 を加重する消費者契約の条項であって、 民法1条2項に規 定する基本原則 (信義誠実の原則) に反して消費者の利益 を一方的に害するもの
四 他の法律の適用
消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の 効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めに よるものとされている。 たとえば、 消費者契約法が適用される契約にも、 宅建業法 等の規定は適用される。 具体的には、 宅建業法で規定されている宅建業者が自ら売 主となる場合に適用される瑕疵担保責任の特約の制限は、消費者契約法が適用され る契約においても、適用される。