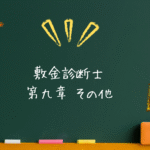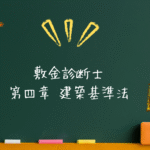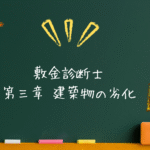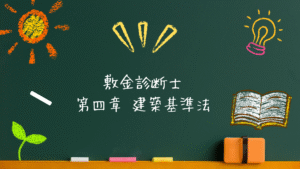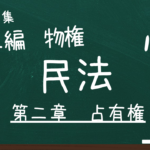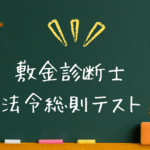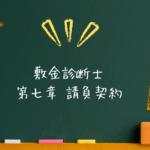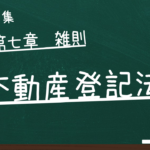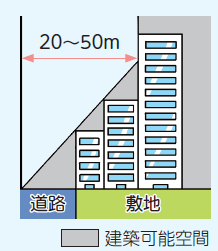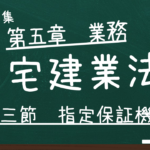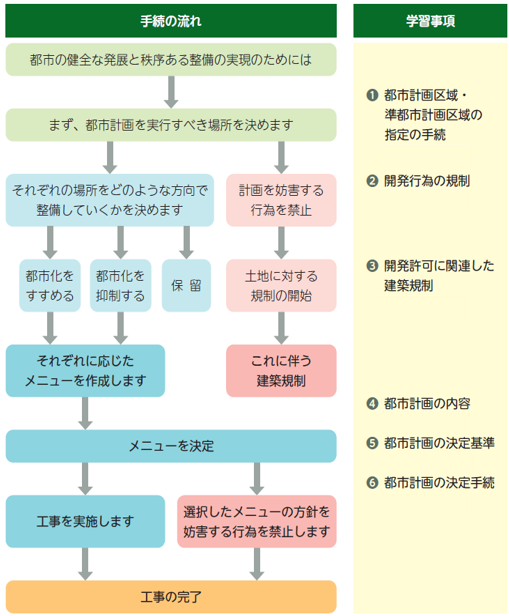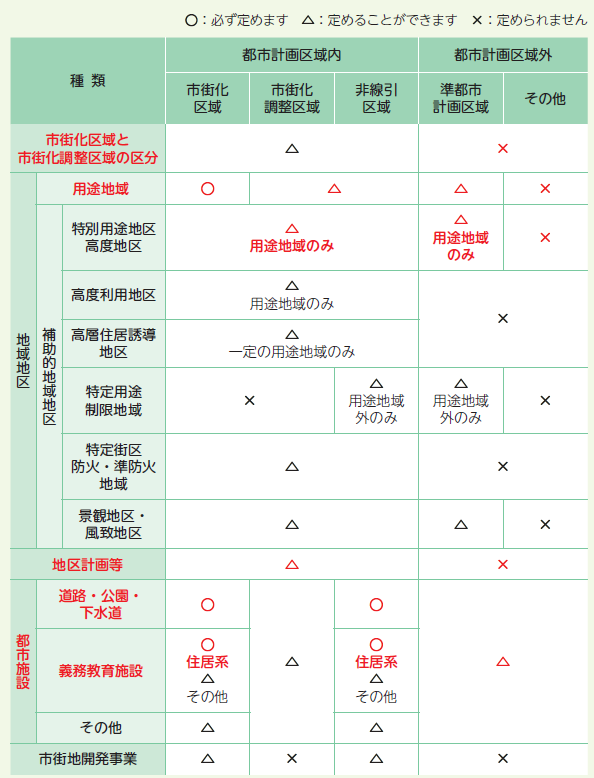Contents
第1節 債権の担保 (民法)
一. 総論
債権の担保には、大きくわけて2つの種類 (人的担保と物的担保)がある。 人的担保とは、債務者以外の者の総財産で債務の弁済を確保する手段をいい、 保証債務が典型例である。物的担保とは、 特定の財産による債務の弁済の確保をいい、 法律上当然に成立 する法定担保物件 (先取特権等) と、 契約に基づいて成立する約定担保物権 (抵 当権等) がある。
二. 保証
1. 意義
保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、 保証人が主たる債務者の 代わりに債務を履行する義務を負う制度をいう。 また、 保証人が債権者に対して 負担する義務を保証債務という。
2. 成立
保証債務は、 債権者と保証人との契約で生じる。 そして、この保証契約は、主 たる債務者の意思に反して結ぶことができるが、書面 (又は電磁的記録) でしな ければ、その効力を生じない。なお、主たる債務者と保証人との契約は、必ずしも必要でない。
3. 保証人となる資格
主たる債務者が保証人を立てる義務を負う場合、 その保証人は、行為能力者で、弁済の資力を有する者でなければならない。ただし、債権者が保証人を指名した場合には、この要件はあてはまらない。
4. 保証債務の範囲
保証債務は、主たる債務に関する利息 違約金 損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを含む。
5.性質
① 附従性
主たる債務がなければ保証債務は成立せず、主たる債務が消滅すれば、保証債務もまた消滅するという性質のこと。附従性の内容をまとめると、 以下のようになる。
・主たる債務が成立しなければ、 保証債務も成立せず、主たる債務が消滅すると、 保証債務も消滅する。
・主たる債務の内容が軽くなると、 保証債務の内容も軽くなる。 しかし、主 たる債務の内容が重くなっても、 保証債務の内容は重くならない。
・保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、 主たる債務の限度に減縮される。
・主たる債務者について生じた事由の効力 (消滅時効の中断等)は、原則と して保証人にも及ぶ。 一方、 通常の保証の場合、 保証人について生じた事 由の効力は主たる債務を消滅させる行為のほかは、主たる債務者に影響を 及ぼさない。
なお、主たる債務者が債権者に対していえることは、保証人も債権者に対し ていうことができる (抗弁権の援用)。
②随伴性
主たる債務が移転した場合、それに伴って保証債務も移転する性質のこと。
③補充性
主たる債務者が履行しない場合に、 はじめて履行すべき責任が生ずるという 性質のこと。 したがって、 保証人は、以下の2つの抗弁権を有する。
a) 催告の抗弁権
債権者が保証人に請求してきた場合に、 保証人は、まず主たる債務者に 催告すべきと主張できる。 これを催告の抗弁権という。
b) 検索の抗弁権
債権者が債務者に催告した上で保証人に請求してきた場合、保証人が債 務者に弁済の資力があり、かつ、 強制執行が容易にできる、ということを 証明すれば、債権者はまず債務者の財産について執行をしなければならな い。 これを検索の抗弁権という。
6.求償権
求償権とは、保証人が主たる債務者に代わって債権者に弁済した場合、自分が 弁済した分を返すよう請求する権利をいう。
三. 連帯保証
1. 意義
連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を保証する保証債務をい う。 通常の保証に比べて、 債権者に有利なことが多い。
2. 性質 〈S454 S453 S 452〉
① 補充性が認められない。→催告の抗弁権・検索の抗弁権がない。
② 分別の利益が認められない。
四. 連帯債務
1. 意義
連帯債務とは、複数の債務者がいて、 債権者がその中の1人に又は全員に対し て債務の全部の履行を請求できるような債務をいう。
2.負担部分
各連帯債務者は、それぞれ独立に全額について債務を負っているから、 債権者 から全額の支払いを請求されると、それを拒めない。ただし、債務者の間では、それぞれ一定の割合で義務を負担しあうことができ る(負担部分という)。そして、連帯債務者の1人が債権者に全額を支払った場 合、当該連帯債務者は、他の連帯債務者に対して、負担部分に従って、求償をすることができる。
3. 連帯債務者間の関係
① 相対的効力 (原則)
相対的効力とは、連帯債務者の一人に生じた事由が、他の連帯債務者には影 響しないことをいう。たとえば、債権者Aが、連帯債務者Bに対して裁判上の 請求をし、Bの債務について消滅時効の完成が猶予された場合でも、連帯債務 者Cの債務については、 消滅時効の完成は猶予されない。連帯債務では、この相対的効力が原則である。
② 絶対的効力 (例外)
絶対的効力とは、連帯債務者の1人に生じた事由が、 他の連帯債務者に影響 することをいう。たとえば、連帯債務者が債務全部の履行を行って消滅すれ ば、連帯債務者Cの債務も消滅する。連帯債務では、この絶対的効力は例外となり、次の事由がこれにあたる。
絶対効を 生ずる事由
① 債務の履行 (弁済)
②更改 (旧債務を消滅させ、 新債務を発生させる契約)
③連帯債務者の1人が自己の有する反対債権で行う相殺
④混同 (債務者が債権者を相続した場合のように、 債権者 の地位と債務者の地位が同一人に帰属すること)
五. 先取特権
1. 意義
先取特権とは、法律で定める一定の債権を有する者が、 債務者の財産から、他 の一般債権者より優先して弁済を受けることができる担保物権のことをいう。 一 定の条件がそろえば法律上当然に発生する (法定担保物権)。
2.性質
後述する抵当権と同様、 ① 物上代位性、 ②不可分性、 ③ 附従性、 随伴性の性質をもつ。
六. 抵当権
1. 意義
抵当権とは、債務者または第三者(物上保証人という)が、債務の担保にした 不動産等その他一定の権利について、 他の債権者に先立って優先的に弁済を受け る権利をいう。 具体的にいうと、担保の目的物を競売にかけて、その代金から優 先的に弁済を受けることができる権利である。
2. 成立
① 債務者が抵当権設定者の場合抵当権は、抵当権者と抵当権設定者との合意により成立する。 この場合、 書 面の作成や登記は必要ない。
② 債務者以外の者が抵当権設定者の場合
債務者が適当な不動産を持っていない場合に、 債務者以外の者が所有する不 動産等財産に抵当権を設定してもらうことを物上保証といい、 その財産を提供 する者のことを物上保証人という。
③.目的物
不動産、地上権、 永小作権を抵当権の目的とすることができる。 しかし、賃借権は、抵当権の目的とすることはできない。
④. 性質
抵当権には、次のような性質がある。
①附従性
被担保債権が成立しなければ、 抵当権も成立せず、 また、 被担保債権が消滅すると、 抵当権も消滅するという性質のこと。
②随伴性
被担保債権が移転すると、 抵当権も移転するという性質のこと。
③不可分性従性
債権の全額の弁済を受けるまで、抵当目的物全体に対して権利を 行使できるという性質のこと。
④物上代位性
目的物の売却・賃貸・滅失・損傷等により、 債務者が受ける金銭 その他の物に対しても権利を行使しうるという性質のこと。 対象 となるのは、保険金請求権、 損害賠償請求権、 賃料 売買代金等 ある。 なお、 物上代位をするためには、金銭が抵当権設定者に支 払われる前に、抵当権者が差押えをしなければならない。
⑤ 効力の及ぶ範囲
抵当権の効力が及ぶ範囲とは、抵当権の実行の際に、抵当権が設定されている 目的物(抵当不動産)のほか、一緒に競売の対象とすることができるものの範囲 である。 具体的には、次のものがある。
抵当権の効力が及ぶ範囲/具体的内容
目的不動產
・抵当権の設定された土地
・抵当権の設定された建物
付加一体物
・不動産の構成部分。 壁紙等。
抵当権設定時の従物
・ある物に従属して効用を助けるもの。 畳等。
従たる権利
・借地上の建物に対する借地権等。
⑥. 被担保債権の範囲
抵当権者が、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則として、 その満期となった最後の2年分についてのみ、 抵当権を行使できる。ただし、後順位抵当権者等がいない場合には、抵当権者は、満期となった最後 の2年分を超える利息についても抵当権を行使できる。 この制度が、 抵当権者と 第三者の利益を調整することを目的とするものであり、抵当債務が縮減するわけ ではないからである。
⑦. 抵当権設定者の権利
抵当権設定者は、 抵当権が実行されるまでは、 抵当目的物を使用・収益処分することができる。
⑧. 第三取得者との関係
① 第三取得者とは
(抵当不動産の) 第三取得者とは、抵当不動産について所有権を取得した者をいう。
② 抵当権者と第三取得者との関係
・第三取得者が先に登記した場合は、第三取得者は、抵当権がついていない土地を取得することができる。
•抵当権者が先に登記した場合は、第三取得者は、抵当権がついている土 地を取得する。
③代価弁済
抵当不動産の第三取得者は、抵当権者からの請求に応じて抵当権者にその代 価を弁済すれば、抵当権を消滅させることができる。
④抵当権消滅請求
抵当不動産の第三取得者は、一定の手続きに従って、抵当権消滅請求をすることができる。
⑨. 抵当権設定後の賃貸借
抵当権設定登記後に抵当目的物について賃貸借契約が締結された場合、当該 賃借人は賃借権を抵当権者に対抗することができない (競売により消滅させら れる)のが原則である。
① 抵当権者の同意の登記がある場合
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者 が同意をし、かつ、 その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者 に対抗することができる。ただし、抵当権者がその同意をするには、その抵当権を目的とする権利を 有する者その他抵当権者に同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得 なければならない。
②明渡猶予制度
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建 物の使用又は収益をする者で、a) 競売手続の開始前から使用又は収益をす る者、及びb) 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始 後にした賃貸借により使用又は収益をする者は、建物の競売における買受人 の買受の時から、6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
もっとも、買受人の買受の時より後にその建物の使用をしたことの対価に ついて、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1ヶ月分以 上の支払を催告し、 その相当の期間内に履行がない場合には、その建物を買愛人に引き渡さなければならない。
⑩. 法定地上権
① 意義
土地と建物が同一の所有者に帰属する場合に、 抵当権の実行により、土地と 建物の所有者が異なることとなったときに、 建物の存続を図るため、一定の要件を満たすことを条件にその建物について地上権が設定されたものとみなし た。 これを法定地上権という。
② 法定地上権の成立要件
法定地上権が成立するためには、以下の4つの要件が必要である。
a) 抵当権設定時に、 土地の上に建物が存在する。
.建物について登記は不要 (建物が存在すればよい)。抵当権設定当時建物が存在していれば、 設定後に建物が滅失し、同様の建物が再築された場合でもよい。
b) 抵当権設定時に、土地と建物の所有者が同一人である。
抵当権設定後に、土地、建物のどちらかが譲渡され、 土地と建物がそれぞれ別人の所有に属した場合でもよい。
c) 土地と建物の一方又は両方に抵当権が存在する。
d) 抵当権実行の結果、 土地と建物の所有者が別々になる。
⑪. 一括競売
更地に抵当権を設定した後に、 抵当地に建物を建築した場合に、抵当権者は、 土地とともに建物を一括して競売することができる。これを一括競売という。 ただし、優先的に弁済を受けられるのは、土地の代価についてのみである。
第2節 不法行為(民法)
一. 不法行為責任(一般的不法行為)
1. 意義
不法行為責任とは、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者が、 これによって生じた損害を賠償する責任をいう。
2. 要件
①故意又は過失があること
②権利侵害 (違法性) があること
③他人に損害を発生させること
④行為と損害との間に因果関係があること
3. 効果
被害者は、加害者に対して損害の賠償を請求できる。賠償の方法は、金銭賠償によるのが原則である。
二. 特殊な不法行為
1. 使用者責任
① 意義
使用者責任とは、 ある事業のために他人を使用するものが、被用者がその事 業をするにあたり、 第三者に加えた損害を賠償する責任をいう。
②要件
・使用者と被用者との間に使用関係があること
・被用者の行為が事業の執行につきなされること
・被用者が第三者に不法行為を行ったこと
・免責事由がないこと (選任監督の注意義務)
③ 効果
使用者は、被用者の行為から生じた損害を賠償する責任を負う。 この場合、 被用者にも不法行為責任が成立しているので、 使用者、 被用者いずれも全額の 損害賠償責任を負う。
④ 使用者の求償権
使用者は、 被害者に賠償をしたときは、 その後、直接の加害者たる被用者に、一定の範囲で求償をすることができる。
2. 工作物責任
① 意義
工作物責任とは、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他 人に損害を生じさせた場合に、その工作物の占有者と所有者が負う責任のこと をいう。
②要件
土地の工作物であること
設置または保存の瑕疵によること
瑕疵によって損害が生じたこと.
占有者については、 免責事由のないこと
③ 効果
第一次的には占有者が損害賠償の責任を負うが、 占有者が、 損害の発生を防 止するのに必要な注意をした場合にはその責任を免れる。 その場合には第二次 的に所有者が責任を負う。 この所有者の責任は、 無過失の責任である。
④ 原因が第三者にある場合の責任
土地工作物から生じた損害を賠償した占有者・所有者は、損害の原因につい て他にその責任を負う者があるときは、その者に対して求償権を行使すること ができる。
3. 動物の占有者等の責任
① 意義
動物の占有者等の責任とは、動物の占有者または占有者にかわって動物を保 管する者が、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任をいう。
②要件
動物の加えた損害であること免責事由のないこと
③効果動物の占有者等は原則として責任を負い、 動物の種類や性質に従って相当の注意をもってその管理をしていた場合には、責任を免れる。
4. 共同不法行為
① 意義
共同不法行為責任とは、数人の者が共同して不法行為を行い、それによって 他人に損害を加えた場合 (狭義の共同不法行為) または、 共同行為者中のだれ が実際に損害を加えたのかが明らかでない場合に、 共同行為者が負担する責任 のことをいう。
② 要件
a) 数人の者が共同して不法行為を行い、それによって他人に損害を加えた場合(狭義の共同不法行為)
・各自の行為が独立して不法行為の要件を備えていること
・共同行為者間に客観的共同関係があること
b) 共同行為者中のだれが実際に損害を加えたのかが明らかでない場合
・共同行為者であること
・各共同不法行為者が因果関係以外の不法行為の一般的成立要件をみたしていること
・共同行為者のいずれかの行為によって損害が生じていること
③ 効果(不真正連帯債務)
共同不法行為と相当因果関係がある全損害について、 共同不法行為者は、連帯して損害賠償責任を負い、この債務は、不真正連帯債務と解されている。不真正連帯債務とは、 同一内容の給付を目的とする債務が偶然に競合する場合に、①多数の債務者が同一内容の給付について全部履行すべき義務を負い、 一債務者の履行によって全債務者が履行を免れるとういう点で連帯債務と似 ているが、 ② 債務者間に緊密な結合関係がないため、一債務者について生じた 事由が他の債務者に影響を及ぼさず、求償関係も当然には生じないという点で、 連帯債務とは異なる債務である。債権者は不真正連帯債務者の一人に対し、 または全員に対して、同時もしく は順次に、全部または一部の履行の請求をすることができる。 そして、 弁済等 の債権を満足させる事由は、 絶対的効力を生じるが、 その他の事由については 相対的効力にとどまる。なお、判例上、 共同不法行為者の1人が被害者の全損害を賠償した場合、 そ の者は過失割合ないし損害発生に対する寄与度に応じて、 他の共同不法行為者 に求償することができるとされている。
5. 未成年者の不法行為
① 未成年者の責任能力
未成年者が他人に損害を加えた場合において、 自己の行為の責任を弁識する に足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わ ない。自己の行為の責任を弁識するに足りる知能のことを責任能力という。 そして、 行為の責任を弁識するに足りる知能とは、自己の行為が違法なものであって、 法律上の責任が生じるものであることを認識できる能力のことをいう。
② 監督義務者等の責任
責任無能力者が他人に損害を加えたが責任を負わない場合、 その責任無能力 者を監督する義務を負う者は、その損害を賠償する責任を負う。 また、監督義 務者に代わって責任無能力者を監督する者も、同様の責任を負う。ただし、監督義務者等がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠ら なくても損害が生ずべきであったときは責任を負わない。
6. 請負契約の注文者の責任
注文者は、原則として、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償 する責任を負わない。なぜなら、注文者と請負人との関係は、使用者としての責任 が問われる使用関係に該当しないからである。ただし、注文者が請負人に対してなした注文又は指図について過失があり、これによって他人に損害が生じた場合は、 その損害を賠償する責任を負う。
第3節相続 (民法)
一. 意義
相続とは、死亡した人 (被相続人という)が生前に有していた財産(権利義務)をその者の死後に、法律が特定の者 (相続人という)に包括的に受け継がせる制 度をいう。相続は、被相続人の死亡だけを原因として開始する。
二. 効果
1. 相続財産の包括承継
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した権利義務を包括的に承継する。相続人は、被相続人の一身に専属したもの(委任者、受任者たる地位など)を 除いて、被相続人が有していた一切の権利義務(不動産の所有権等の財産、さら には、契約当事者の地位や、善意悪意、故意・過失といった主観的事情)を承継する。
2. 相続人の範囲
相続人となることができる者の範囲は法律で定められており、 その中でも順位 がある。 ただし、相続放棄、 排除、 相続欠格といった制度があるので、 実際の相 続人は、この順位と異なることもある。
3. 推定相続人
・配偶者は、他の相続人とともに常に相続人となる。
・直系尊属、 兄弟姉妹は、この順で相続人となる。
・相続人がいない場合は、 特別縁故者なき限り、 相続財産は国庫に帰属する。
4.相続分
相続分とは、相続人が数人いる場合、 各相続人が承継する被相続人の財産の割 合のことをいう。 相続分は、各相続人の遺留分を害しない範囲で、被相続人が自 由に指定できる(指定相続分)。 しかし、指定がないときは、法律が規定する割 合による(法定相続分)。
法定相続分は、以下のように定められている
a) 配偶者と子が相続人の場合→配偶者2分の1、2分の1
b) 配偶者と直系尊属が相続人の場合→配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
c) 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合→配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
※子、直系尊属または兄弟姉妹が複数いるときは、各自の相続分は平等。
5. 共同相続の効力
相続人が数人いる場合を共同相続という。 この場合、相続財産はいったん相続 人全員の共有に属する。
6. 金銭債権・債務の相続
金銭債権・金銭債務は、 原則として、 相続開始と同時に、 遺産分割手続を経ず に、各相続人の相続分に応じて法律上当然に分割して帰属する。
三. 相続の承認・放棄
1. 意義
①相続の(単純) 承認とは、 相続人が、被相続人の権利義務を無限定・無条件 に承継することをいう。
② 限定承認とは、相続人が承継する積極財産の限度で相続債務等の責任を負う という留保をつけて相続することをいう。 限定承認は、 共同相続人全員が共同 して行わなければならない。
③ 相続放棄とは、一切の相続財産の承継を拒否することをいう。
2.承認・放棄の撤回
一度なされた相続の承認・放棄は、原則として撤回できない。 これを認めると、 法律関係が不安定になり、利害関係人に不利益を与えるからである。ただし、意 思表示に関する規定に基づき、 無効や取消しを主張することはできる。
四. 遺言 遺留分
1. 遺言
遺言とは、死後の法律関係を定める最終意思の表示のことをいう。 遺言者は、 その意思を書き残すことによって、死後も自己の財産を自由に処分することができる。遺言によって財産を贈与することを遺贈という。
2. 遺留分
一定の相続人のため、法律上必ず確保されなければならない一定額のことをい う。 遺言によって、 遺言者は、自己の財産を自由に処分することができるが、こ れを無制限に認めると、 最も身近な親族が遺言者の死後、生活を脅かされること にもなる。 そこで、 遺言があっても、兄弟姉妹以外の相続人は、 最低限の取り分 として、一定額を確保することができるとされているのである。
第4節 個人情報の保護 (個人情報保護法)
一. 個人情報保護法
高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに かんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、 基本理念及び政府による基本方針の 作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方 公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守す べき義務等を定めることにより、 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利 益を保護することを目的として制定された。
二. 定義
1. 個人情報
個人情報とは、生存する個人に関する情報で,次のどちらかに該当するものをいう。
① 当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を 識別することができるもの
② 個人識別符号が含まれるもの
※①には,他の情報と容易に照合することができ, それによって特定の個人 を識別することができるものを含む。 たとえば, 防犯カメラに記録された 情報等, 本人 (特定の個人) が判別できる映像情報も該当する。
※②の「個人識別符号」 とは, 「身体の一部の特徴を電子計算機のために変 換した符号 (指紋認識データ顔認識データ DNA情報等)」 や 「サー ビス利用のため、及び, 書類上で対象者ごとに割り振られる符号 (基礎年 金番号・旅券(パスポート) 番号・免許証番号・住民票コード・マイナン バー等)」のことである。
2. 個人情報データベース等
個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の集合物であって、 ①特定 の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し たもの、②①に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができ るように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。
3. 個人情報取扱事業者
個人情報取扱事業者とは、 個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 ただし、①国の機関、 ②地方公共団体、③ 独立行政法人等、 ① 地方独立行 政法人は除外する。
4. 個人データ
個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
5. 保有個人データ
個人情報取扱事業者が、 開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去 及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであっ て、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして 政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなる もの以外のものをいう。
6. 本人
本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
三. 個人情報取扱事業者の義務
1. 利用目的の特定
個人情報取扱事業者は、 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的 (「利用目的」)をできる限り特定しなければならない。
2. 利用目的による制限
個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合 人の生命、身体又は財産の保護の ために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合等を除 くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な 範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
3. 適正な取得
個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
4. 取得に際しての利用目的の通知等
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、原則として、あらかじめ その利用目的を公表している場合を除き、 速やかに、その利用目的を、本人に通 知し、又は公表しなければならない。また、個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合も、原則として、変更 された利用目的について、 本人に通知し、又は公表しなければならない。
5. データ内容の正確性の確保
個人情報取扱事業者は、 利用目的の達成に必要な範囲内において、 個人データ を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
6. 安全管理措置
個人情報取扱事業者は、 その取り扱う個人データの漏洩、滅失又はき損の防止 その他個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
7. 従業者の監督
個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、 当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な 監督を行わなければならない。
8.委託先の監督
個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、 その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者 に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
9. 第三者提供の制限
個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合、 人の生命、身体又は財産の保護の ために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合等を除 くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
10. 保有個人データに関する事項の公表等
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、一定の事項について、本人の 知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。) に置かなけ ればならない。また、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目 的の通知を求められたときは、原則として、 本人に対し、遅滞なく、 これを通知 しなければならない。
11. 開示
個人情報取扱事業者は、 本人から、当該本人が識別される保有個人データの開(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせる ことを含む。)を求められたときは、原則として、 本人に対し、政令で定める方 法により、遅滞なく、 当該保有個人データを開示しなければならない。 もっとも、 この場合、 個人情報取扱事業者は、 当該措置の実施に関し、 手数料を徴収するこ とができる。
12. 訂正等
個人情報取扱事業者は、 本人から、当該本人が識別される保有個人データの内 容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は 削除を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特 別の手続が定められている場合を除き、 利用目的の達成に必要な範囲内において、 遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂 正等を行わなければならない。
13. 利用停止等
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが利 用目的による制限の規定に違反して取り扱われているという理由又は適正な取 得の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人デ ータの利用の停止又は消去 (利用停止等) を求められた場合であって、その求め に理由があることが判明したときは、原則として、 違反を是正するために必要な 限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。
14. 理由の説明
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関する事項の公表等、 開示、訂正等 又は利用停止等の規定により、 本人から求められた措置の全部又は一部について、 その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通 知する場合は、 本人に対し、 その理由を説明するよう努めなければならない。
15. 開示等の求めに応じる手続
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関する事項の公表等、 開示、訂正等 又は利用停止等の規定による求めに関し、政令で定めるところにより、その求め を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法 に従って、開示等の求めを行わなければならない。
第5節 住宅性能表示制度(品確法)
一. 住宅性能表示制度の創設
住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法)により、住宅の構造耐力、遮音性、火災時の安全性、省エネルギー性、高齢者への配慮等、 住宅の性能を表示する ための共通の基準である「日本住宅性能表示基準」を、国土交通大臣が定めなけれ ばならないとされた。これにより、購入者が契約等の前に住宅の性能を容易に比較 できるようになった。この住宅性能評価の結果を契約内容に反映させることで、表 示された住宅の性能についての信頼性を確保することができる。
二. 住宅性能表示制度の対象となる住宅
新築及び中古の住宅が対象となる。なお、一棟の建物の中に住居部分と事務所部分とに分かれているものがある場合 には、「住居部分」と「住居部分と事務所部分の共用する部分」 については当該制 度を利用することができるが、 「事務所として使用される部分」 は、この制度の対 象とはならない。
三. 日本住宅性能表示基準
国土交通大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、 日本住宅性能表 基準 (住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準をいう。)を 定めなければならない。 この基準は、 住宅の性能に関し 「構造の安全に関すること」 「火災時の安全に関すること」 などの項目について、 等級や数値等で表示される。 また、この基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価 (評価のための検査 を含む。)の方法の基準 (「評価方法基準」)をも定めなければならない。
四. 住宅性能評価
国土交通大臣の登録を受けた者 (登録住宅性能評価機関) は、 申請により、 住宅 性能評価 (日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、 評価方法基準に 従って評価することをいう。)を行い、標章を付した評価書 (住宅性能評価書)を 交付することができる。
五. 住宅性能評価書
1. 設計住宅性能評価書
① 住宅の建設工事の請負人は、設計された住宅に係る住宅性能評価書(設計住 宅性能評価書) 若しくはその写しを請負契約書に添付し、又は注文者に対し設 計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅 性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行う契 約をしたものとみなされる。
②新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評価書若しくはその写しを売買契約書に添付し、 又は買主に対し 設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住 宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すこ とを契約したものとみなされる。
2. 建設住宅性能評価書
新築住宅の建設工事の完了後に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、 建設 された住宅に係る住宅性能評価書 (建設住宅性能評価書) 若しくはその写しを売買 契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくはその写しを交付した 場合において、当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新 築住宅を引き渡すことを契約したものとみなされる。
六. 指定住宅紛争処理機関
国土交通大臣は、 弁護士会等で、 建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工 事の請負契約又は売買契約に関する紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を公正か つ適確に行うことができると認められるものを 指定住宅紛争処理機関として指定することができる。そして、指定住宅紛争処理機関は、 建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設 工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請に より、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁 (住宅紛争処理) の業務を行うものとされている。
七. 住宅紛争処理支援センター
国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅 購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目 的として、 財団法人であって、 業務に関し一定の基準に適合すると認められるもの を 住宅紛争処理支援センターとして指定することができる。これにより、当該住 宅紛争を解決する相談窓口が用意されている。