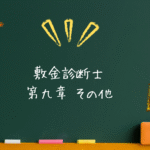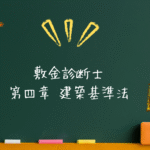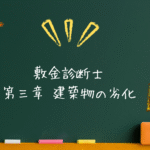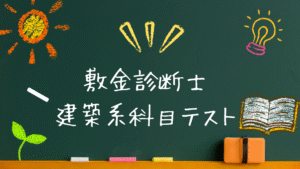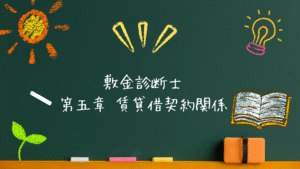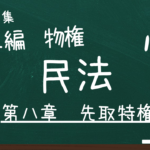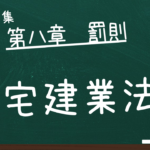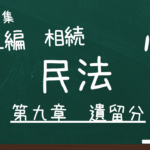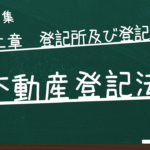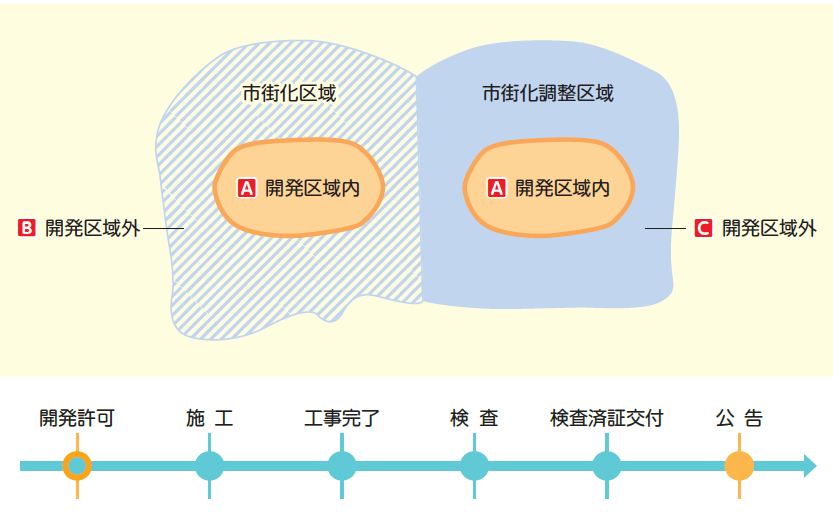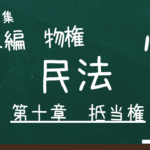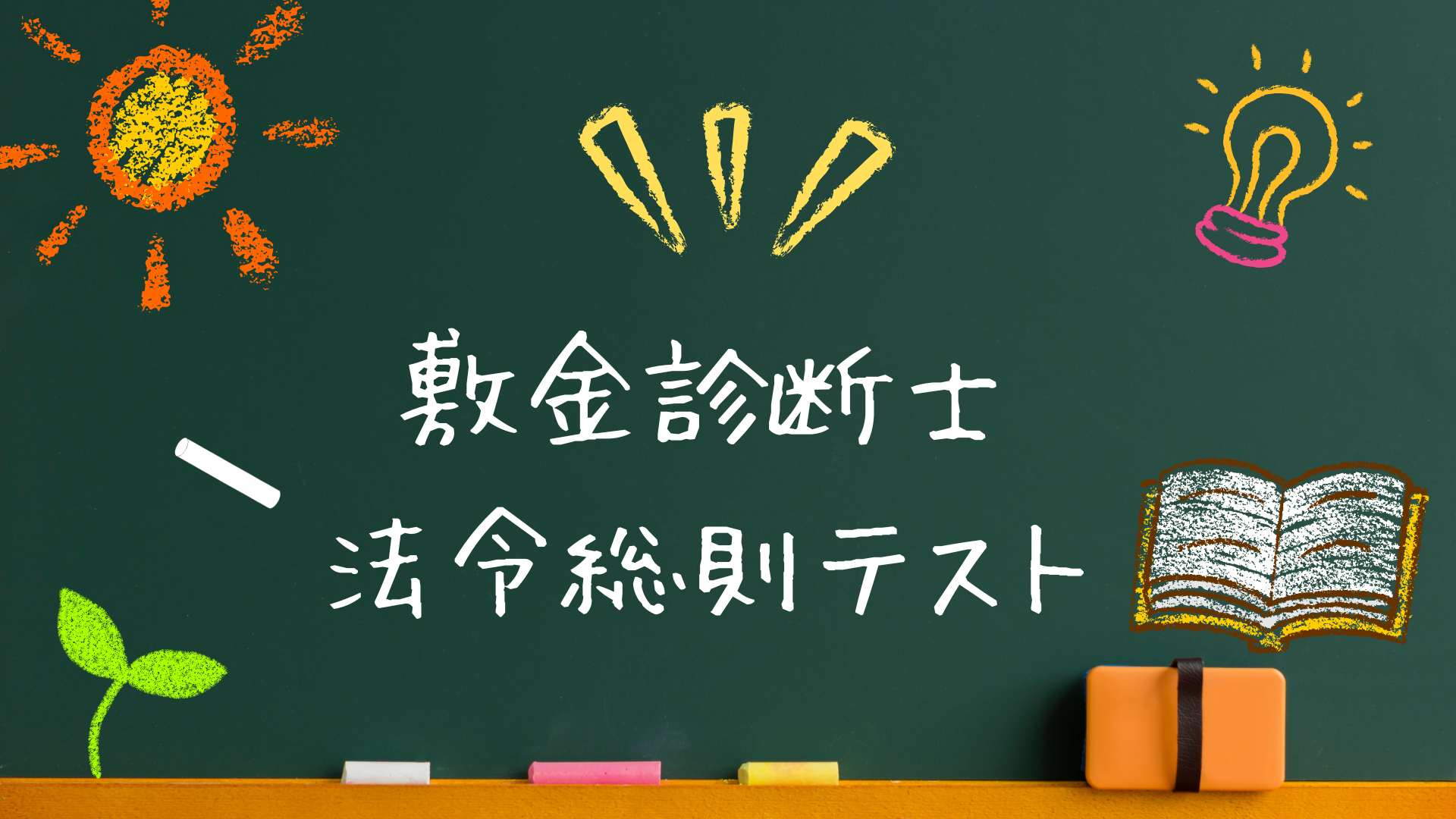
第1節 民法(総則)
1. 制限行為能力者とは、未成年者、成年被後見人、被保佐人の三者である。
2. 営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の能力を有する。
3. 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、原則として、当意思表示の取消しをすることができない。
4. 詐欺による意思表示は、取り消すことができるが、 当該取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
5. 強迫による意思表示はこれを取り消すことができるが、取消し前の善意かつ無過失の第三者には、その取消しを対抗することができない。
6. 代理人が本人のためにすることを示さなかった場合には、原則として、その代理人の意思表示は、自己のためにしたものとみなされる。
7. 制限行為能力者が任意代理人としてした行為は、行為能力の制限によって 取り消すことができる。
8. 代理人が、 その権限外の行為をした場合であっても、 相手方がその権限が あると信ずるべき正当の理由があるときは、 有効な代理となり、本人はその 責任を負う。
9. 債権について消滅時効の期間が満了すれば、その債権は直ちに消滅する。
10. 債権は、原則として、債権者が権利を行使することができることを知った時 から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
11. AがBに対して有する債権について裁判上の請求を行った場合でも、後に その請求を取り下げたときは、その終了の時から6ヵ月を経過するまでの間 は、 時効は、 完成しない。
12. 時効の完成後にそれを知らずに債務の存在を承認した者は、その後時効の 援用をすることができない。
1. × 制限行為能力者は、未成年者、 成年被後見人、被保佐人、被補助人の四者である (民法5条、8条、12条、16条)。
2 . ○ 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の 能力を有する(民法6条1項)。
3. ○ 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、原則として、当該意思 表示の取消しをすることができない (民法95条3項)。
4. ○ 詐欺による意思表示は、取り消すことができる (民法96条1項)。 しかし、当該取 消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない (同条3項)。
5. × 強迫による意思表示はこれを取り消すことができる(民法96条1項)。 また、 強 迫による取消しは、取消し前の善意かつ無過失の第三者に対しても、対抗すること ができる (同条3項参照)。
6. ○ 代理人が本人のためにすることを示さなかった場合には、原則として、その代理 人の意思表示は、自己のためにしたものとみなされる (民法10条本文)。 代理人が 相手方に顕名しなかった場合の規定である。 なお、 相手方が、 代理人が本人のため にすることを知り又は知ることができたときは、 代理行為として本人に効果が帰属 する (同法100条ただし書)。
7. × 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消す ことができない。 ただし、 制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人とし てした行為については、この限りでない (民法102条)。
8. ○ 代理人が、その権限外の行為をした場合であっても、第三者 (行為の相手方) が その権限があると信ずるべき正当の理由 (善意無過失) があるときは、 有効な代 理となり、 本人はその責任を負う(表見代理 民法110条)。
9. × 消滅時効を当事者が援用しなければ、裁判所はこれに基づいて裁判をすることが できない (民法 145条)。 従って、 消滅時効の期間が満了しても当事者が援用するま では、 債権は消滅しない。
10. × 債権は、原則として、債権者が権利を行使することができることを知った時から 「5年間」 行使しないときは、時効によって消滅する (民法166条1項1号)。
11. ○ 裁判上の請求を行った場合、 その事由が終了する (確定判決又は確定判決と同一 の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあ っては、その終了の時から6ヵ月を経過する) までの間は、 時効は、 完成しない (民 法147条1項1号)。
12. ○ 時効完成後に債務者が債務を承認した以上、 時効完成の事実を知らなかったとき でも、その後当該債務についてその完成した時効の援用をすることは許されない (最 判昭和 41.4.20)。 これは自己の行為に矛盾した態度をとることは信義則上許されな いからである。
第2節 消費者契約法
1 . 消費者契約とは、消費者と消費者との間で締結される契約をいう。
2. 消費者は、 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消 費者に対して、 重要事項について事実と異なることを告げられ、 当該告げら れた内容が事実であると誤認をした場合、 それによって当該消費者契約の申 込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
3. 消費者契約において、当該契約における事業者の債務の履行に際してなさ れた当該事業者の不法行為 (当該事業者、 その代表者又はその使用する者の 故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償 する民法の規定による責任の一部を免除する条項がある場合、 当該条項は原 則として無効となる。
1. × 消費者契約とは、消費者と 「事業者」 との間で締結される契約をいう。
2. ○ 消費者は、 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に 対して、 不実告知 (重要事項について事実と異なることを告げられ、 当該告げられ た内容が事実であると誤認をした場合) あるいは、断定的判断 (物品等当該消費者 契約の目的となるものに関し、 将来におけるその価額等将来における変動が不確実 な事項につき断定的判断を提供され、 当該提供された断定的判断の内容が確実であ るとの誤認をした場合) によって、 当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表 示をしたときは、これを取り消すことができる。
3. ○ 消費者契約において、当該契約における事業者の債務の履行に際してされた当該 事業者の不法行為 (当該事業者、 その代表者又はその使用する者の故意又は重大な 過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責 任の一部を免除する条項がある場合、当該条項は、消費者に不利益となるため、原 則として無効となる。
第二章 物権関係
第1節 民法 (共有)
1. 数人である物を共有する場合の共有持分は、共有者間で別段の特約がない限り、それぞれ等しいものと推定される。
2. 共有物の変更については、共有者の全員の同意が必要である。
3. 数人で共有する土地の保存登記をするには、持分価格の過半数の賛成が必要である。
1. ○ 各共有者の持分は、 特約がない限り相等しいものと推定される(民法250条)。
2. ○ 共有物の変更には、民法上、 共有者全員の同意が必要とされる (民法251条)。
3. × 共有物の保存行為は、各共有者が単独でなし得る (民法252条ただし書)。 共有す る土地の保存登記は、保存行為にあたる。 従って、 持分価格の過半数の賛成がなく とも、各共有者が単独でなし得る。
第2節 区分所有法
1. 専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいい、 専有部分といえ るためには、構造上の独立性と利用上の独立性が必要とされている
2. 法定共用部分とは、 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上 区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分をいい、そ の旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
3. 専有部分を規約により共用部分とすることができるが、規約による共用部 分を専有部分とすることはできない。
4. 共用部分についての共有者の持分は、区分所有法に別段の定めがある場合 を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
5. 各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積 の割合により、共用部分の管理費等の負担をしなければならない。
1. ○ 専有部分とは、 区分所有権の目的たる建物の部分をいう(区分所有法2条3項)。 そして、 区分所有権とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で (構造上の 独立性) 独立して住居、 店舗、事務所、又は倉庫その他建物としての用途に供する ことができるもの (利用上の独立性) があるときは、その各部分 (規約共用部分を 除く。)を目的とする所有権をいう (区分所有法2条1項、 1条)。
2. × 法定共用部分は、その性質や構造から当然に共用部分とされるのであり、外観上 明らかであるので、 登記がなくても第三者に対抗することができる (不登法91条3 項参照)。
3. × 専有部分を規約により共用部分とすることができる (区分所有法4条2項、1条)。 また、規約による共用部分を専有部分とすることもできる (同法4条2項、 31 条1 項参照)。
4. ○ 共用部分についての共有者の持分は、区分所有法に別段の定めがある場合を除い て、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない (区分所有法 15 条2項)。
5. ○ 共有者は、規約に別段の定めがない限り、 その持分に応じて、 共用部分の負担 に任ずる (区分所有法19条)。 そして、 持分は、 規約に別段の定めがなければ、 そ の専有部分の床面積の割合による (区分所有法14条1項、 4項)。
第三章 債権関係
第1節 民法(債務不履行)
1. 債権者が債務者の債務不履行を理由として契約を解除した場合、損害があれば合わせて損害賠償の請求をすることができる。
2. 金銭債務の不履行については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることはできない。
3. 契約の当事者間で違約金を定めた場合には、これは損害賠償額の予定と推 定される。
4. 債務不履行を理由とする損害賠償請求において、 特別の事情によって生じ た損害は、当事者がその事情を予見すべきであったとしても、債権者は、そ の賠償を請求することができない。
1. ○ 債務不履行を理由として解除をした場合でも、 損害があればその賠償を請求する ことができる(民法415条、545条4項)。
2. ○ 金銭を目的とする債務の不履行については、債務者は不可抗力をもって抗弁とす ることはできない (民法419条3項)。
3. ○ 契約の当事者間で違約金を定めた場合には、これを損害賠償額の予定と推定され ○る(民法420条3項)。
4. × 債務不履行を理由とする損害賠償請求において、特別の事情によって生じた損害 であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償 を請求することができる(民法416条2項)。
第2節民法 (契約総則)
1. 売買契約は、 有償・双務 要物契約である。
2. 賃貸借契約は、有償 双務諾成契約である。
3. 委任契約は、原則として、有償 双務 諾成契約である。
4. 請負契約は、原則として、有償 双務要物契約である。
1. × 売買契約は、有償 双務・ 「諾成」 契約である。
2. ○ 賃貸借契約は、有償 双務 諾成契約である。
3. × 委任契約は、 原則として、 「無償」・「片務」 諾成契約である。 なお、 報酬支払の 特約をした場合には、 有償・双務 諾成契約となる。
4. × 請負契約は、原則として、有償・双務・ 「諾成」 契約である。
第四章売買契約
第1節 民法 (売買)
1. 判例によれば、売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合、売主は原則として瑕疵担保責任を負うが、売主に過失がなければ免責される。
2. 売主が自己の所有する専有部分を買主に売却した場合に、 当該専有部分の 家庭用エアコンディショナーが故障していた場合、買主は売主に対し、 瑕疵 担保責任を追及して、当該売買契約を解除することができる。
3. 売買の目的物に隠れた瑕疵があることを、 契約締結から3年後に買主が知 った場合でも、その瑕疵の存在を知った日から1年以内であれば、 損害賠償 の請求をすることができる。
1. × 売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合の売主の担保責任 (民法570条、566条) は、 売買の有償性から法律上認められた責任であり、売主の故意過失にかかわらず、 売主が負わなければならない責任である (無過失責任)。
2. × 瑕疵担保責任に基づき契約を解除するためには、当該瑕疵により契約の目的を達 せられないことが必要である(民法570条、566条1項)。 この点、 専有部分にある 家庭用エアコンディショナーの故障があるだけでは 「契約の目的を達せられない」 人とは通常いえない。 従って、 当該契約を解除することはできない。
3. ○ 売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合、買主は売主に対し、 瑕疵担保責任と して損害の賠償を請求できるが (民法570条、566条)、 その期間は、買主が瑕疵の 存在を知ったときから1年以内である (同法 570条、566条3項)。 従って、契約締 結から3年後であっても、瑕疵の存在を知ってから1年以内であれば、損害賠償を 請求することができる。
第2節 担保責任
1. 宅地建物取引業者が自ら売主となって、一般消費者に家屋を売却する場合 において、 宅建業者は、 その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適 合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間を、 目的物の 引渡から1年とする特約を結ぶことができる。
2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」という。)の適用 のある新築住宅の売買契約において、 住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵が 存在する場合、品確法上、買主は売主に対して、追完請求として当該瑕疵の 修補を請求することができる。
1. × 宅建業者が自ら売主となって、 一般消費者に家屋を売却する場合において、 宅建 5 業者は、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合における その不適合を担保すべき責任について、 宅建業法上、 原則として、民法の規定より 買主に不利となる特約をしてはならない。 但し、例外的に、その期間について、「目 的物の引渡しの日から2年以上」 とする特約はすることができる。 したがって、宅 建業者は、 担保責任を負う期間を目的物の引渡から1年とする特約を結ぶことはで きない。
2. ○ 新築住宅の売買契約における買主は、品確法上、 ① 債務不履行による損害賠償請 ②催告による解除、 ③催告によらない解除、 ④履行の追完請求、 ⑤代金減額請 求をすることができる (品確法95条1項)。
第五章 賃貸借契約
第1節 民法 (賃貸借)
1. 賃借人が必要費を支出したときは、賃貸人に対して賃貸借終了時にその信 還を請求することができる。 また、有益費を支出したときは、賃貸人に対し て直ちにその償還を請求することができる。
2. 賃貸人が自己所有のマンションを賃貸している場合、賃貸人は賃借人の 同意を得ることなく当該マンションを第三者に売却することができる。
3. 賃借人が賃貸人所有のマンションについて敷金を差し入れて賃借してい る場合、賃貸人は賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、 賃借人に対し、 常に敷金全額を返還しなければならない。
4. 賃借人が賃貸人に事前に連絡しないで、 賃借している建物の修繕に必要な 費用を出費した場合には、その償還請求をすることができない。
5. 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができ なくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由 によるものであるときは、 賃料は、 その使用及び収益をすることができなく なった部分の割合に応じて、 減額される。
6. 不動産の賃借人が賃貸人に無断で賃借権の譲渡をした場合、 その譲渡契約 が成立すれば、譲受人が賃借物を使用する前であっても、賃貸人は無断譲渡 を理由に賃貸借契約を解除することができる。
7. 不動産の賃借人が賃貸人に無断で賃借権の譲渡をした場合、賃貸人は原則 として無断譲渡を理由に賃貸借契約を解除することができるが、 当該無断譲 渡に背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には解除をする ことができない。
1. × 賃借人が 「必要費」 を支出したときは、賃貸人に対して 「直ちに」 その償還を請求することができる。 また、 「有益費」 を支出したときは、賃貸人に対して 「賃貸借 「終了時」にその償還を請求することができる(民法608条1項、2項)。
2. ○ 民法は、貸主が貸した物を売ることを何ら制限していない。 従って、賃借人の同 意を得ることなくマンションを売却することができる。
3. × 賃貸人は、敷金 (いかなる名目によるかを問わず、 賃料債務その他の賃貸借に基 づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的 で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう)を受け取っている場合において、 賃貸 借が終了し、かつ、 賃貸物の返還を受けたときなどは、賃借人に対し、「その受け取 った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目 的とする債務の額を控除した残額」 を返還しなければならない (民法622条の2)。
4. × 賃借人が、 賃貸物につき賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人 に対して直ちに償還請求することができる(民法608条1項)。 しかし、 賃借人が賃 貸人に対して事前に連絡することは、償還請求をするための要件ではない。
5. ○ 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなっ た場合において、 それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであ るときは、 賃料は、 その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応 じて、 減額される (民法 611条1項)。
6. × 賃借人が賃貸人に無断で転貸 賃借権の譲渡をした場合において、第三者(転借 人・譲受人) が賃借物の 「使用・収益を開始したとき」 は、 賃貸人は、原則として 賃貸借契約の解除をすることができる (民法612条2項)。
7. ○ 賃借人が賃貸人に無断で転貸 賃借権の譲渡をした場合、 第三者 (転借人譲受 人)が賃借物の使用・収益を開始したときは、賃貸人は、原則として賃貸借契約の 解除をすることができる(民法 612条2項)。 しかし、無断譲渡・転貸であっても 背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、賃貸人は解除をするこ とができない (最判昭28.9.25)。
第2節 借地借家法
1. 建物の賃借人は当該建物の引渡しを受けていれば、その後、当該建物の所 有権を譲り受けた第三者に対して、当該建物の賃貸借を対抗することができる。
2. 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、 公正証書によって 契約を締結するときに限り、 契約の更新がないこととする旨を定めることが できる。
3. 駐車場として利用する目的で土地の賃貸借契約を締結した場合、 借地借家 法の適用はない。
4. 建物の賃貸借契約の期間が満了した場合において、 賃貸人が自ら使用する ことを必要とする等正当の事由があるときは、賃貸人は、 あらかじめ更新拒 絶の通知をしなくても、 賃貸借契約の更新を拒むことができる。
5. 建物の賃貸人の同意を得て賃借人が建物に付加した造作について、賃借人 は、 賃貸借契約終了の時に賃貸人に対して造作を時価で買い取るよう請求で きる権利を持っているので、 賃貸人は造作の買取りをしない旨の特約は、賃 借人に不利なものとして無効となる。
6. 借地契約の期間が満了し、 更新がない場合、 借地権者は、 借地権設定者に 対して、 借地上の建物を時価で買い取ることを請求できるが、かかる建物買 取請求権を認めないとする特約をすることもできる。
1. ○ 建物の賃借権は、その登記がなくても、当該建物の引渡しがあったときは、その 後その建物について所有権を取得した者に対し、その効力を対抗することができる (借地借家法31条1項)。
2. × 本肢はいわゆる「定期建物賃貸借」に関する問題である。 借地借家法によれば、 公正証書等の書面によって契約をするときに限り、 契約の更新がない旨を定めるこ とができる (借地借家法 38条1項)。 従って、書面によれば足りるのであって、必 ずしも公正証書によって契約を締結する場合に限られるのではない。
3. ○ 借地借家法は、建物所有を目的とする地上権及び土地の賃借権について適用され る(借地借家法1条)。 駐車場として利用する目的で土地の賃貸借契約を締結した場 合、建物所有を目的としたものではない。 従って、本肢の場合、 借地借家法は適用 されない。
4. × 期間の定めのある建物賃貸借契約は、当事者が期間満了の1年前から6カ月前ま での間に、 相手方に対して更新拒絶の通知をしなければ、 前の借家契約と同じ条件 で契約をしたものとみなされる。
5. × 建物の賃貸人の同意を得て賃借人が建物に付加した造作がある場合、賃借人は、 賃貸借契約終了時に、賃貸人に対して、 当該造作を時価で買い取ることを請求する ことができる。 この造作買取請求を認めない特約は、賃借人に不利な特約となるが 有効である。
6. × 借地契約の期間が満了し、 更新がない場合、 借地権者は、 借地権設定者に対して、 借地上の建物を時価で買い取ることを請求できる。 そして、この建物買取請求を認 めない特約は借地人に不利なものであるとして無効となる。 なお、この建物買取請 求は、 借地権者の債務不履行に基づく解除によって借地権が消滅した場合には認め られない (判例)。
第3節 賃貸住宅標準契約書
1. 住宅の賃貸借契約を締結する場合、賃貸住宅標準契約書を使用しなければならない。
2. 1か月に満たない期間の賃料は、1か月を31日として日割計算した額と する。
3. 貸主及び借主は、 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃 料が不相当となった場合、 協議の上、 賃料を改定することができる。
4. 階段、 廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、 上下水道使用料、 清 掃費等に充てるための共益費は、 貸主が負担する。
5. 借主は、 賃借した物件を明け渡すまでの間、 敷金をもって賃料 共益費そ の他の債務と相殺をすることができない。
6. 貸主は、賃借した物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、 敷金の全額を 無利息で借主に返還しなければならないが、 当該物件の明渡し時に、賃料の 滞納、 原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる借主の債務 の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができ る。
7. 貸主が修繕を行う場合は、貸主は、あらかじめ、 その旨を借主に通知しな ければならないが、 借主は、 当該修繕の実施を拒否することができる場合はない。
8. 借主は、貸主に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことによ り、本契約を解約することができる。
9. 借主は、解約申入れの日から30日分の資料(本契約の解約後の資料相当 額を含む。)を貸主に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30 日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
10. 借主は、本契約が終了する日までに(貸主の解除の規定に基づき本契約が 解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。
1. × 賃貸住宅標準契約書の契約書を利用することにより、合理的な賃貸借契約を結び、貸主と借主の間の信頼関係を確立することが期待できる。 しかし、 賃貸住宅標準契 約書は、あくまで賃貸借契約のひな型であるため、その使用は法令で義務づけられ ているものではない。
2. ✕ 1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする。
3. ○ 貸主及び借主は、 ①土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が 不相当となった場合、 ② 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変 動により賃料が不相当となった場合、 ③ 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料 相当となった場合には、協議の上、 賃料を改定することができる。
4. ×「借主」 は、 階段 廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、 上下水道使用 料、 清掃費等 (維持管理費) に充てるため、 共益費を貸主に支払うものとされてい る。
5. ○ 借主は、 賃借した物件を明け渡すまでの間、 敷金をもって賃料、共益費その他の 債務と相殺をすることができない。
6. ○ 貸主は、賃借した物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、 敷金の全額を無利息 で借主に返還しなければならない。 ただし、 貸主は、当該物件の明渡し時に、 賃料 の滞納、 原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる借主の債務の不 履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。 なおそ の際、貸主は、 敷金から差し引く債務の額の内訳を借主に明示しなければならない。
7. × 貸主が修繕を行う場合は、 貸主は、あらかじめ、 その旨を借主に通知しなければ ならない。 この場合において、 借主は、 「正当な理由がある場合を除き」、 当該修繕 の実施を拒否することができない。
8. ○ 借主は、貸主に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、 本 契約を解約することができる。
9. ○ 借主は、 貸主に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、 本契約を解約することができる。もっとも、これにかかわらず、借主は、 解約申入れ の日から30日分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。) を貸主に支払うこ とにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契 約を解約することができる。
10. ○ 借主は、本契約が終了する日までに(貸主の解除の規定に基づき本契約が解除さ れた場合にあっては、直ちに)、 本物件を明け渡さなければならない。この場合にお いて、 借主は、 通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復し なければならない。
第4節 国土交通省ガイドライン
1. 本ガイドラインは、賃借人の原状回復義務とは何であるのかを明らかにし、 それに基づいて賃貸人と賃借人の費用負担の割合等について一般的な基準 を示している。
2. 建物の損耗のうち、 通常の使用により生ずる損耗等 (通常損耗) を修繕す るための費用は、 賃借人が負担する。
1. ○本ガイドラインは、賃借人の原状回復義務とは何であるのかを明らかにし、それ に基づいて賃貸人と賃借人の費用負担の割合等について一般的な基準を示している。
2. × 本ガイドラインは、建物の損耗を次の三つに区分した。 すなわち、 ①自然的な劣 化損耗等 (経年変化)、 ②通常の使用により生ずる損耗等 (通常損耗)、 ③賃借人 の故意過失、 善管注意義務違反、 その他通常の使用を超えるような使用による損 耗等である。 そして、 ①と② による損耗等を修繕するための費用は 「賃貸人」 が負 担するものとし、 ③の損耗等を修繕するための費用は、 賃借人が負担するものとし ている。
第5節 東京ルール
1. 宅地建物取引業者は、住宅の賃貸借の代理又は媒介をする場合は、当該住 宅を借りようとする者に対して宅地建物取引業法第35条第1項の規定によ り行う同項各号に掲げる事項の説明に併せて、退去時における住宅の損耗等 の復旧や住宅の使用及び収益に必要な修繕について、 これらの事項を記載し た書面を交付して説明しなければならないとされている。
1. ○ 宅地建物取引業者は、 住宅の賃貸借の代理又は媒介をする場合は、当該住宅を借 りようとする者に対して宅地建物取引業法第35条第1項の規定により行う同項各号 に掲げる事項の説明に併せて、退去時における住宅の損耗等の復旧について (原状 回復)や住宅の使用及び収益に必要な修繕について (入居中の修繕) といったこと について、 これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならないとされ ている。
第六章 委任契約
第1節 民法 (委任契約)
1. 委任契約は、特約をした場合に限って無償契約とすることができる。
2. 委任契約の受任者は、無償契約の場合であっても、善良なる管理者の注意をもって事務の処理を行わなければならない。
3. 委任契約を締結した場合、委任者からは特別の理由なく委任契約を解除できるが、受任者からは特別の理由がなければ解除できない。9099 S SIC SINロ
4. 受任者は、委任された事務の処理について、事務の継続中 委任者の請求 がなくても、定期的に報告しなければならない。
5. 受任者が委任事務を処理するにあたって必要と認められる費用を支出し たときは、委任者に対してその費用の償還を請求できるが、これに利息を付 することはできない。
1. × 委任契約の受任者は、特約があるときでなければ、委任者に対して報酬の請求をすることができない (民法648条1項)。 本肢は原則と例外が逆である。
2. ○ 委任契約の受任者は、委任の本旨に従って、善良なる管理者の注意をもって委任 事務の処理を行わなければならない (民法644条)。 これは、有償・無償を問わない。
3. × 委任契約においては、委任者 受任者のいずれからでも、特別の理由なく自由に 契約を解除することができる(民法651条1項)。 委任契約は当事者間の信頼関係を 基礎とする契約であるため、 相手方が信頼できない場合に自由に解除することを認 めたのである。従って、 受任者からの解除にも、 特別の理由は不要である。
4. × 受任者は、委任者の請求があった場合、及び、委任が終了した場合に、委任され また事務の処理について報告しなければならない (民法645条)。 従って、委任事務処 理継続中は特約がない限り、 委任者の請求がなければ受任者に報告する義務はない。
5. × 受任者が委任事務を処理するにあたって必要と認められる費用を支出したときは、 委任者に対してその費用及び支出の日以後の利息の償還を請求できる(民法 650 条 1項)。
第七章請負契約
第1節 民法 (請負契約)
1. 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕 事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を 生ずる。
2. 請負契約における報酬の支払いは、原則として、仕事の目的物の引渡しと 同時に行う。
3. 屋上防水の改修工事について、 工務店と請負契約を締結した場合、工事が 4割程度完成した場合でも、注文者は損害賠償をすれば、請負契約を解除す ることができる。
1. ○ 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、 相手方がその仕事の 結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる (民法632条)。
2. ○ 請負契約における報酬の支払いは、仕事の目的物の引渡しと同時に行う (民法 633 条本文)。 なお、物の引渡しを要しない請負契約の場合は、業務終了後に報酬を支払 (同条ただし書)。
3. ○ 請負人が仕事を完成するまでの間は、注文者は、いつでも損害を賠償して、 契約 の解除をすることができる(民法641条)。
第2節 担保責任
1. 品確法の適用のある新築住宅の請負契約において、 請負人又は売主が瑕疵 のある目的物を注文者又は買主に引き渡した場合において、注文者又は買主 がその瑕疵を知った時から3年以内にその旨を請負人又は売主に通知しな いときは、 注文者又は買主は、原則として、その瑕疵を理由として、履行の 追完の請求 報酬の減額の請求 損害賠償の請求及び契約の解除をすること ができない。
2. 品確法の適用のある新築住宅の請負契約において、 請負人が注文者に対し て担保責任を負う期間は、 引渡から10年であるが、 この期間は、 特約によ り20年まで延長することができる。
1. × 品確法の適用のある新築住宅の請負契約において、 請負人又は売主が瑕疵のある 目的物を注文者又は買主に引き渡した場合において、注文者又は買主がその瑕疵を 知った時から 「1年以内」 にその旨を請負人又は売主に通知しないときは、 注文者 又は買主は、原則として、その瑕疵を理由として、 履行の追完の請求、 報酬の減額 の請求 損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2. ○ 品確法の適用のある新築住宅の請負契約において、 請負人が注文者に対して担保 責任を負う期間は、原則として、 引渡しから10年であるが、 この期間は特約により 20年まで延長することができる。 なお、請負契約において、 引渡しから10年経過す る前であっても、瑕疵によって目的物が滅失・損傷した場合は、その滅失・損傷の ときから1年以内に瑕疵修補を請求しなくてはならない。
第八章 訴訟関係
第1節 民事訴訟
1. 民事訴訟法によれば、訴えは、原則として、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2. 民事訴訟法によれば、 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を 定めることができる。
3. 少額訴訟は、簡易裁判所だけでなく、 地方裁判所に対しても訴えを提起す ることができる。
4. 少額訴訟においては、被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述を することができる。
5. 少額訴訟においては、 相手方は反訴を提起することができないが、 終局判 決に対して控訴をすることはできる。
6. 少額訴訟において、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限 りすることができる。
7. 少額訴訟は、原則として1回の期日で審理を終了し、口頭弁論後1ヵ月後 に判決が言い渡される。
8. 支払督促の申立ては、その請求額が30万円以下の場合に限ってすること ができる。
9. 支払督促において適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に保 る請求については、その目的の価額に従い、 支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄すある地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
10. 仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。
11. 公示送達によらなければ被告に対する最初の口頭弁論期日の呼出しをす ることができない場合は、少額訴訟による審理及び裁判をすることができない。
1. ○ 訴えは、 被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する (民事訴訟 法4条1項)。 なお、人の普通裁判籍は、住所等により定まる (同法4条2項)。
2. ○ 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる(民事訴 訟法11条1項)。 合意による管轄とは、当事者の合意によって生じる民事訴訟法で 定めている管轄と異なった管轄をいう。 当事者の利益を考慮して設けられている規 定である。
3. × 訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、 簡易裁判所に対して、 少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる(民訴法 368条1項)。 少額訴訟は簡易裁判所のみで取扱われる。
4. ○ 少額訴訟においては、 被告は、 訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をするこ とができる(民事訴訟法 373条1項本文)。 迅速簡易な審理を求めるか、慎重な審理 を求めるかを原告の意思によって決定させていることとの公平を図っている。
5. × 少額訴訟においては、 反訴も控訴も認められない (民訴法369 条、 377条)。
6. ○ 少額訴訟においては、 証拠調べは、 即時に取り調べることができる証拠に限りす ることができる (民事訴訟法 371 条)。 一期日審理の原則を採用しているからである。
7. × 少額訴訟は、原則として1回の期日で審理を終了し、 口頭弁論後 「直ちに」 判決 が言い渡される (民事訴訟法 374条1項)。 少額訴訟は、簡易 迅速に裁判が行われ 制度だからである。
8. × 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について は、債権者の申立てにより、 裁判所書記官が支払督促を発することができる(民事 訴訟法 382条)。 しかし、 30万円以下の金額に限る制限はない。
9 .○ 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、 支払督促の申立ての時に、 支払督促を発した裁判所書記官の所 属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったもの とみなす (民事訴訟法 395条1項)。
10. ○ 仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督 異議の限度で効力を失う (民事訴訟法 390条)。 なお、仮執行の宣言 「後」に督促 異議の申立てがなされても、 支払督促はその効力を失わない。
11. ○ 公示送達によらなければ被告に対する最初の口頭弁論期日の呼出しをすることが できない場合は、少額訴訟による審理及び裁判をすることができない(民事訴訟法 373条3項3号)。 「公示送達」とは、受送達者が所在不明等により、訴訟上の書類を 送達できない場合に行われる送達方法である。この場合、 被告が現実に呼出しを了 知することが少なく、 少額訴訟で審理することは適当でないからである。
第2節 ADR
1. ADRは、一般に、 裁判内紛争解決制度と言われる。
2. ADRを手続きの種類で分類をすると、 一般に、 助言型、 調整型、 裁断型 といったものに分類できる。
3. ADR法によれば、民間事業者の行う和解の仲介の業務に関し、その適正 さを確保するため、一定の要件に適合していることを法務大臣が認証する制 度を設け、認証を受けた民間事業者の和解の仲介業務には、時効の中断・訴 訟手続の中止といった法的効果が与えられる。
1. × ADRは、 Alternative Dispute Resolution の略称であり、 一般に裁判 「外」 紛 争解決制度と訳される。 これは、身の回りの紛争について、 裁判以外の手続きによ って解決を図る制度である。
2. ○ ADRを手続きの種類で分類をすると、 助言型 (当事者間の自主的な解決を促す ために第三者が助言を行うもの。相談など。)、調整型 (当事者間の合意により紛争 の解決を図ろうとするもの。 調停、 あっせんなど) 裁断型 (あらかじめ第三者の審 理判断に従うという一般的な合意の下に手続を開始するもの。 仲裁など)といっ たものに分類できる。
3. ○ ADR法とは 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」のことであるが、 これによると、 民間事業者の行う和解の仲介の業務に関し、その適正さを確保する ため、一定の要件に適合していることを法務大臣が認証する制度を設け、認証を受 けた民間事業者の和解の仲介業務には、 時効の中断・訴訟手続の中止といった法的 効果が与えられる。
第九章 その他
第1節 債権の担保 (民法)
1. 保証契約とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人が主たる 債務者の代わりに債務を履行する義務を負うとする契約であり、主たる債務 者と保証人との契約(保証委託契約)に基づいてなされる。
2. 連帯保証契約における連帯保証人は、保証人と異なり、 催告の抗弁権や検 索の抗弁権を有しない。
3. 抵当権においては、債務者が抵当権設定者となり、 それ以外の者がなることはできない。
4. 抵当権を成立させるためには、書面の作成と登記が必要である。
5. 建物に抵当権を設定した場合、その建物の敷地である土地にも抵当権の効力が及ぶ。
1. × 保証契約は、 主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人が主たる債務者の 代わりに債務を履行する義務を負うとする契約であるが (民法446条1項)、これは 債権者と保証人との契約であり、主たる債務者と保証人との契約(保証委託契約) は必ずしも必要でない (判例)。
2. ○ 出たる債務に対して二次的な地位にある保証債務と異なり、 連帯保証債務には補 性がない。 従って、 連帯保証人は催告の抗弁権 検索の抗弁権を有しない(民法 454条、 452条、 453条)。
3. × 抵当権者は、 ① 債務者、又は②第三者 (物上保証人)が債務の担保に提供した不 動産につき他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受ける権利を有する(民法369 条1項)。 従って、 債務者以外の第三者が抵当権設定者となることができる。
4. × 抵当権は、抵当権者と抵当権設定者との合意により成立する (諾成契約)。 従って、 抵当権の成立に、 書面の作成や登記は不要である。
5. × 土地と建物は別個独立した不動産である(民法 86条1項、 不動産登記法14条) ため、建物に抵当権を設定した場合でも、その建物の敷地である土地に抵当権の効 力は及ばない。
第2節 不法行為 (民法)
1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって、他人に損害を生じたときは、所有者又は占有者が責任を負う。
2. ある事業のために他人を使用する者は、 被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害について、 常に賠償する責任を負う。
3. B所有のマンションの301号室が原因となる水漏れにより、A所有の 201 号室に水漏れ被害が生じた場合、 Bに過失がない場合には、AはBに対し、 損害の賠償を請求することができない。
4. Bの所有するマンションの301号室の水漏れによりAの所有する201号室 に水漏れ被害が生じた場合、 301 号室の水漏れがC工務店の粗悪な工事が原 因であった場合において、BがAに請求されて損害を賠償したときは、Bは、 Cに対して求償することができる。
5. 使用者は、被用者がその職務と全く無関係に行った私生活上の行為により 第三者に損害が発生したときには、 使用者責任を負わない。
6. 未成年者が他人に損害を加えた場合において、その未成年者が当該行為の 責任を弁識することができる知能を備えていないときは、その行為について 損害を賠償する責任を負わない。
1. ○ 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって、他人に損害を生じたと きは、所有者又は占有者が責任を負う (民法717条1項)。
2. × ある事業のために他人を使用する者は、原則として被用者がその事業の執行につ き第三者に加えた損害を賠償する責任がある(民法715条1項本文)。 しかし、 使用 者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意を払っていた場合、又は 相当の注意をしていても損害を免れ得ない場合には、この使用者責任は生じない (民 法 715条1項ただし書)。
3. × 土地の工作物 (マンションの専有部分もこれにあたる) の設置又は保存の瑕疵に よって他人に損害 (水漏れ被害もこれにあたる) が生じた場合、 その工作物の占有 者及び所有者は、損害の賠償責任を負う (工作物責任、 民法 717条1項)。 Bは301 号室 (土地の工作物) の所有者であるから、損害賠償責任を負い、 所有者であるた め無過失の責任を負う。
4. ○ Bは、 301 号室の設置又は瑕疵によるAの損害につき損害賠償責任を負うが(民法717条1項)、この瑕疵の原因がCにある場合には、BはCに対して求償権を行使す ることができる(民法717条3項)。
5. ○ 使用者責任が成立するためには、 「事業の執行に付き」 なされることが必要である (民法715条1項)。 しかし、 被用者が職務とはまったく無関係に行った私生活上の 行為によって生じた損害は、 「事業の執行に付き」 生じた損害とはいえない。 従って 使用者は、当該損害が発生したときでも、使用者責任を負わない。
6. ○ 未成年者が他人に損害を加えた場合において、その未成年者が当該行為の責任を 弁識することができる知能を備えていないときは、その行為について損害を賠償す る責任を負わない (民法712条)。
第3節 相続 (民法)
1. 相続は、被相続人の死亡だけを原因として開始する。
2. 相続人は、被相続人の一身に専属したものを除いて、被相続人が有していた一切の権利義務を承継する。
3. 相続人となることができる者と、実際の相続人とは常に一致する。
4. 相続分とは、相続人が数人いる場合における各相続人が承継する被相続人 の財産の割合のことをいうが、配偶者と子が相続人である場合、相続分は、 配偶者が3分の2、 子が3分の1となる。
5. 相続財産が金銭の場合、 法律上当然に分割され、共同相続人は、当該金銭 を保管している他の相続人に対して、自己の相続分について引渡し請求をす ることができるが、相続財産が金銭債権・金銭債務の場合は、相続分に応じ て当然に分割されない。
6. 限定承認とは、相続人が承継する積極財産の限度で相続債務等の責任を負 うという留保をつけて相続することをいうが、かかる限定承認は、 共同相続 人が個々に行うことができる。
7. 相続の承認 放棄がなされても、一定の期間内は自由に撤回できる。
8. 相続放棄とは、 相続財産の承継を一切拒否することをいうが、これをする と、その者は最初から相続人ではなかったことになる。
9. 遺留分とは、一定の相続人のため、法律上必ず確保されなければならない 一定額のことをいう。
1. ○ 相続は、被相続人の死亡だけを原因として開始する。
2. ○相続人は、被相続人の一身に専属したもの (委任者、受任者たる地位など)を除 いて、被相続人が有していた一切の権利義務(不動産の所有権等の財産、さらには、 契約当事者の地位や、 善意悪意、故意・過失といった主観的事情)を承継する。
3. × 相続人となることができる者の範囲は法律で定められており、その中でも相続の 順位がある。 また、相続できる順位にあっても、相続放棄、排除、相続欠格により 相続しない場合があるので、相続できる者と実際の相続人は、 異なることもある。
4. × 相続分とは、 相続人が数人いる場合における各相続人が承継する被相続人の財産 の割合のことをいう。 配偶者と子が相続人である場合、 相続分は、配偶者が2分の 1、 子が2分の1となる。
5. × 相続財産が 「金銭債権 金銭債務」 の場合は、原則として、法律上当然に分割さ れ、各共同相続人がその相続分に応じて権利・義務を承継する。 しかし、相続財産 が 「金銭」 の場合、 共同相続人は、 当該金銭を保管している他の相続人に対して、 自己の相続分について引渡し請求をすることはできない。
6. × 限定承認とは、 相続人が承継する積極財産の限度で相続債務等の責任を負うとい う留保をつけて相続することをいう。 限定承認は、 共同相続人全員が共同して行わ なければならない。
7. × 一度なされた相続の承認 放棄は、原則として撤回できない。これを認めると、 法律関係が不安定になり、利害関係人に不利益を与えるからである。 ただし、意思 表示に関する規定に基づき、 取消しを主張することはできる。
8. ○ 相続放棄とは、 相続財産の承継を一切拒否することをいう。 かかる相続の放棄を すると、その者は最初から相続人ではなかったことになる。
9. ○ 遺留分とは、一定の相続人のため、法律上必ず確保されなければならない一定額のことをいう。
第4節 個人情報の保護 (個人情報保護法)
1. 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも のをいうが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものまでは含まれない。
2. 個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場 合等を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の 達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
3. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、原則として、あらか じめその利用目的を公表している場合であっても、速やかに、その利用目的 本人に通知し、又は公表しなければならない。
4. 個人情報取扱事業者は、 法令に基づく場合 人の生命、身体又は財産の保 護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場 合等を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に 提供してはならない。
1. × 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報 と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができること となるものを含む。)をいう。
2. ○ 個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合 人の生命、身体又は財産の保護のた めに必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合等を除くほ か、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を 超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
3. × 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、原則として、 あらかじめそ の利用目的を公表している場合を除き」、 速やかに、その利用目的を、 本人に通知 し、又は公表しなければならない。
4. ○ 個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合、 人の生命、身体又は財産の保護のた めに必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合等を除くほ か、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
第5節 住宅性能表示制度 (品確法)
1. 日本住宅性能表示基準は、 住宅の性能に関し 「構造の安定に関すること」 「火災時の安全に関すること」 などの項目について、 等級や数値等で表示す るものとしている。
2. 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅について、 建設工事の請負契約又 は売買契約に関する紛争が生じた場合、当該紛争の当事者は、指定住宅紛争 処理機関に対し、当該紛争のあっせん、調停、仲裁を申請することができる。
3. 住宅性能評価の制度は、既存中古住宅には適用されない。
1. ○ 日本住宅性能表示基準は、住宅の性能に関し 「構造の安定に関すること」 「火災時 の安全に関すること」 などの項目について、 等級や数値等で表示することを定めて いる
2. ○ 指定住宅紛争処理機関は、 建設住宅性能評価書が交付された住宅 (評価住宅)の 建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請 により、当該紛争のあっせん、 調停及び仲裁の業務を行う。
3. × 品確法上の 「住宅」 には、 既存の中古住宅も含まれる。 従って、 住宅性能評価の 制度は、 既存住宅にも適用される。 なお、品確法上の瑕疵担保責任の特例の適用が あるのは 「『新築』 住宅」 のみであり、これと混同しないよう注意が必要である。